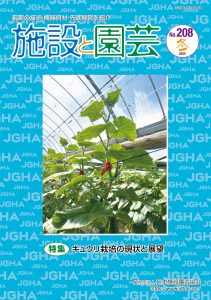〝国消国産〟特別号

生源寺眞一氏の特別インタビューも掲載
〈本号の主な内容〉
■10月・11月は「国消国産月間」
JAグループが東京・丸の内で国消国産をPR
■令和7年度(第64回)農林水産祭 実りのフェスティバル
10月31日~11月1日 サンシャインシティ ワールドインポートマートビルで
■令和7年度農林水産祭
天皇杯に、おしの農場、佐藤勲氏、ヤマニファーム等7点
■特別インタビュー
農業・農政の現状と課題を語る
(公財)日本農業研究所 研究員
東京大学・福島大学 名誉教授
生源寺眞一 氏
■お米の食パン 米粉専用品種で広がる用途
~国産を食卓に~ JA全農の取組み
■㈱富澤商店と全農のニッポンエールがタイアップ
専用品種「笑(え)みたわわ」原料の米粉 パン用・製菓用を今月販売開始
優れた改良品種と「湿式気流粉砕」製粉で高品質を実現
■RICE TASTE MAPで お好みのお米を探そう!
■〈JA全農グループの飲食店舗〉みのりみのるのお店、焼肉店舗など
特別インタビュー
農業・農政の現状と課題を語る
(公財)日本農業研究所 研究員
東京大学・福島大学 名誉教授
生源寺眞一 氏
コメ価格高騰など様々な要因が重なるなか、食料安全保障への関心が広がっている。食料・農業・農村政策審議会会長等を務めてきた、東大・福島大名誉教授で(公財)日本農業研究所研究員の生源寺眞一氏に、情勢認識や今後について聞いた。(本紙姉妹紙の『日刊アグリ・リサーチ』1万5000号特別インタビュー〔2025年10月10日号〕から)
「令和のコメ騒動」と農政の対応
コメ論議、短期対応と構造問題が混在
そもそも昨年8月、日向灘沖を震源とする最大震度6弱の地震を受けて発表された「南海トラフ地震臨時情報」が引き金になった。全国で海水浴場の閉鎖やイベントの中止といった対応が取られ、直後から人々がコメの買いだめに走り、首都圏などの店頭でもコメがなくなった。そうした状況下で、初めは流通の「目詰まり」といった説明をしていた政府の対応も次第に変わるとともに、備蓄米の放出にも至ったが、端的にいえば、短期的な変動への対応に失敗して問題を拡大させてしまった面がある。
その後の現在までの議論を見ると、短期的な対応の問題と、平時のコメ生産の課題、すなわち農業や稲作が抱える構造的な問題が混同されてしまっている。今の騒動が始まる前、コメの需給バランスは落ち着いていて、その中で担い手の確保など構造的な問題が議論されていた。ところが、騒動後は両者の問題が区別されることなく、むしろ構造問題についても短期の対応の延長線上で考えるような形で、非常に議論が錯綜してしまった。
こうした議論のあり方は食料安全保障にも関わる。食料・農業・農村基本法で食料安全保障は「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義されている(第2条)。英語のフード・セキュリティを食料安全保障と訳したのだが、これは日々の食生活をどうするかという問題と、不測の事態にどう対応するかという問題の両方をカバーしている。ただし、実態としてフード・セキュリティの大半は、途上国の貧困層の日々の食生活の問題として捉えられていた。
一方、現在のガザ地区やウクライナなど、戦争状態によって食料が確保できない人々の問題があり、日本でも地震をはじめとする災害時などの不測の緊急事態における食料確保の問題がある。つまり、食料安全保障という言葉で一括りにしているが、日本でも徐々に増えつつある毎日の食料へのアクセスに苦しむ低所得者の問題と、自然災害や国家間の紛争によって市場経済自体が機能不全に陥るような事態における食料確保の問題の両面がある。いずれも重要だが、対応策はそれぞれ違うはずで、ごちゃごちゃに扱ってしまうのは危険だ。同様に、今回のコメ騒動は短期的な問題であり、コメ作りの担い手などの長期的な問題とはきちんと分けて議論すべきだと思う。
国の政策決定と責任
トレーサビリティを欠く危うさ
政府はこの間、不作や災害時に限って放出するとしていた備蓄米を、流通が滞っていると判断した場合にも放出できるよう運用を見直した。その際、売り渡した備蓄米と同じ量のコメを1年以内に買い戻す新たな仕組みを作ったが、私は「政府はしっかりと検討することなく、これまでになかったことに取組もうとしている。危ないな」と感じた。実際には放出後、この仕組みは見直されたが、そんな政府の対応の変化がさらなる不安やリスク回避の行動を呼び起こし、騒動がいっそう膨らんでいく結果を招いた。研究者として申し上げれば、一連のコメ問題は落ち着いてから検証をしっかりすべきだ。
というのも、安倍政権以降の官邸主導の政治では、外部の誰かが発言し、それを具体化するという形で政策が進められるケースが目立った。例えば、コメの減反(生産調整)に関しても、2013年に新浪ローソン社長(当時)が産業競争力会議の農業分科会で廃止を発言し、2018年に形式上は廃止された。これに限らず、誰かがどこかで行った発言によって、政策が打ち出されることが多々あり、どういう経緯で導入され、どういう結果を生んだかについて事後的にトレースできない類の政策決定が少なからずあった。
私は国の食料・農業・農村政策審議会会長を2017年まで務めたが、「審議会として責任を果たせていない」という趣旨の発言をしたことがある。農業競争力強化プログラムについて事後報告を受けた時で、審議会は農政、農業の問題について意見を具申する立場にあるにもかかわらず、全く別のところで農政が動いていた。したがって、問題がどこから投げ込まれ、どういう形で検討され、結果的にどこが責任を取るかが分からなくなる。のみならず、それを政府関係者も明らかにしない。これは政策のトレーサビリティ(追跡可能性)を欠く状態で、非常に深刻な事態だったと思う。
ある人物が政策に関わる思いを発言しながら、数か月後にはその場からいなくなる。あるいは公的な組織とは別のところにいる人物が自身の思いから発言するといった状態では、責任ある発言によって新しい政策を提案するという道筋が立たなくなる恐れさえ出てくる。農政に限らず、国の制度や政策に、こうした共通する危うさが感じられる。その意味で、今回のコメ問題についても経緯をトレースすることによって、政策決定における責任を明確化し、評価を明らかにすることで、政策の形成システムの健全性を取り戻す必要がある。
新たな基本計画と「みどり戦略」
生産性向上と環境負荷軽減の二兎得る
改正法に基づく初の食料・農業・農村基本計画では1年ごとの検証が謳われている。政策のさまざまな要素について、目標に対応するKPIは統計データなどに基づいて評価できるので、検証は可能だ。特に食料自給率の目標は、以前から基本計画で設けていたが、一度も達成状況を評価していなかったことを考えると、検証を打ち出したのはいいことだ。
環境と調和の取れた持続可能な農業を目指す「みどりの食料システム戦略」に注目している。この戦略自体は基本法改正より前に、法律も含めてスタートしていた。戦略のサブタイトルにある「食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現」という方向性は、私自身が現在の農業に向き合う感覚ともよくマッチしている。「二兎を追う者は一兎をも得ず」ではなく、いわば「二兎を追って二兎を高いレベルで得る」。つまり、食料の生産性向上と、環境への負荷軽減の両立を図るという目標は真っ当だ。
みどりの戦略には、農水省でもどちらかというと農学系の人々が具体的な詰めを行いながら策定した面もあるようだ。2050年までに全耕地面積に占める有機農業の割合を25%に拡大するといった個々の目標の妥当性はともかく、構えとしては生産力と持続性の両方を、それぞれ高いレベルで達成を目指すもので、現代の農業の実態をよくつかんだうえで打ち出されている。若い新規就農者のあいだでは有機農業に興味を持ち、取組もうというケースも比較的増えており、前進する可能性は大いにあると思う。
これからの農業の担い手
多様な価値・形態が地域で連携
大前提として、経済成長一本やりの時代はもう終わったと考えるべきだ。成熟社会への移行期にある現在、規模を拡大して生産性を上げて販売額を増やすタイプの農業者が頑張る一方、別の仕事をしながら農業も営む「半農半X」といった人々もいて、両者が共存できるような時代を迎えている。
農地をめぐっては、借り手をいかに確保するかが最大の問題になっている。かつては小規模な兼業農家が安定して農業を継続していたため、農地を借りて規模を拡大することが難しい「貸し手市場」だったが、今は兼業農家の後継者が急減していて、借りたいといえば、ほぼ借りられる「借り手市場」に変わった。特に水田農業は高度成長期以降、兼業農家が支えてきたといっても過言ではないが、その子供たちが農業から離れ、後継者がいなくなり、余った農地がどんどん出てきた。兼業農家の存在が、専業農家や農業法人の規模拡大の妨げになる状況はなくなった。
また、49歳以下の若手就農者の過半は、非農家出身者が占めている。その地で生まれ育った人ではない若者や中堅の人々が農業に取組むわけだが、農業に対する考え方はさまざまだ。会社勤めの10年を経た後、中山間地域で自家消費分ぐらいの農業生産に取組み、残りの時間はテレワークで仕事を続けるという人もいる。あるいは小規模農業の選択も、中山間地域のような農村らしい場所に暮らすこと自体に価値を見いだす場合もある。2地域居住も増えていくだろう。
動機や形態はさまざまだが、新規就農者を含む若い世代の農業者は自分の意思で選択し、判断して農業に取組むようになった。従来の成長一本やりの時代とは違う形で、多様なタイプの農業が地域社会で連携しながら、互いを認め合うような形になりつつあると思う。
農業人材の確保・育成
「生き物を育てる」価値の見直しを
新聞の農業報道に関して気になるのは、地方紙では地域の農業のさまざまなケースを紹介する記事もそれなりにあるが、全国紙では衰退産業、人手不足、高齢化といった決まり文句によるネガティブな評価が定着していることだ。かつては全国紙にも長年農業を担当し、長期的な観点から現場に即した判断のできる記者もいたが、今は担当者が2、3年で頻繁に交代し、深く取材する記者が少なくなった。若い世代、特に小・中・高校生にとって、農業のイメージを形作るうえで、新聞報道のトーンが影響している気がする。
農業者教育に関してはいろいろなタイプが必要で、農業高校や農業大学校のほか、農業経営者の育成を目指す(一社)アグリフューチャージャパンや、酪農教育ファームなどのように、子供のうちに農業や家畜に触れる機会もある。
農業については、国土保全や景観形成のような多面的機能のあることが強調されてきたが、副産物だけでなく、農業そのものの価値も考え直すべきだ。農業は生き物という自ら育ちゆくものを育てる営みで、人を育てる学校教育と重なる面がある。うまくいかない場合もあるし、対象とする相手にも個性がある。これに対し、製造業はあくまで材料となるモノが相手だ。
その意味で、農福連携に注目している。もともと障がい者雇用の推進策として進められ、ひきこもりの若者や認知症の高齢者なども含めて、人々が農業生産に取組むことを通じて、生きがいを見いだす場となっている。これは製造業と異なる農業の本質的な価値に関わってくるし、そんな認識が農業分野における働き手の確保にもつながる。こうした農業の持つ力を多くの人々にきちんと伝えたいものだ。
協同組合としての農協
「自主・自立」の大原則に立ち返れ
2015年の農協法改正では、第7条にJAや連合会の事業目的として「農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない」と明記された。自主・自立が国際的にも認められた協同組合の大原則である点から見ると、こうした目的は本来、法律で規定するのではなく、協同組合が協同組合自身で決めることで、農協法の改正には違和感があった。近年は各単協が個性的になってきており、互いに学ぶこともできる。2025年は国際協同組合年(IYC)でもあるが、もう一度、原則に立ち返り、協同組合としての農協を見つめ直す必要がある。
関連して、農協や生協などをカバーする協同組合に関する基本法を作る動きにも注目したい。今後の農協にとって重要なのは、農業者のあり方がますます多様化していくと予想されることだ。既に、農協の販売ルートは部分的に活用し、そのほかの農産物は自分でルートを作って販売するといった選択が行われるようになっている。そうした変化を踏まえた対応も必要になるだろう。