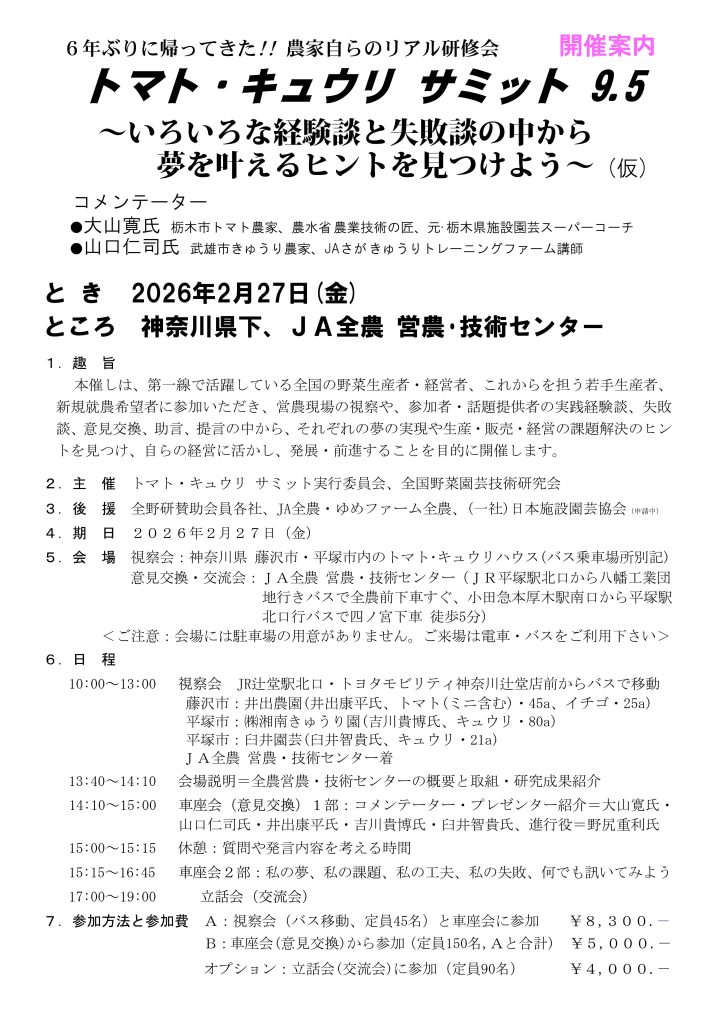〈本号の主な内容〉
■このひと
新たな「酪肉近」の方向と畜産行政
農林水産省 畜産局長 長井俊彦 氏
■家の光文化賞JAトップフォーラム 2025
家の光文化賞農協懇話会、家の光協会が開催
「経営的視点による教育文化活動の展開~協同活動と総合事業の好循環を実現する~」テーマに
■JA全農 令和7年度事業のポイント
畜産総合対策部 佐藤勧 部長
畜産生産部 富所真一 部長
酪農部 服部岳 部長
■蔦谷栄一の異見私見「首都圏での流域自給圏づくりからの食料安全保障確立」
 このひと
このひと
新たな「酪肉近」の方向と畜産行政
農林水産省
畜産局長
長井俊彦 氏
4月、新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」(=「酪肉近」)が公表された。7月に畜産局長に就任した長井俊彦氏(前 大臣官房長)に、そのポイントを聞いた。
生産コストの上昇・高止まり続く
■畜産・酪農を取り巻く課題をどのように捉えるか。
畜産は、耕種部門に比べると規模が大きくまさに「経営」と言える。兼業の概念が少なく、専業的な面からみた課題があげられる。
日本の畜産・酪農は濃厚飼料を輸入に頼っている。ウクライナ紛争以来国際情勢の影響を受け、飼料価格の高騰をはじめ、資材・エネルギー価格の高騰が経営に大きな影響を及ぼしている。特に酪農の離農が顕著だ。
生乳の需給緩和による脱脂粉乳の在庫の積み上がりや、枝肉価格の低下などによる販売環境も厳しい。また、家畜のメタンガスの排出など、地球温暖化対策にも配慮しなければならない。環境や持続性に配慮した畜産物生産の必要性が世界的に高まっている。
〝売れるもの〟をきちんと生産する
■こうした変化を受けた対応方向は。
ニーズをつかみ、売れるものをきちんと生産することが大事だ。昨今では、例えば牛肉も〝霜降り〟指向だけでいいのか。消費者の好みは多様化してきている。牛乳の特に冬場の消費拡大はどうしたらいいのか。消費してもらう場面や世代を増やしていかなければならない。輸出も含めて需要をきちんとつくっていかなければならない。経営改善の取組みとともに、需要をしっかりつくり喚起することが大事だ。
飼料では、濃厚飼料は海外との価格競争のなかで増やすことは難しい。耕種農家と連携して粗飼料を出来るだけ増やしていかなければならない。
値ごろ感ある国産牛肉の需要拡大
■「酪肉近」で示された主な対応方向は。
生乳では、国産ナチュラルチーズの競争力強化とともに、牛乳や脱脂粉乳の商品開発と需要拡大の推進、牛乳や乳製品の輸出促進などを図っていくことが必要だ。
牛肉では、和牛特有の脂肪交雑の強みは活かしつつ、美味しさに関する要素にも着目した改良の推進、適度な脂肪交雑の牛肉生産のための和牛早期出荷の本格化、酪農経営由来の値ごろ感のある国産牛肉の需要拡大や輸出拡大など、新規需要の開拓も見据えていかなければならない。
飼料については、国産飼料生産基盤に立脚した経営への転換促進が最大課題であり、粗飼料を中心とした国産飼料の生産・利用拡大が急がれる。
「地域計画」のなかで耕畜連携を
■持続可能な生産に向けた取組みのポイントは。
今後の生乳の生産量は、1頭当たりの乳量の回復が大きく左右するため、生産者自らが判断できるよう、見通しに必要な客観的データの情報発信を強化していく必要がある。
また、経営資源に見合った生産規模を選択し、強靭な乳用牛への牛群構成の転換をめざす。
肉用牛では、若い繁殖雌牛への更新による牛群能力の向上、繁殖における分娩期間短縮に向けたスマート技術の活用や放牧利用、経営資源に見合った規模拡大などによる生産コスト低減の推進を図る。
国産飼料の生産・利用では、畜産農家からの働きかけによる耕種農家との連携を強化していく。「地域計画」の中に飼料生産を位置付け、飼料生産組織の運営を強化していく。
地域計画のバージョンアップをめざして、畜産サイドもこれに参加し耕種農家と結び付いていけるような地域計画をつくっていく必要がある。これまで空白だった部分に自給飼料を増やしていけば、畜産農家の経営安定に繋がる。
耕畜連携は、畜産農家が働きかけないと難しい。お互いの信頼関係による取組みが多い。畜産は長い時間をかけて生産するのに対し耕種は1年が基本。その時間軸を合わせていくのには、地域計画等でお互いが話し合っていくことが大事だ。
アニマルウェルフェア(AW)については、指針を出し、取り組み状況を把握し有識者会議へ報告し議論していただいている。
難しいのはAWへの取組みに要するコストに見合うだけの評価をしてもらえるかだ。消費者にそういう取組みを理解してもらう循環をつくっていく必要がある。世界全体の潮流を見つつ付加価値を見出し消費者に理解してもらいながら生産をしていくことが重要だ。AWの認知度を高めていかなければならない。
資源循環型畜産の推進や温室効果ガス対策の推進など、環境と調和のとれた畜産経営を引き続き強化していくとともに、暑熱対策の推進もこれからの大きなポイントになってくる。
次代が継ぎたくなる畜産・酪農へ
■これらを踏まえた新たな「酪肉近」の目指す方向性は。
生乳や牛肉の需要拡大への取組みと、需要に応じた生産による需給ギャップの解消。従来の生産手法の見直しを含む生産コストの低減・生産性の向上。国産飼料の生産・利用拡大を通じた輸入飼料依存度の低減。環境負荷低減等の取組みの推進の4つが柱になる。
しっかり経営できているところには後継者がいることから、次の世代が継ぎたくなるような畜産・酪農にしなければならない。
そのためには、ニーズに合った物を生産し、コストを下げ所得を確保することが重要だ。そのための支援をしていくのが、国の使命だ。