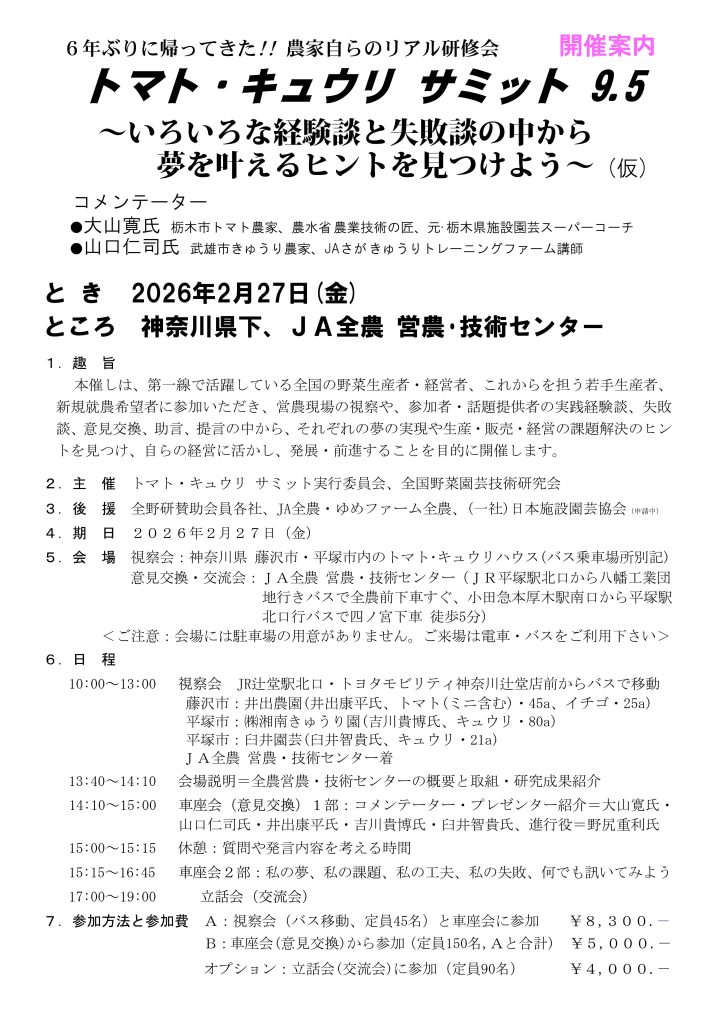改正食料・農業・農村基本法では食料安全保障の強化が最大の柱として位置づけられた。ウクライナ侵攻が穀物相場高騰のトリガーとなったが、食料安全保障についての議論は迫力に欠ける感じは否めなかった。これを一変させることになったのが令和の米騒動で、低迷していた米価が急騰する一方、深刻な農地減少・担い手不足の構造が浮かび上がり、日本農業が崩壊の崖っぷちにあることについての国民の理解がやっと広まり始めた。
こうした状況を踏まえて、この4月に食料・農業・農村基本計画が閣議決定され、その目玉として2027年度から水田政策を見直ししていくことが盛り込まれた。まさに令和の米騒動という災いを福に転じていくためにも、今回の経験をも十分に踏まえて、食料安全保障の確立が可能な抜本的見直し、制度設計が求められる。
その最大の焦点となるのは所得補償であり、先行きの収支見通しが得られる水田経営を可能にしていく条件整備が欠かせない。加えて農村整備を強化し農村を活性化させながら、安定した販売先や援農等の担い手を確保していくための関係人口の増加が必須である。このためにも消費者サイド、都市側のあり方を変えていくことがきわめて重要であり、国民をあげての総合的な対策としていくことなくして実効は期待し難い。
ここでは消費者・都市側の取組に絞って論述すると、そのポイントとなるのが三大都市圏、特に首都圏、中でも東京での取組展開である。三大都市圏で人口は全国の約半分、首都圏では3割強となり、東京だけで14百万人弱の人口を抱える。その東京の食料自給率は0%(カロリーベース)であり、都市農業があるとはいいながら、面積は限られ、そのほとんどは野菜、これに果樹や花卉が加わるものの、主食である米の生産はほとんどない。東京で世田谷区や足立区をはじめとして地産地消に力を入れているところもあるが、肝心の主食については他県に依存せざるを得ないのが実態である。
そこで提案を続けてきたのが地域自給圏づくりである。東京でお米の地産地消を図っていくことは困難であり、発想を転換して近隣の諸県とつながり、もう少し広域に地産地消の取組を拡げて、地域自給圏として取り組んでいく。具体的には東京の場合、東京湾に注ぎ込む隅田川(荒川)、中川、江戸川等の大きな河川があり、これら川の上流とつながっての流域自給圏づくりとして展開していく。下流と上流との行き来を増やし、下流の住民は米生産農家とつながって継続購入を確保するとともに、援農により田植えや稲刈りにも参加していく。消費者と生産者が提携して米等の持続的な購入を可能にしていくだけでなく、援農によって上流の生産をも支えていく、という構想である。まずは生産に関心を持つ消費者の育成・確保が必要であり、消費者も参画する都市農業の振興と都市農地の保全、あわせて各地での「農あるまちづくり講座」の展開等がこのための必要条件となる。
東京を中心にした首都圏でこれをモデル化し全国に広げていく。食料安全保障を確立していくためには、農政の転換と合わせて、都市側での民間レベル、特に協同組織が連携しての取組展開が大きなカギを握る。これは森-里-川-海の循環づくりとも重なる。
日本農民新聞 2025年9月5日号 -第1部- 掲載
(農的社会デザイン研究所代表)