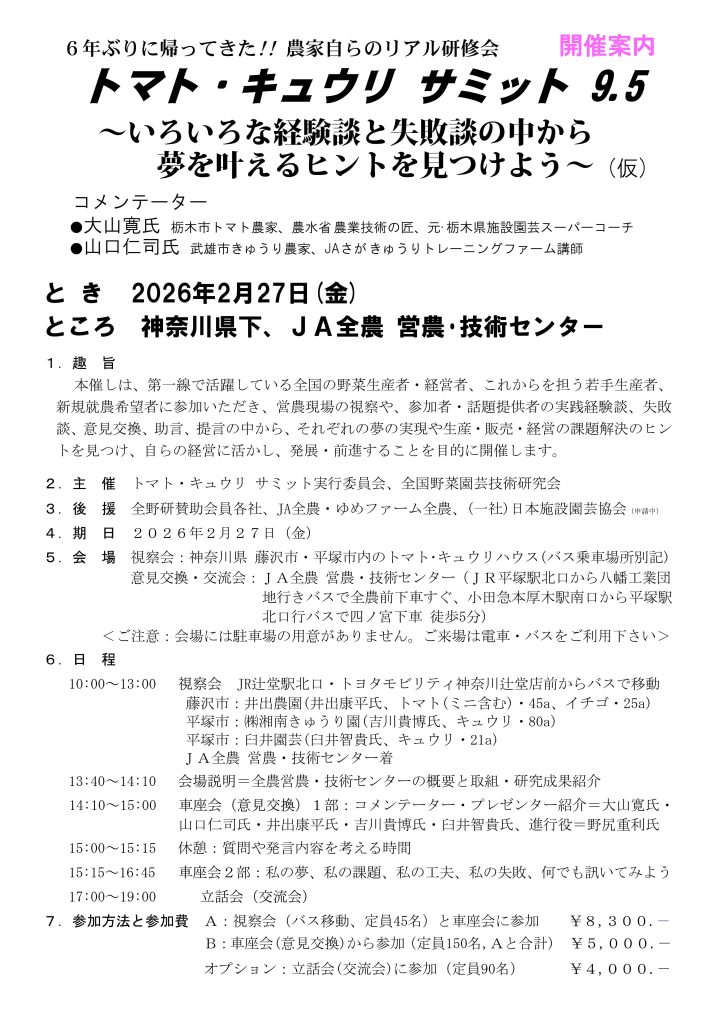〈本号の主な内容〉
■アングル
JA全青協設立70周年記念 第71回JA全国青年大会を迎えて
JA全青協 会長 洒井雅博 氏
■JA青年組織活動の現場を訪ねて
熊本県 JAかみましき青壮年部 嘉島支部の取組み
■JA全青協 設立70周年に寄せて
JA青年組織が与えてくれたもの~JA全青協会長を経験して~
JA全青協 2016年度会長 善積智晃 氏
JA全青協 2017年度会長 飯野芳彦 氏
■JA全青協 前史と70年のあゆみ
■水稲作の初期防除のポイント
JA全農 耕種資材部
 アングル
アングル
JA全青協設立70周年記念
第71回 JA全国青年大会を迎えて
全国農協青年組織協議会(JA全青協)
会長
洒井雅博 氏
次代の農業と農協組織を担うJA全青協は、令和6年5月に設立70周年を迎えた。農業・地域を取り巻く環境が益々厳しくなる中、青年世代の農業者はどう対応していくのか。70周年を記念する第71回JA全国青年大会を迎える洒井雅博JA全青協会長に聞いた。
重大な局面を乗り越え積み重ねられてきた70年
■JA全青協の最近の活動を振り返って。
昨年一年を振り返っても、農業・農政面で大きな変化が起きた年でした。新たな食料・農業・農村基本法が制定され、8月には「令和の米騒動」と言われる米不足が起き、夏場を通した猛暑から野菜の価格の高騰が止まらない状況が続いています。
こうしたなかでJA全青協は、10月に東京・丸の内で70周年記念事業としてマルシェを開催し、首都圏のみなさんに直に農家の声を伝え、食料や農業に対する理解を求めたことは大きなエポックでした。
70年の歴史は、その時々の重大な局面を乗り越え積み重ねられてきたものです。昨今では、食料の価格高騰が止まらないなかで、日本の農業の大切さをしっかりと消費者に伝えていく役割が、ますます重要になってきたと受け止めています。
青年部の原点は 全国の盟友の課題を吸い上げ解決すること
■ご自身が展開している都市農業からみた活動は。
都市近郊で農業に頑張る青年部の盟友もたくさんいます。ポリシーブックでは「都市農業部会」も設置されています。ここでの内容を整理したときの座長は、都市農業と全く関係のない県の代表が務めましたが、しっかりと全国の意見をまとめ国に提言することが出来ました。
これは青年部だからこそできることです。都市部に関係のない地域、生産緑地のない地域でも、自分達の仲間が困っていることは課題として全国段階にまで上げ解決に取組むのが全青協です。しっかりと提言をまとめ国に訴えていく姿が、70年の歴史から見ることができます。
青年部は、全国の盟友の課題をしっかり吸い上げて解決していくことに原点があると思っています。
初の女性の地区代表が発表 青年部活動の節目となる大会
■今大会で特に力を入れる点は。
今回も全国6ブロックで大会を開き、各県域の代表者の中から組織活動実績の発表者を選出しました。どの県域の代表者の発表も素晴らしく、その中から選ばれたブロック代表の優良事例です。ぜひしっかり見て、聴いて、学んで、地元に持ち帰っていただき、自分達の活動のきっかけづくりにしていただきたいと思います。
今回は、初めて九州青年部の代表として女性が発表します。これは70年の歴史のなかでの大きな進歩です。男女関係なく加入することができ、女性も大いに活躍できる組織としてのJA青年部のこれからの方向に踏み出す節目の大会になることを期待しています。
男性にはない、女性ならでは切り口、発表の仕方も大いに学んで欲しいと思います。次の10年に向け素晴らしい大会になるのではないでしょうか。
テーマは「NEVER GIVE UP!!新しい時代への前進あるのみ」。あきらめない。この10年、農業界は逆風がずっと続いていますが、我々はあきらめずに営農を続けていくなかで、地域・農村の振興に取組んでいます。
基本法が改正され基本計画が具体化されていく中で、我々もそれに合わせてしっかりと営農を続けていかなければなりません。基本計画にも次の世代である我々の意見を取り込んでもらい、地域の5年後、10年後を見据えて取組んでいかなければなりません。
70周年の記念セレモニーでは、俳優の森崎博之さんが講演します。本人も北海道で農業のTV番組をもっており、農業に対してすごく熱い思いをもった方です。農業関係者でなくても農業を熱く語りかけてくれる森村さんに、今回は登壇願いました。自分たちの活動に、もっと前向きに取組める一つの手助けになればと思っています。
農業者も消費者も〝損〟しないため 消費者一人ひとりに理解を求め
■農政に対しては。
基本計画で具体的な施策がどんどん打ち出されつつあることを踏まえて我々も活動していかなければなりません。農業者もそうですが消費者も〝損〟しないような農政が必要です。いろいろな論調が飛び交うなかで、いかに現状を消費者に理解してもらうのか。生活するうえでのコストがあがっている中で、いかにしてお互いに損をしない形で理解し合えることができるのか。国に訴え、消費者にも我々の声を伝えなければなりません。
日本の食材を買ってくれるのは日本の国民です。ここで理解が得られなければ営農している意味もなくなってしまいます。食料自給率が向上しない中で、まずは自分の地域の方々そして日本の国民のみなさんに食べて欲しいと思います。そのためには、我々もしっかり表に出て、一人ひとりの消費者のみなさんにしっかり説明していくことが重要です。
71回大会は次の10年占うような大会に
■農業の担い手としての決意を。
今の青年部世代のほとんどは、農業は厳しいが大切だという思いがあって、親世代の農業を継いだのではないかと思います。しかし、大切だという思いだけではやっていけない状況です。サラリーマンと遜色のない程度にまでしっかりと稼げなければ、次の世代に農業を職業の選択肢の一つに入れてもらえないでしょう。それができる環境を創っていかなければなりません。
経営者としての人事労務管理や企業としての役割も勉強しなければなりません。ただ、がむしゃらに農畜産物を生産するのではなく、経営者としての目線をしっかり培っていく必要があります。
■盟友へのメッセージを。
71回大会は、次の10年を占うような大会になると思います。大会での素晴らしい事例発表を、自分達の地域でいかに活用できるのか。その思いをしっかり受けとめ地域に還元していく、そうした目線をもって大会に参加していただくことを期待しています。