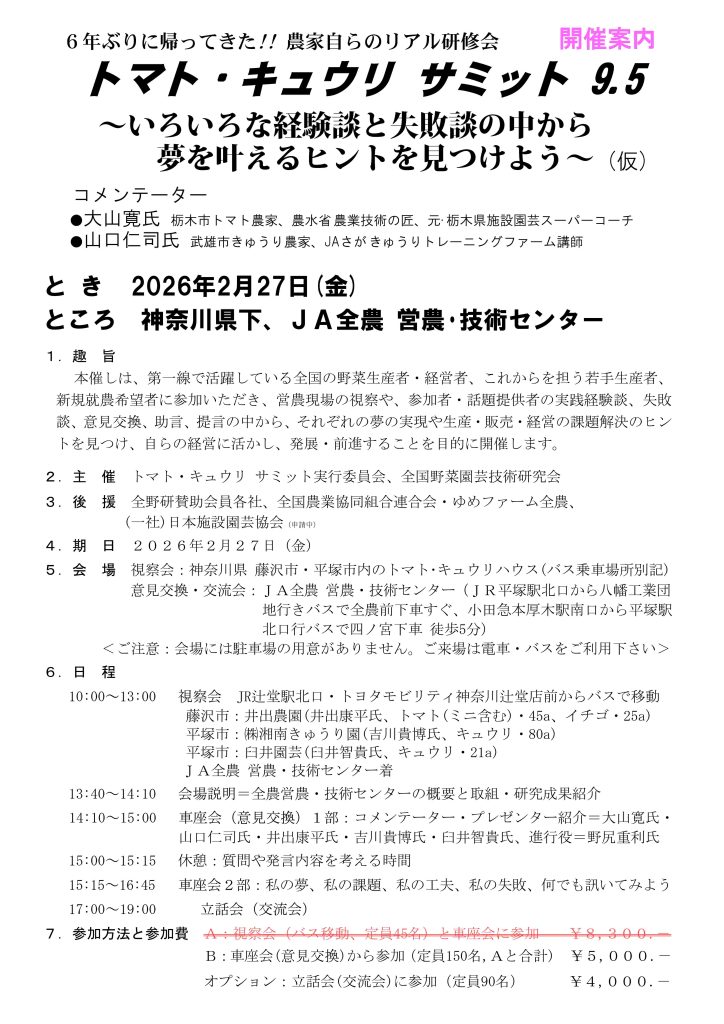水田活用直接支払交付金(水活)の「5年に一度の水張り」という支給要件が撤廃されることになった。福島県飯舘村では原発事故の影響で主食用米の作付けが減り、多くの水田で飼料用作物が生産されている。湿害に弱い牧草やトウモロコシの栽培に水張りは余計なので、見直しは朗報だ。ただ交付対象が拡大すれば単価が下がる可能性もあり、それを心配する農業者もいる。
需要が減り続ける主食用米から麦類、大豆、飼料用作物などへの転作を促す水活は広義の減反政策だ。輸入依存度の高い品目が多いので食料自給率向上につながり農地も守れる。水田を水田のまま維持するなら水張りは必要だが、その意義は薄れている。
しかし、メディアには米価高騰を背景に「減反をやめて米を増産せよ」との声があふれている。余れば輸出し、米価下落で赤字になる農家には所得を補てんすればいいという理屈だ。
1キロあたり341円の高関税を支払い、国家貿易の枠外で米を輸入する商社や流通業者が増えているという。それでも国産米より安いと聞けば、増産論もわからなくはない。
だが、米トランプ政権は高関税に同等の関税で報いる「相互関税」を打ち出した。もし、日本の米に適用されたら対米輸出は難しくなる。世界最大の経済大国が自由貿易に死刑宣告を下そうとしている時に「余ったら輸出すればいい」という楽観論が通用するだろうか。
凶作や災害などの非常時でもないのに備蓄米を放出することも決まった。国が直接的に農産物を売買して価格を操作するのは「減反」以上に古い政策手法だ。過去30年の農政は、こうした市場介入型の政策からの脱却を目指してきたのではなかったか。これを許せば、次は「値下がりしたから国が買い上げろ」という政治介入を招きかねない。
複雑に絡み合う問題が一挙に解決する「魔法の杖」はない。米以外の作物も含めた食料安全保障の構築、市場原理と規制の最適な組み合わせ、再生産可能な生産者の所得確保と農産物の値上がりに苦しむ社会的弱者への支援など、総合的な検討が必要だ。冷静でバランスの取れた、視野の広い議論を期待したい。
(いいたて結い農園勤務/農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2025年2月25日号掲載