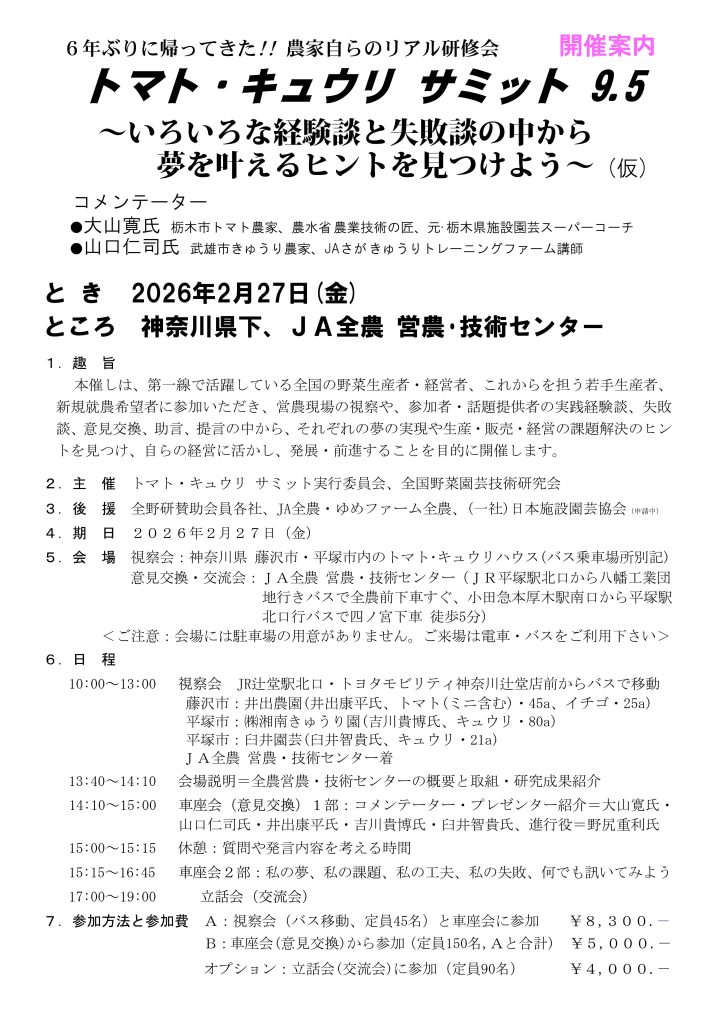〈本号の主な内容〉
■このひと
製粉業界の現状と展望
製粉協会 会長(昭和産業㈱代表取締役社長執行役員)
塚越英行 氏
■令和6年度JA助けあい組織全国交流集会 JA全中が開催
地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築へ
■第42回 全農酪農経営体験発表会
■組合員・地域とともに食と農を支える協同の力を
わがJAの取組み
~協同活動と総合事業の好循環をめざして~
・JAはだの 代表理事組合長 宮永均 氏
■かお
JA共済連 代表理事専務の 高橋一成 氏
早水徹 氏
角野隆宏 氏
JA共済連 常務理事の 関浩樹 氏
小野雅彦 氏
宮臺俊彦 氏
■YEAR’S ニュース2024
 このひと
このひと
製粉業界の現状と展望
製粉協会 会長
(昭和産業㈱ 代表取締役社長執行役員)
塚越英行 氏
製粉協会の新会長に今年8月、塚越英行氏(昭和産業㈱代表取締役社長執行役員)が就任した。地球温暖化にともなう気象変動の農業生産へのマイナス影響、地政学的リスクの高まり、国際情勢と穀物需給の不安定化等々、取巻く環境が内外ともに厳しさを増す中、国内製粉業界の現状と展望を聞いた。
業界を取り巻く環境が大きく変化
■製粉協会会長就任の抱負を。
国際情勢の不安定化にともなう世界的な原料供給不安、穀物や為替の相場変動など、製粉業界を取り巻く環境が大きく変化している。その中で製粉協会の会長に就任し、身が引き締まる思いだ。任期は来年の8月までの1年となるが、その間にも新たな課題が生起する可能性があると思うので、それぞれにしっかりと対応していきたい。
いかなる状況下も安全・安心・高品質な小麦粉を安定的に
■製粉業界の現状と課題は?
取組むべき直近の課題としては大きく4つある。1つは食料安全保障への対応である。先の通常国会で食料・農業・農村基本法が四半世紀ぶりに改正され、その中の基本理念に食料安全保障の確保が明確に位置づけられた。それに合わせて各方面の制度の整備も行われており、これを受け今年度中には新たな基本計画が策定される見込みとなっている。その具体的な施策の実現に向け、今後様々な取組みが加速されていくと予想される。製粉業界としても適時適切に対応していきたい。
2つ目は国内産小麦の振興である。食料安全保障の確保の観点から、新たな基本計画の中では国内産小麦の意欲的な生産努力目標が設定され、生産拡大の取組みが推進されていくだろう。これまで以上に生産者サイドの皆様との連携を強化して需要の確保と拡大を図ると同時に、需要に応じた生産、安全で高品質な小麦粉の安定供給の実現に向けて一緒に取組んでいく必要があると考えている。
3つ目は輸入小麦を安定的に確保していくことである。気候変動や地政学的なリスクなどにより、国際的な穀物の需給や相場、物流に様々な影響が出てきており、先行きが非常に不透明となっている。そのような状況だからこそ、国内外の関係機関との協力を密にして、まずは安定的な制度運用のもとで良品質な小麦を安定的に確保していくことが重要になる。
4つ目は小麦粉の需要拡大である。国内の小麦粉需要については、新型コロナウイルスの影響で大幅に落ち込んだ局面からだいぶ回復の兆しが見えてきている状況となっている。この機会を逃さずに消費者や実需者のニーズ、また生活様式の変化や多様化を的確に捉えて小麦粉需要の確保と拡大にどう繋げていくかがポイントになる。
この他にも多くの課題があるが、いかなる状況下でも安全で安心、高品質な小麦粉を安定的にお届けすることが製粉業界の使命だ。これをしっかりと実現していけるよう、会員各社の皆様と一致協力し、会長として力を注いでいきたい。
二次加工メーカーや生産者との連携が重要
■国産小麦の需要拡大に向けた取組みを。
国内産志向が高まり、国内産小麦粉を使いたいという要望が増えてきている。製粉協会製粉研究所では、原料小麦の試験、テストミルを使った小麦粉の試験、あるいは2次加工製品である製パン・製麺に対しての適性試験などを行っているが、近年の国内産小麦は新品種の開発をはじめ生産技術の向上も図られ、品質改善には目覚ましいものがある。実需者、消費者の方々のニーズを的確に捉えて、生産者の皆様と連携しながらそれらに対応できる製品を提供していかなければならない。
一方、品質にばらつきがあること、供給量の変動が大きいことは否めない事実であり、全体的な品質の底上げと高いレベルでの品質の安定化、供給量の安定化について、生産者の皆様と丁寧に話し合っていく必要がある。我々製粉メーカーは二次加工メーカーに向け高品質で一定品質の小麦粉を安定的に供給していく責任がある。せっかくニーズを吸い上げてもその体制が整わないと国内産小麦の需要拡大には繋がらない。我々製粉メーカーとその先の二次加工メーカーや、生産者と連携していくことが重要だと考えている。
社では複数の穀物を扱い多様な製品を提供
■貴社、昭和産業は再来年、創業90周年を迎えるが。
当社は2026年2月に創業90周年を迎える。90周年の到達イメージとして、ありたい姿の長期ビジョン『SHOWA Next Stage for 2025』を2017年に策定し、現在、最終ステージとなる「中期経営計画23-25」の中で、基盤事業の強化と事業領域の拡大、環境負荷の低減、プラットフォームの再構築、ステークホルダーエンゲージメントの強化という5つの基本戦略を展開している。
日本の食品メーカーの中では唯一小麦、大豆、菜種、トウモロコシという複数の穀物を扱っており、これを原料に小麦粉、食用油、デンプン糖化製品と多様な製品を提供している。国内でも非常に稀有な存在であり、穀物の取扱量、顧客数においてもトップクラスだと自負している。この最大の特徴をきちんと武器として磨き上げていく必要がある。
昨年4月、創業以来の大幅な組織変革を行った。従来は小麦粉を販売する人、油を販売する人のように、プロダクトアウト型営業組織だったが、これをお客様に対してベストパフォーマンスを発揮するねらいで顧客ごとの組織に変更した。例えば、ある製パンメーカーに対して小麦粉、油、でんぷん糖類とそれぞれ少なくとも3人の営業担当者がいたところを、1人の担当者が全てを担当し、複合的に新たな提案ができる体制に変更した。
また、将来への布石という意味では、高付加価値化を目指した新規領域の拡大、新規事業にも取組んでいる。8月に発表したのが大豆たん白の新商品ブランド「SOIA SOIYA(ソイア ソイヤ)」。第一弾は大豆たん白を帯状のシートに成型した商品で、幅広い加工適性があり、テレビ番組でも取り上げられて引き合いが非常に増えている。
また10月には、東北大学のスタートアップ企業、ファイトケミカルプロダクツ㈱と資本提携した。同社はイオン交換樹脂を用いて高純度の有効成分を複数生成できる反応分離技術を持つ企業で、2020年から米油の製造過程で発生する副産物からスーパービタミンEやパラフィン、植物ステロールなどを製造販売している。当社グループ会社のボーソー油脂㈱から産生する副産物と同社の技術を融合させ新しい価値の創造を目指す。2025年以降に新工場を建設しスケールアップする計画で、高付加価値分野への事業進出を具体化する。