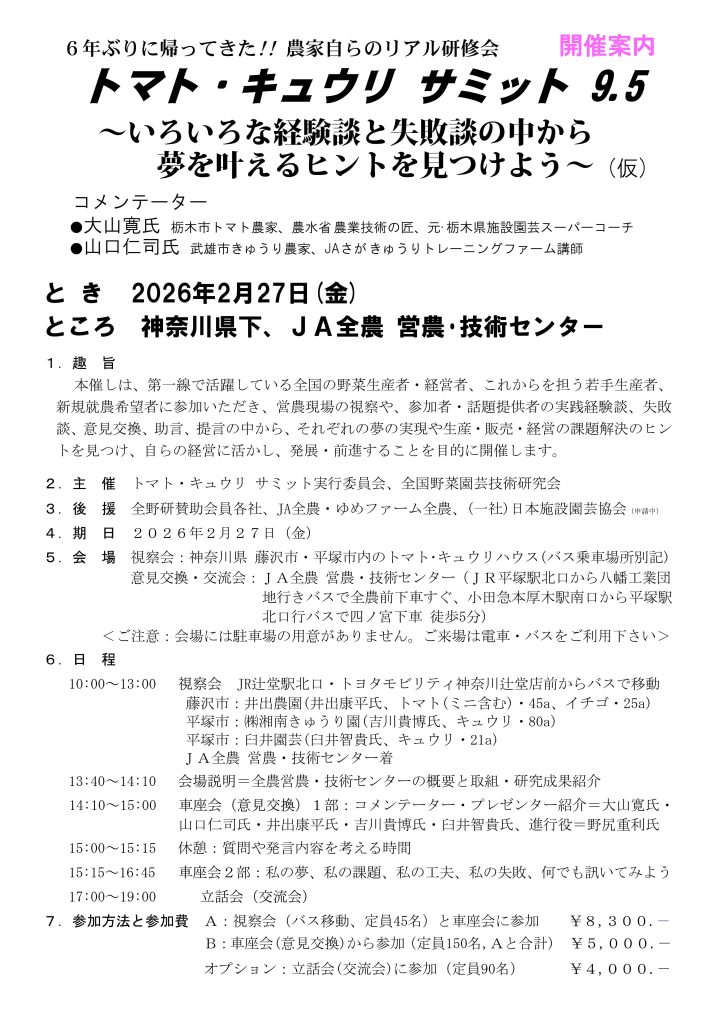〈本号の主な内容〉
■このひと
日本生協連のこれから
日本生活協同組合連合会 代表理事会長 新井ちとせ 氏
■令和7年度JA経営ビジョンセミナー 第1セッション
JA全中が開催
「協同組合の原点とJAの組織・事業のミライ投資/協同組合による地域社会づくり」テーマに
福祉クラブ生協(神奈川県横浜市)に学ぶ
■かお
農林中央金庫 監事に就任した 三浦綾子 氏
 このひと
このひと
日本生協連のこれから
日本生活協同組合連合会
代表理事会長
新井ちとせ 氏
日本生協連は6月13日、通常総会・理事会において新役員体制を決定。新会長に新井ちとせ氏(副会長)が就任した。新井新会長に抱負や生協の事業・活動をめぐる情勢、これからの課題について聞いた。
一組合員からスタート 暮らしと地域に密着を体感
■会長に就任しての抱負から。
私は生協の職員ではなく、一組合員として地域の活動からスタートした。他の組合員と、ふだん感じている疑問や知りたいこと、やりたいことを話し合いながら、商品だけでなく環境や福祉、平和など幅広いテーマを勉強させてもらい、企画・運営に達成感ややりがいを得た。
職員と一緒に仲間づくりの活動に取組み、組合員同士の集まりでパンの食べ比べや牛乳の飲み比べなどもやる中で、職員の大変さも分かり、活動と事業を同時に進めることの価値も知った。また、被災地支援などを通じ、生協が自分たちの暮らしと地域に密着していることを体感した。
これらの活動を通し、組合員と職員と共に生協が元気になるために力を合わせてきたという経緯がある。その意味で、現場感覚を忘れず、今まで通り、いつも通りの感覚でやらせていただきたいと思う。持ち前のフットワークの軽さを生かし、たくさん現場を見て、そこで聞いた声をきちんと事業や活動に反映できたらいいと考えている。
立ち位置変わっても 話し合い重ねるのは同じ
■2015年、コープみらい理事長に。
コープみらいは2013年3月、とうきょう・ちば・さいたまの3生協が合併してできたが、それまでの過程でずいぶん議論も行った。その時、「一つになって未来を見よう」という考え方を中心に置けたのが良かったと思う。
私が理事長に就いたのは、経営が安定軌道に乗っていたこと、生協の主体者は組合員であり地域に寄り添うためには組合員の声を反映したい、そのために真ん中に組合員を置きたいという常勤職員の強い意思があったからだと考えている。
その時、立ち位置は変わっても、一人ひとりが考え、みんなで話し合い、認め合う場を作りつつ、プロセスを踏んでゴールを目指すというスタンスは変わらないのではないかと感じた。私一人の力は取るに足りなくても、事業については専務理事以下、きちんと役割を担ってくれるメンバーがいる。自分は渉外や広報、自治体との連携などに努める、それによって、地域で必要とされる生協に向けてみんなで協力し合うというのは変わらないと思った。
大事にしてきた産直 生産者・産地との連携、密に
■生協から見た農業の現状は。
まず気候変動、地球温暖化の問題がある。現在のコメをめぐる諸課題についても地球環境の変化によって起きていると考えている。
もう一つは担い手問題。生協は、中でも組合員は、特に産地、生産者とつながる産直を大事にしている。
コロナ禍でなかなか交流ができない時期があったが、今の危機においても、もう少し生産者や産地と、組合員や現場の職員が密に関わって現状を知り、解決の方法を話し合える場ができるといい。誰もが手頃な価格でおいしくて安全なコメを食べたいけれども、どうしたらみんなが幸せになるかということも一緒に考えられる場が、まずは作れたらいいと感じている。
ビジョン踏まえ 全国の生協がつながり合う
■日本生協連が抱える課題は。
全国の生協それぞれがさまざまな事業を展開し、地域によって過疎化などの問題を抱えつつ、懸命に自分たちにできることを考えて取組んでいただいている。
その中で多くの好事例が出てきているが、他地域につなげきれていない。私たちは「つながる力で未来をつくる」という2030年ビジョンを掲げているので、全国の生協がもっとつながり合い、教え合い、学び合っていくこと、さらに生協だけでなく、(一社)日本協同組合連携機構(JCA)をはじめとして全国の協同組合が手をつなぎ、各地域の自治体などとのつながりもきちんと広げ、良い相乗効果がもたらされるようになるのが望ましいと考える。
協同組合間連携 点を線にし、相乗効果を
■協同組合間連携について。
協同組合組織にはそれぞれの強みがあるが、互いの組織をどれだけ知っているのか。もっと知ったら、もっと一緒にできることがいろいろあるはずだ。例えば、子育て支援や貧困問題に対する取組みも、それぞれ点では行われているものの、なかなか線で結ばれていないと感じている。
もっと線で結ばれたら、社会に対してのアピール力を高め、協同組合の価値を上げることにつながり、何よりも組合員と職員が元気になるだろう。組織に自信や誇りが持てるようなつながりができれば、現場の職員の働きがい、やりがいといった相乗効果を生むのではないか。
貧困や格差に抗し 誰一人取り残さない社会へ
■協同組合の良さとは。
私はコープ商品の共同購入から生協に入ったが、入ってみたらいろいろことが学べる大学のようで、環境から福祉、平和、ユニセフ、消費者問題などこれほど多くの課題を学ばせてくれる。そのなかで、ニュースを見る目線も変わり、正しい情報を自ら選んで受け取り、自分で考える姿勢を学べたことは貴重な経験だ。
課題に対し一人ひとりが考え、みんなで議論を重ね、自分たちで落としどころを見つけるからこそ、その課題を自分事にできる。こうした考え方は協同組合の大事な部分だと思う。
人と人とのつながりの希薄さが、今の貧困や格差、差別を生んでいると感じている。協同組合はたすけあいの組織なので、誰一人取り残さないSDGsの社会を実現するために、つながりの大切さを噛みしめる取組みを実現したいと考えている。
約3080万人の生協の組合員も高齢化が進み、一人暮らしの高齢者も増加している。若者だけでなく高齢者の貧困も大きな問題になる中で、職員や組合員を通じて現場の声にしっかり耳を傾けていきたい。