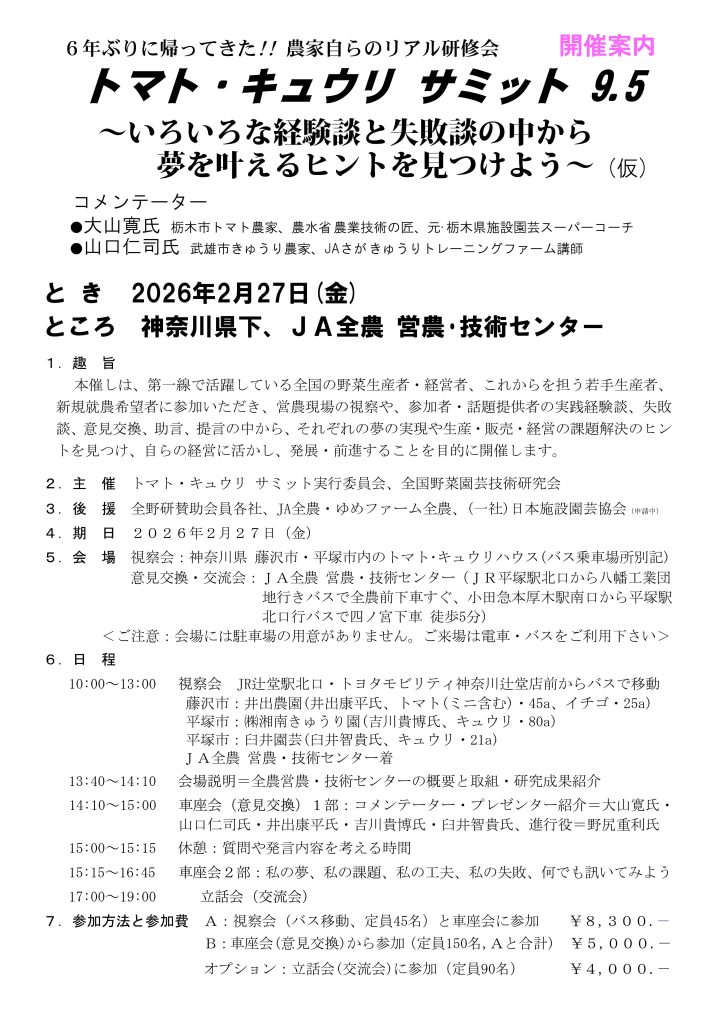参議院選挙で自民党は大敗、石破首相の進退問題が浮かび上がったところに、日米関税交渉が8月1日の期限を前に急転、合意した。日米交渉合意を受けて石破首相の退陣は不可避になったとの報道が大半であるが、9月の臨時国会で結局は比較第一党の自民党総裁が首相に選出されると見る向きが強い。いずれにしても衆院に続いての参議院での与野党逆転。また相互関税が当初の25%から15%に引き下げられたとはいえ大きな影響を被ることは間違いなく、さらに交渉の切り札となった5500億ドルにおよぶ対米投資という中身不明の内容解明も含めて、難しい政局が続くことになりそうだ。
農業問題に絞って見れば、関税ゼロのミニマムアクセス米の枠内でアメリカからの調達割合を増やすことで合意した。輸入総量は増えないということで、国内への影響は少ないとはいうが、果たして増加分が非主食用という理解でアメリカと合致しているのか、また無差別原則に抵触しないよう、アメリカ外の国の理解を得られるのかがポイントになってこよう。そして何よりも2027年度から抜本的転換をはかることにしている水田政策について十分な協議がおこなわれるかが問題で、難しい政局が続くことは免れないとはいえ、農政の停滞は許されない農業情勢にあることは言うまでもない。
こうした中、フード・マイレージ資料室が主催する「食と農の未来フォーラム」が開かれ、所用が入り翌日送られてきた動画を見た。講師は福島県喜多方市山都町にある本木・早稲谷堰(もとき・わせだにせき)と里山を守る会の大友治さんで、テーマは「米は田んぼだけで作られるのではない、稲作が生産するのは米だけではない」で、江戸時代の中期、1736年に着工され12年間の難工事を経て完成された本木上堰の現状と課題についてお話しされたものである。本木上堰は早稲谷川から取水し本木大谷地まで全長約6kmの山腹を走る水路で、高度差70m、平均勾配50分の1の緩傾斜に、最小15cm、最大で200cmの幅の水路を通すことによって約14haの水田が開かれたものである。スライドの、ブナ林の間を流れる早稲谷川や棚田の風景は、息をのむほどに美しい。まさに森と里が一体となり、里山で300年近く積み重ねられてきた生業が創り出してきたものだ。
その里山は、農家数の激減と高齢化によって後継者不足はきわめて深刻であり、本木上堰も存亡の危機にさらされている。これにともない2000年から堰浚いのボランティアの募集を始め、現在では40人前後の参加者を得てかろうじて維持されているという。
こうした現状は中山間地域に共通するものであるが、自民党農政は大規模化、スマート農業による生産性の向上をもっぱらとしており、水田面積14haの当地をはじめとして、中山間地域は切り捨てられようとしてきた。意見交換の中で、上流での水の管理があってこそ、平場でも水が確保され稲作も可能になるとの大事な話も出された。
水田政策の見直しは、米の増産を可能にする持続的な稲作にしていくところにポイントはあるが、まずは何よりも上流も含めた現場の実情をしっかり理解しておくことが前提となる。(7月25日現在)
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2025年8月5日号掲載