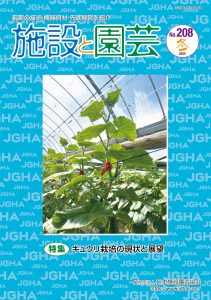〈本号の主な内容〉
■アングル
JA全農事業ビジョン2030と令和7年度事業がめざすもの
JA全農 代表理事専務 安田忠孝 氏
■持続可能な農業と食の提供のために 〝なくてはならない全農〟であり続ける
〝つくる〟力、〝とどける〟力、〝つながる〟力で
JA全農事業ビジョン2030
令和7年度事業計画 のポイント/経営計画
■令和7年産米をめぐるJA全農の対応
JA全農 米穀部 藤井暁 部長
■TAC・出向く活動パワーアップ大会2024
TAC部門 全農会長賞を受賞した
JAフルーツ山梨 山梨ブロック指導課 竹川要さん
 アングル
アングル
JA全農事業ビジョン2030と令和7年度事業がめざすもの
JA全農
代表理事専務
安田忠孝 氏
JA全農は3月25日の臨時総代会で、従来の中期計画に代わる長期的な目標として策定した「JA全農事業ビジョン2030」と、その初年度となる令和7年度事業計画を決定した。そのポイントを、4~6年度の前中期計画の成果とともに安田忠孝専務に語ってもらった。
スマート農業普及などに成果、社会的課題へ対応
■まず、前中期計画の振り返りから。
令和4~6年度の中期計画を策定する段階で、既に2030年を見据えて考えていました。ちょうどコロナ禍が収束しつつある時期に当たります。農業の生産基盤が脆弱化し、食をめぐる消費者の生活様式が変化する中で、長期的には日本の人口が減少する一方、世界の人口は増え続けるという環境認識がありました。
ところが、中期計画1年目の令和4年にロシアのウクライナ侵攻が起き、策定時点で考えていたこととは全く異なる事業対応を迫られました。その結果、少なくとも、世の中想定通りに動くものではない、という覚悟ができました。その意味では貴重な経験になりましたし、全農としては、そうした想定外の状況下でも着実にやるべきことをやってこられたと考えています。
前中期計画では、①生産振興、②食農バリューチェーンの構築、③海外事業展開、④地域共生・地域活性化、⑤環境問題など社会的課題への対応、⑥JAグループ・全農グループの最適な事業体制の構築の6つの全体戦略を掲げて取組んできました。
生産振興については、生産基盤が縮小していく中、少ない担い手で効率的な生産を進めるという観点から、スマート農業に関わる技術の開発・普及に力を入れ、コメの「ZR1」など新品種開発も実現しました。国内資源の有効活用に関しても、飼料用子実とうもろこしの栽培実証や、再生リンを活用した肥料生産といった成果を上げることができました。労働力支援も全国的な取組みに拡大し、広く多くの方に農業に携わってもらう仕組みになってきました。
食農バリューチェーンの構築では、集出荷施設や貯蔵・保管施設など物流のインフラ整備、トラック輸送から鉄道や船舶を活用するモーダルシフトなどに取組みました。国産農畜産物を活用した商品開発も「ニッポンエール」など全農ブランドの取組みで定着してきており、一定のブランド価値を確立できたと考えています。
海外事業については、突然生起した地政学リスクに対応して、肥料・飼料原料の安定調達の面で一定の役割を果たせたと思いますし、輸出に関してもこの3年、着実に量を伸ばすなど成果を生んでいます。
地域共生・地域活性化では、スマートアグリコミュニティの実証を始め、エネルギー事業ではホームエネルギーの導入に向けた事業形態の転換に着手しました。店舗事業ではAコープ会社の統合を進めました。
環境問題など社会的課題については、環境調和型農業に関する技術・資材を体系化した「グリーンメニュー」の作成、畜産酪農事業のサステナビリティ課題に対する対応方針・目標・取組み事例を情報開示する「畜産酪農サステナビリティアクション」の発行などで我々の姿勢を示すことができたと思います。
農業生産の持続性確保へ、温暖化問題にアクション
■対米関税の問題など先行きに不透明感もある中、全農グループ事業を取り巻く情勢認識については。
先が読めない面は多々あります。ただ、この3年間の経験もあって、思ってもみないことが起こり得るということを念頭に置きながら事業を進める覚悟はできてきました。そのこともあって、今回は従来の3カ年の中期計画をいったん横に置き、長期的なビジョンを策定することにしました。今のような激しく不透明な変化の中では、そのつど柔軟に対応するとともに、長期的に我々のめざす目標を明確に出していかなければなりません。
一方で、変わらない課題としては、国内の人口減少があり地球温暖化があります。近年の自然災害の激甚化・頻発化はおそらく温暖化に起因しているでしょうし、農作物にも高温障害が出てきています。農業生産の持続性の面からも、温暖化に対して何らかのアクションは必要だと考えています。
食料安全保障確立へ、全農の役割あらためて自覚
■国の農政が食料安全保障を打ち出した中、あらためて全農が果たすべき役割は。
食料・農業・農村基本法が昨年改正され、食料安全保障が法律の中にしっかり位置付けられたことは、農業に対するポジティブなメッセージとして受け止めています。国民の中にも、農業への関心、重要性への理解が広がってきた感はあるのですが、コメや野菜の高騰が社会問題化する中、国際情勢における食料安全保障という問題以前に、国内で当たり前だと思われていた農畜産物の安定供給に対する不安のようなものが広がってきたようにも感じています。これはこれまでとは違う事業環境です。そもそも生産者の努力だけでは今ある食料生産が当たり前に続けられず、消費者や流通・加工業者も一緒に取組まないと続かないという時代認識に変わってきているのではないでしょうか。我々全農役職員としても、全体の中の一事業者ではありながら非常に重要な役割を担っているということを、あらためて自覚する機会になったのではないかと思います。
「めざす姿」は不変、財務目標を明示
■「JA全農事業ビジョン2030」のポイントを。
ビジョン策定にあたり、まず「持続可能な農業と食の提供のために〝なくてはならない全農〟であり続ける」という従来からの「全農グループのめざす姿」は変える必要がないと考えました。「めざす姿の実現に向けた全体戦略」に掲げた6つの領域も、大枠として前中期計画から引き継いで、これまで以上に一つ一つ深掘りしていきたいと考えています。
また、財務目標を新たに掲げ、「取扱高6兆円および会員への80億円以上の継続的な配当ができる財務体質の実現」としました。これくらいの財務力を持った事業体でなければ、めざす姿は実現できないというメッセージでもあります。
さらに、「全農グループが培ってきた力」を、「つくる力」「とどける力」「つながる力」に大別して示しました。ビジョンに掲げた目標は、まったく新しいことをやらなければ達成できないわけではなく、我々が培ってきた力を最大限に発揮すれば十分達成できると考えるからです。そのうえで、さらに2030年の先に向けて、どんな新しいものをつくっていけるのかを楽しみにしながら取組んでいきたいと考えています。
持てる力を結集しJA・産地を全力サポート
■全体戦略に掲げた各領域で、7年度に向けて重要なポイントを。まず「生産振興」から。
2030年という時点を想定した時、その時点における自然環境や担い手の状況にきちんと対応できる生産技術や品種がなければ、必要な生産量を維持することは難しくなります。さらに生産物の販売の仕方まで提案する、いわば産地を丸ごとつくっていく機能が求められています。
我々は生産から原料調達、技術・品種の開発・普及、販売まで一つ一つを専門的に追求してきましたが、持っている力を結集したら何ができるかという観点で再構成をしたい。例えば、「ゆめファーム」で施設園芸の人材育成から生産開始へと段階を進め、乳肉複合農場で更地の整備から畜産の生産農場づくりまで手掛けることで、個別の取組みではできないことを身をもって体験します。そのような生産の現場に近い仕事を通じて我々の機能を高めていきます。
■「食農バリューチェーンの構築」に向けた取組みでは?
単に付加価値を訴求するだけではなく、食の持続可能性の観点が求められます。そのためのインフラ整備を、食に携わっている他企業等とも連携しながら進めることが急務だと思います。流通の各段階で必要となる施設への投資、実需者ニーズを満たす商品開発と販売提案にも取組みます。
■「海外事業展開」では?
今回の〝トランプショック〟もそうですが、リスク管理はこれまで以上に大事になってきます。特に、我々の飼料穀物の事業はアメリカに集中していますが、ビジネスの拠点まですべてアメリカに置くリスクは大きい。これら海外で事業展開する子会社を中立国に新設した会社の傘下にする再編を実施しました。こうしたサプライチェーンの強靭化による海外資源の安定調達、輸出戦略の構築に引き続き注力します。
■「地域・くらしの維持と活性化」については?
地方の衰退は急速に進み、地域の暮らしのインフラが維持できなくなってきています。その対策の一環として、JAグループが保有する地域インフラやサービスをICTでつなぐ「スマートアグリコミュニティ」の構築にピッチを上げて取組み、地域サービスの拡大・充実をはかっていきます。我々にとって地域は生産基盤そのもの。そこでの暮らしをいかに成り立たせるかは、地域に立脚したJAの重要な役割の一つであり、取組むべき必須の課題です。そのための持続可能な事業体制の点検も、並行して行っていく必要があります。
■「環境および社会的課題への対応」に関しては?
脱炭素化や耕畜連携、地域事情を踏まえた段階的な環境に配慮した農業生産の実践を進めます。「適正な価格形成の実現」は前中期計画では「食農バリューチェーンの構築」の中に位置付けていましたが、広く消費者も関わる食の持続可能性を高めるための問題としてより重視し、社会的課題に組み入れました。
また、(一社)AgVenture Lab(あぐラボ)で支援しているスタートアップ企業の事業創出のアプローチは、ストレートに社会的課題と結び付いています。事業展開に応じて企業の形をどんどん変えていくダイナミズムにも学ぶところがあります。そうしたスタートアップ企業に全農職員を出向させる制度を設けましたが、戻ってきた職員の報告を聞くと、経験がいい刺激になっているようで、今後の事業展開にも生きてくるのではないかと感じています。
■「JA・全農グループにおける最適な事業体制の構築」では?
JA段階での人手不足に対するサポートが重要課題であり、ここがDX推進の眼目でもあります。最も必要なのに人手が足りない営農指導については、「担い手営農サポートシステム」の普及に努めます。
集出荷業務のデジタル化も面的な普及を行い、効率化を進めます。
また、生産資材の「受発注センターシステム」の導入にも力を入れます。
この3点セットは必要不可欠であり、強力に進めたいと考えています。
全農グループの職員については、少子化やジェンダー平等、働き方改革の流れに合わせて、組織の価値向上と個人の成長意欲・働き甲斐が一致するように人事制度を見直していきます。併せて、グループ各社を含めてヒト・モノ・カネを全体としてうまく活用する仕組みの構築も進めたいと考えています。
■最後に、災害等の危機管理への対応について
気候変動により農業現場の自然災害リスクが高まっていることから、災害対策積立金の目標額を増額します。併せて、災害発生時に全農グループが保有する備蓄資材を被災地に融通し、より迅速な復旧・復興につなげる仕組みづくりや動き方の整理などを、あらためて行いたいと考えています。