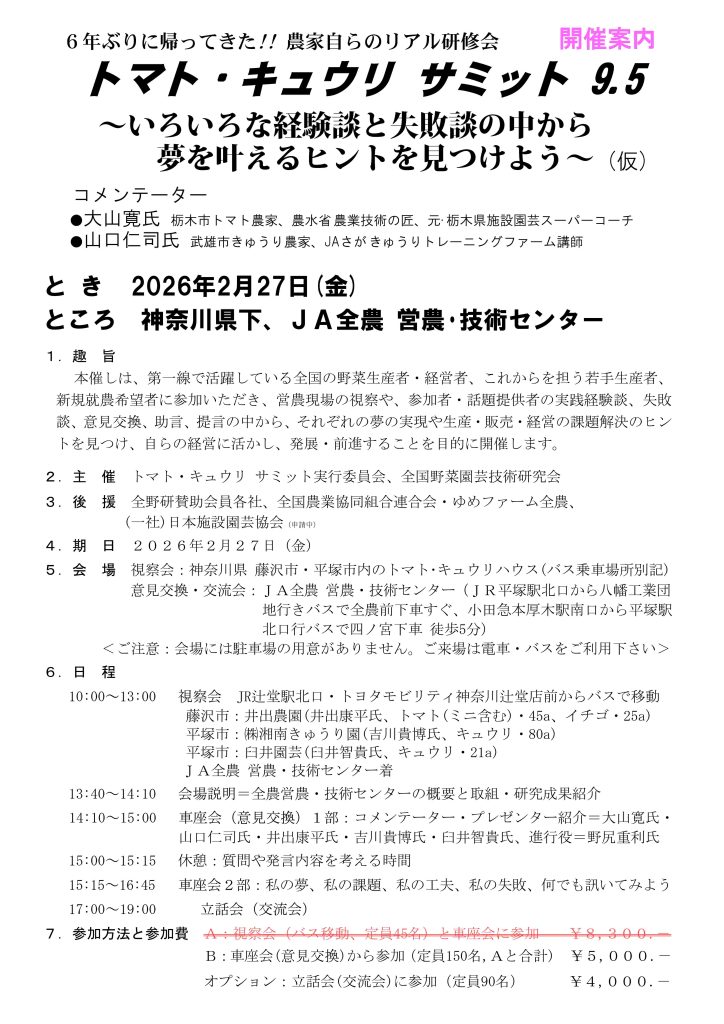コロナ・ショックが
基本計画の具体化に問うもの
東京大学 大学院
農学生命科学研究科
教授
鈴木宣弘 氏
3月決定した新たな食料・農業・農村基本計画にも急遽記述が加えられた新型コロナウイルス感染症問題。人々の健康はもとより経済・社会活動が地球規模で極めて深刻な打撃を受け、食料安全保障上の問題も懸念される中、日本の食料・農業・農村に突きつけられた課題や〝コロナ後〟を見すえた今後などについて、鈴木宣弘東大大学院教授に聞いた。
過度の貿易自由化に歯止めを
■新型コロナウイルスの世界的感染拡大にともなう食料・農業・農村への影響・課題は?
新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延(コロナ・ショック)を受けて、輸出規制に耐えられる食料自給率の向上の重要性がクローズアップされ、具体的かつ着実な食料自給率向上の道筋が示される必要性が高まった。不可欠な生産要素として、飼料、種だけでなく、労働力の海外依存の問題も認識された。
WTOが4月23日公表した「新型コロナウイルス関連の輸出禁止・制限措置に関する報告書」によれば、小麦の大輸出国ロシア、ウクライナ、コメの大輸出国ベトナム、インドなどをはじめ、世界17の国・地域が輸出規制に動いた。
食料の輸出規制は簡単に起こり得る。そのことが今回も明白になった。FAO・WHO・WTOの各事務局長は4月1日、共同で輸出規制の抑制を要請したが、食料確保は国家の最も基本的な責務。最低限の食料自給率を維持するための措置は当然のことであり、他国から非難されるべきものではないはずだ。事実、GATT協定にも輸出規制の抑制条項はあるが歯止めになっていない。
過度の貿易自由化が、多数の輸入依存国と少数の生産国という構造を生み、それがショックに対して価格が上昇しやすい構造を生み、不安心理から輸出規制も起こりやすくなり、自給率が下がってしまった輸入国は輸出規制に耐えられなくなっている。
今行うべきは、過度の貿易自由化に歯止めをかけ、各国が自給率向上政策を強化することである。
ところが、FAO・WHO・WTOの共同声明は、輸出規制の抑制と同時に、一層の食料貿易自由化も求めている。輸出規制のそもそもの原因は貿易自由化なのに、解決策は貿易自由化だとは論理破綻も甚だしい。一層、食料の海外依存を強めよというのか。これはコロナ・ショックに乗じた〝火事場泥棒〟的ショック・ドクトリン(災禍に便乗した規制緩和の加速)であり看過できない。
このような、一部の利益のために農民・市民・国民が食いものにされる経済社会構造から脱却しなくてはならない。食料の自由貿易は見直し、食料自給率低下に本当に歯止めをかけないといけない瀬戸際に来ていることを、もう一度思い知らされているのが今である。
TPP11、日欧EPA、日米貿易協定と畳みかける貿易自由化が、危機に弱い社会経済構造を作り出した元凶であると反省し、特に、米国からの一層の要求を受け入れていく日米交渉の第2弾はストップすべきである。
これを機に貿易自由化が加速し、多くの国の食料自給率がさらに低下するようなことは、あってはならない。
「食料国産率」と「食料自給率」
■新たな食料・農業・農村基本計画をどう評価されるか。
今回の食料・農業・農村基本計画では、私が企画部会長としてとりまとめた2010年計画で重視し、2015年計画で消えた「地域を支える多様な農業経営体の重要性」が再確認された。
「望ましい農業構造の姿」の中に、2015年計画で位置づけられたのは「担い手」だけだったが、今回の2020年計画では「その他の多様な経営体」が加わり一体として捉えられた。あくまで「担い手」を中心としつつも、規模の大小を問わず「半農半X」なども含む多様な農業経営体を、地域を支える重要な経営体として一体的に捉える姿勢が復活した。
前回の2015年計画は、狭い意味での経済効率の追求に傾斜した、大規模・企業化路線の推進が全体を覆うものとなっていた。今回の2020年計画は、前々回の2010年計画のよかった点を復活させ、長期的・総合的視点から、多様な農業経営の重要性をしっかりと位置づけることなどによって、バランスがやや回復した感がある。
しかし前述のように、コロナ・ショックに乗じてさらなる貿易自由化や規制緩和が推し進められ、疲弊しつつある地域農業に追い打ちをかけるようなことになれば、新基本計画の方向性は踏みにじられる。こうした流れは食い止めねばならない。
新基本計画では、目標水準を53%とする、飼料自給率を反映しない新たな食料自給率目標が設定され、名称は「食料国産率」に落ち着いた。
今後の食料自給率の設定は、カロリーベースと生産額ベースの二本立てに加え、それぞれがさらに二本立てになる。今回導入される「食料国産率」と、飼料の国産度合いを反映する従来からの総合食料自給率の二本だ。
カロリーベース自給率について定義を確認すると、食料国産率は、〈国産供給熱量(=国産の純食料×単位カロリー)÷供給熱量(=純食料×単位カロリー)〉で、従来から用いられている通常の総合食料自給率は、簡潔に示せば〈食料国産率×飼料自給率〉である。純食料とは消費に回された食料のうち可食部分をいう。
この2つを併記することは、飼料の海外依存の影響がどれだけ大きいかを認識させることになる。農水省の示している平成30年度の数字を見ると、〈全体〉食料国産率46%→総合食料自給率37%、〈畜産物〉62%→15%、〈牛乳・乳製品〉59%→25%、〈牛肉〉43%→11%、〈豚肉〉48%→6%、〈鶏卵〉96%→12%となる。
最も差の大きい鶏卵で見るとわかりやすい。「日本の卵は96%の国産率を誇りよく頑張っている」と言えるが、「海外からの輸入飼料がストップしたらたいへんなことになる」「もっと飼料を国内で供給できる体制を真剣に整備しないといけない」と実感できる。
コロナ・ショックは、カロリーベースと生産額ベースの自給率の重要性の議論にも〝決着〟をつけたように私には思われる。
生産額ベースの自給率が比較的高いことは、日本農業が価格・付加価値の高い品目の生産に努力している経営努力の指標として意味がある。しかし、「輸入がストップするような不測の事態に、国民に必要なカロリーをどれだけ国産で確保できるか」が自給率を考えるうえでの最重要の視点と考えると、重視されるべきはカロリーベースの自給率である。海外では、より計算が簡便な、畜産の飼料も含めた穀物自給率を、カロリーベース自給率に代わる指標として活用している国も多い。
今回のコロナ・ショックでも、穀物の大輸出国が簡単に輸出制限に出たことは、いくつもの指標を示すことに意味はあるが最終的には、カロリーベースないし穀物自給率が危機に備えた最重要指標であることを再認識させたと思われる。
質の安全保障考えると「国産こそ安い」
■〝コロナ後〟を見すえた今後のあり方などについて。
新基本計画で出された食料国産率の議論においては、生産要素をどこまで考慮した自給率を考えるかという問題もクローズアップされた。
今回のコロナ・ショックでは、日本農業が海外からの研修生に支えられている現実、その方々の来日がストップすることが野菜などを中心に農業生産を大きく減少させる危険が炙り出された。外国からの労働力に大きく依存する欧米ではさらに深刻である。
野菜の種子の9割が外国の圃場で生産されていることを考慮すると、自給率80%と思っていた野菜も種まで遡ると自給率8%(0・8×0・1)になるという衝撃的現実がある。同様に、農業労働力の海外依存度を考慮した自給率も考える必要があると磯田宏九州大学教授などが指摘している。
海外研修生については、その身分や待遇のあり方を含め多くの課題を投げかけている。一時的な〝出稼ぎ〟的な受入れでなく、教育・医療・その他の社会福祉を含む待遇を充実させ、家族とともに長期に日本に滞在してもらえるような受入れ体制の検討も必要だろう。
新基本計画における飼料の海外依存度の議論と、コロナ・ショックにより露呈した労働力の海外依存の問題が、今後の不測の事態に備えた食料自給率の向上の具体的課題を、さらに浮き彫りにしたと言える。
食の安全保障には、「量」とともに「質」の問題がある。成長ホルモン、除草剤、防カビ剤残留などでリスクのある食料が輸入基準の緩い日本を標的に入ってくる。質の安全保障も危機に瀕している。
米国の食肉加工場において、劣悪な労働環境での低賃金・長時間労働の強要が新型コロナの集団感染につながったことを、内田聖子アジア太平洋資料センター共同代表が報告した。低賃金・長時間労働でコストを不当に切り詰め、衛生面・安全面も含む環境に配慮するコストも不当に切り詰めることで輸出競争力を高めている実態を、コロナ・ショックが露呈させた。
本来、負担すべき労働・環境コストを負担せずに価格を安くした商品は、正当な商品とは認められないのであり、輸入を拒否すべき対象と言える。
安全保障のコストを考えたら「国産こそ安い」と言えるのである。
新基本計画の精神が本当に実際の政策に具体的に結実するか、見極めはこれからである。これまで現場で頑張ってきた農林漁家を非効率な者とみなし、強引に特定企業にビジネスを乗っ取らせることを促進するような法律がどんどんできてしまっている。これをまっとうな方向に引き戻せるのか、〝復活の基本計画〟の真価が問われる。
多様な農業経営共存、持続的繁栄を
■農業生産現場への期待を。
コロナ・ショックを機に、生産者とともに自分たちの食と暮らしを守っていこうという機運が、ネット上の一般からのコメントでも高まってきていることがうかがえる。今こそ、安全・安心な国産の食を支え、国民の命を守る生産から消費までの強固なネットワークを確立する機会にしなくてはならない。
農業者は、自分たちこそが国民の命を守ってきたし、これからも守るとの自覚と誇りと覚悟を持ち、そのことをもっと明確に伝え、消費者との双方向ネットワークを強化してほしい。それを通じて、安くても不安な食料の侵入を排除し、自身の経営と地域の暮らしと国民の命を守る。消費者はそれに応えてほしい。それこそが、強い農林水産業だと言えるだろう。
特に、消費者が単なる消費者でなく、より直接的に生産にも関与するようなネットワークの強化が今こそ求められてきている。世界で最も有機農業が盛んなオーストリアのペンカー教授の「生産者と消費者はCSA(産消提携)では同じ意思決定主体ゆえ、分けて考える必要はない」という言葉には重みがある。
全国各地域で、行政・JAなど協同組合・市民グループ・関連産業などが協力して、住民が一層直接的に地域の食料生産に関与して、生産者と一体的に地域の食を支えるシステムづくりを強化していきたいところである。こうした方向性は、新基本計画でも打ち出されている。
政策的には、なんらかの危機により農業者や中小事業者や労働者が大変な状況に陥ったら、最低限の収入が十分に補填される仕組みが機能して確実に発動されるよう、普段からシステムに組み込んでおくことが重要だろう。国民の命と暮らしを守れる安全弁=セーフティネットのある、危機に強い社会システムの構築が急がれる。
危機になってから慌てても乗り切れない。このことも新基本計画の具体化における課題である。
今回のコロナ・ショックは、世界の人種的偏見もクローズアップさせた。アジアの人々が欧米で不当な扱いを受けるケースが増えたことは残念だが、逆に、アジアの人々の間に助け合い、感謝し合う連帯の感情が強まった側面もある。
この機会を、日本の思考停止的な対米従属姿勢を考え直す機会にし、アジアの人々が、そして、世界の人々が、もっとお互いを尊重し合える関係強化の機会にしたいと思う。対米従属を批判するだけでは先が見えない。それに代わるビジョン、世界の社会経済システムについての将来構想が具体的に示されなくてはならない。
まず、日本、中国、韓国などアジアのすべての国々が一緒になって、TPP型の収奪的協定ではなく、お互いに助け合って共に発展できるような互恵的で柔軟な経済連携ルールをつくることが重要である。農業については、アジアの国々には小規模で分散した水田農業が中心という共通性がある。そうした共通性の下で、多様な農業がきちんと生き残り発展できるようなルールというものを、私たちが具体的に提案しなくてはいけない。
多様な農業経営の共存と地域の持続的繁栄の視点は、こうした国際的視野から考えていく必要があろう。それが、最終的には完全な貿易自由化を目指すFTAやWTOのゴールそのものを変えていく力にもなると考えられる。
〈本号の主な内容〉
■このひと コロナ・ショックが基本計画の具体化に問うもの
東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授
鈴木宣弘 氏
■JAグループ 食料・農業・地域政策の推進に向けた政策提案
JA全中が4日決定
■JA全農 2020年度事業のポイント
〈営業開発事業〉
JA全農 営業開発部 山田尊史 部長
〈耕種総合対策事業〉
JA全農 耕種総合対策部 永島聡 部長
〈耕種資材事業〉
JA全農 耕種資材部 冨田健司 部長