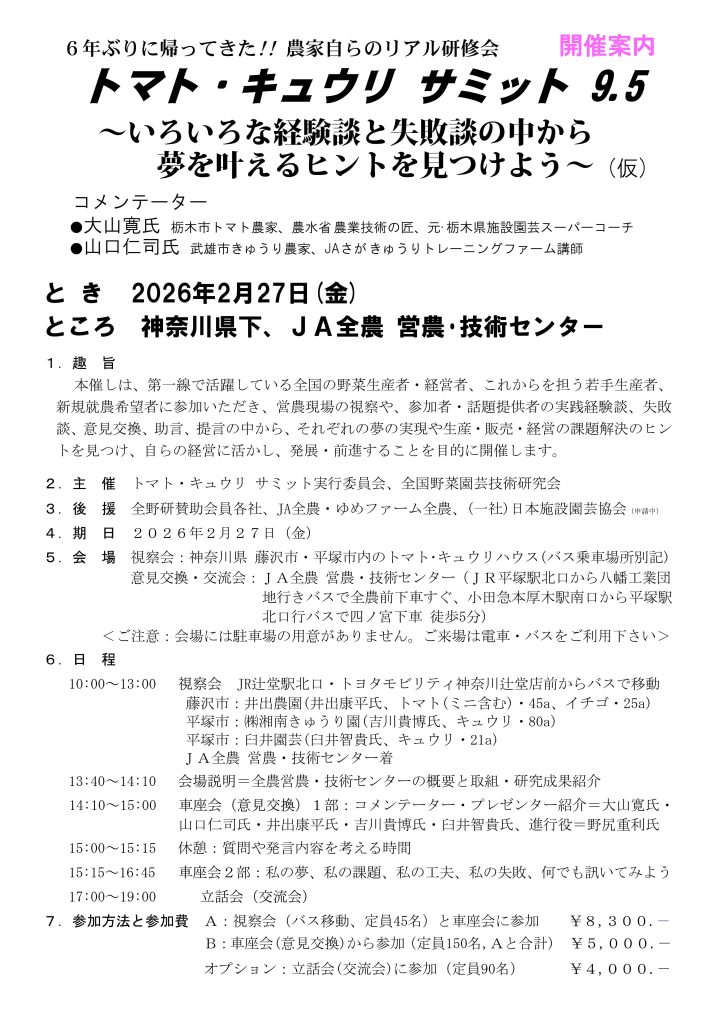〈本号の主な内容〉
■このひと
家の光協会の事業展開
(一社)家の光協会 代表理事会長 伊藤清孝 氏
■JA全農 第49回 通常総代会
令和6年度取扱高5.1兆円、計画比104%
出資配当4%、利用高配当を3年連続実施
新専務に尾本英樹氏、新常務に土屋敦氏
■かお
農林中央金庫 常務執行役員に就任した4氏
・常務執行役員(バンキングユニット) 食農法人営業共同責任者 長谷川智成 氏
・常務執行役員 JA・JF事業共同責任者 篠田崇 氏
・常務執行役員(バリューチェーンユニット) 食農法人営業共同責任者 爲井清文 氏
・常務執行役員 共同投資責任者(Co-CIO) 森順次 氏
■第19回森林組合トップセミナー・森林再生基金事業発表会
農林中金、全森連が開催
 このひと
このひと
家の光協会の事業展開
(一社)家の光協会
代表理事会長
伊藤清孝 氏
家の光協会が6月20日に開催した通常総会後の理事会で、伊藤清孝氏(岩手県中央会代表理事会長)が代表理事会長に就任した。伊藤新会長に家の光協会の事業展開や思い、JA教育文化活動のあり方について聞いた。
改めて「協同」のたいせつさを伝える
■『家の光』創刊100周年を迎えた家の光事業の歩みと思いを。
『家の光』は、令和7年5月号で創刊100周年を迎えました。これもひとえに愛読者のみなさまをはじめ、JAグループならびに関係団体のご支援の賜物であり、深く感謝を申しあげます。
『家の光』は大正14年、「協同の心」を家庭で育むことを目的に産業組合中央会が創刊しました。大正から令和へと発行を重ねる間、農業・農村を取り巻く環境は大きく変化してきていますが、「協同」のたいせつさを伝えるという創刊の使命は変わらないと考えています。
当たり前のことを当たり前にすることはなかなか難しく、できていないこともありますが、会長としてまずは、当たり前のことをしっかり実行することをめざしていきます。
組合員を中心とした教育文化活動に力を
■これまでの家の光事業との関わりは。
水稲農家の長男として生まれたため、物心ついた頃には『家の光』の存在を認識していました。
とくに私の出身であるJAいわて花巻の管内ではこれまでに6回、「家の光文化賞」受賞農協が出ています。その中で私が思い出深いのは、平成24年の受賞です。
当時、私は企画管理部長として教育文化活動の取組みを先導していました。しかし20年に合併すると、地域間で教育文化活動の取組みに温度差があることがはっきりしてきました。
そこで当時の組合長が強調したのは、教育文化活動に力を入れ、組合員を基点に考えること。『家の光』の部数増も重要ですが、やはり要になるのは、教育文化活動をどのように進めていくか。組合長と話し合い、他の農協出身の職員にも〝花巻流〟の教育文化活動の進め方を伝えながら、活動に力を入れていきました。女性部とのつながりも密に進めてきました。
新規事業で組合員・地域住民との接点を構築
■JAグループにおける家の光協会事業の取組み、役割は。
第30回JA全国大会決議で掲げられた5つの取組み戦略のうち、本会はとくに、「くらし・地域活性化戦略」「組織基盤強化戦略(JA仲間づくり戦略)」「経営基盤強化戦略」に関連するさまざまな取組みへの支援や「JAグループ内外に向けた情報発信」にしっかり取組み、大会決議実践に貢献することを、令和7~9年度事業3か年計画の重点方針としています。
くらし・地域活性化関連では、協同活動の最重点として「全世代型食農教育」に取組み、「あぐりスクール」「ちゃぐりんフェスタ」「家の光料理教室」などの開催支援を引き続き行うとともに、7年度からは大人を対象とした食農教育として、「まなVIVA!(まなびば)」の開催支援を開始します。これは例えば、JAの直売所を会場に調理デモなどの本会提供プログラムにJA独自のプログラムを加えて開催するイメージです。
組織基盤強化関連では、令和8年度から、生活文化教室や教育・教養講座の開催に向け動画講座と体験キットを提供する「JAサテライト プラス」を開始。組合員・地域住民との接点を構築する最初の一歩として、ぜひ活用していただきたいと思います。
JAグループ外に向けた情報発信では、Webサイト『あたらしい日日(にちにち)』 を通じた情報発信により、「国消国産」や 「地産地消」、食料安全保障の重要性に関する国民理解の醸成に努めます。
JAグループ内に向けては、組織内広報として、『家の光』『地上』『ちゃぐりん』などでJA事業への理解促進につながる情報発信を行っていきます。これらの取組みを実践するため、令和5~9年度にかけ「中期経営計画」にもとづく事業改革を行っているところです。
家の光協会会長として、どのように取組むべきか。実際に現地へ行き、組合員と話してみないと分からないことがあるでしょう。こちらからの押し付けではなく「あなたはどう思いますか」と投げかけて対話していくことが、相手を知り現状を理解することにつながると考え、対話を重ねていきたいと考えています。
地域間の温度差をなくし事業の平準化を
■JAにおける教育文化活動の重要性は。
協同組合は、組合員が出資し、利用し、運営する、組合員が主役の組織です。しかし、現在のJAは「わがJA」意識が低下した組合員が「顧客化」しているだけでなく、「お客様」として組合員に接する職員もいるなど、協同組合としての内実が問われる状況にあると考えています。
この状況を変えるには、JA役職員が「協同組合運動者」となって、組合員の「わがJA」意識を高め、組織基盤を強固にすること、「協同組合らしいJA」をつくることが重要です。さらには地域間の温度差をなくし、平準化することが求められるでしょう。
例えば、岩手県下の7JAは、小学生を対象にプランターでミニトマトを育てる「わくわく純情プランター」運動を展開しています。各JAでは、コロナ禍をきっかけに組合員との対話や教育文化活動が減少し、コロナが収束しても教育文化活動の取組みが進んでおらず、職員もどのように取組めばいいか分からない状況でした。そこで県下の統一行動として、取組みをスタートしました。小学生はもちろん、保護者に教育文化活動を知ってもらうきっかけにもなっていると感じています。
教育文化活動は、組合員や地域住民と新たに密な関係性を築くもの。その4つの領域のうち、とりわけ「教育・学習活動」はとても重要な活動です。教育文化活動はまだJAによって取組みに濃淡があります。ある程度、取組内容などを平準化していくことで、将来経営が危うくなるJAを減少させることにもつながるのではないでしょうか。
併せて、JA役職員も『家の光』を読んで知識や知見を深め、JAや事業について自分の言葉で組合員に語れる職員になっていただきたいと思います。
組合員を助け、地域に根付く協同組合に
■改めて協同組合の長所は。
一番は、JAは地域に根付いていること。
例えば東日本大震災では、組合員から食べ物や衣服が足りないなど様々な声が届きました。そこで、JAいわて花巻は管内の3つの被災地に向け、物資を運びました。また「白米一升運動」を展開し、白米46tを集め、被災地で炊き出しを実施しました。
このように組合員からのニーズに対し、すぐに対応することは協同組合としての基本中の基本ではないかと感じています。組合員が困った時にJAを頼り、その要望に対し理屈抜きで応える。これが協同組合としての基礎ではないかと思います。