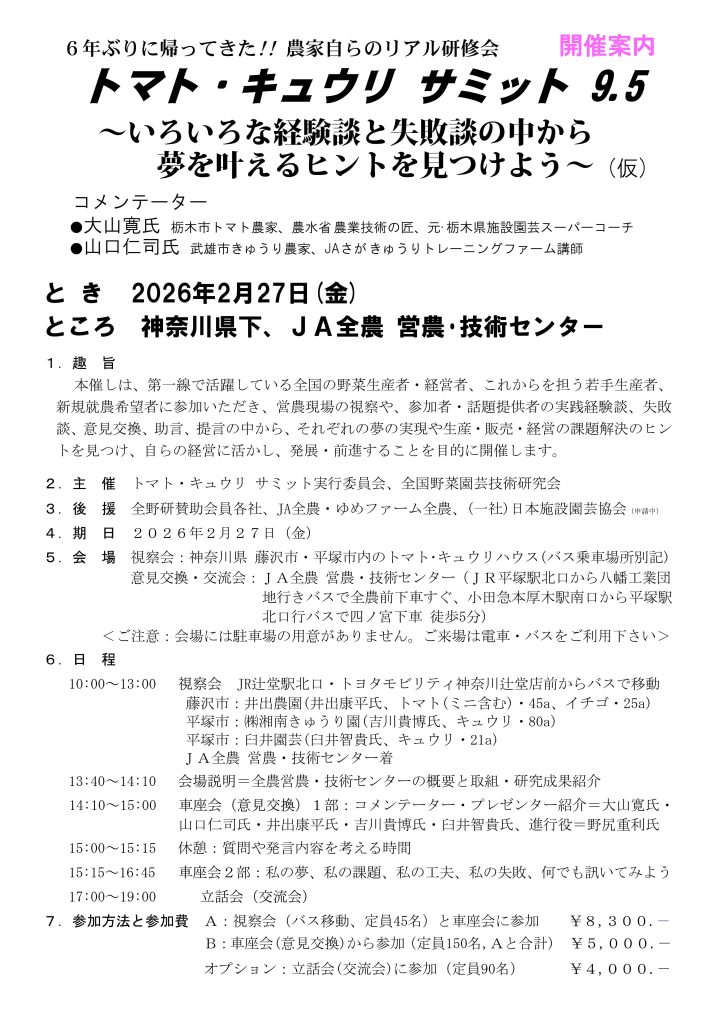福島県飯舘村の田んぼでは、飼料用作物が広く栽培されている。飼料用米や稲のホールクロップサイレージ(WCS)、デントコーン、牧草などだ。WCSや牧草のロールが並ぶ光景に「こんなの昔はなかった」と漏らす高齢の住民もいる。
田園風景を変えたのは福島第1原発事故だ。6年間の全村避難を経て主食用米の生産が急減した。風評被害もあるが、農家自体が大幅に減ったからだ。和牛の繁殖など畜産が比較的早く再開されたこともあり、少数の担い手が農地をまとめ、飼料生産に取り組んでいる。それでも休耕田は多いが、耕畜連携が農地の荒廃を防いだ部分は確実にある。
水田で飼料用作物を生産すれば転作奨励金が出る。いわゆる「事実上の減反政策」だ。それがなければ飯舘の耕作放棄地はもっと多かっただろう。その意味では、減反政策が農地を守ったともいえる。
飯舘は特殊だと言われるかも知れないが、同様の事情を抱える地域は他にもあろう。高齢で米作りをやめる農家は全国的に増えている。一方で「米育ち豚」など国産飼料にこだわる畜産農家も多い。減反は後ろ向きな面ばかり強調されるが、農地を守り地域農業振興に貢献してきた面もある。
しかし、主要メディアは「減反悪政論」一色だ。政府の米増産方針を受けた社説を読むと、たとえば7日付日本経済新聞は「生産基盤の弱体化を招いた政策」と断じ、特に飼料用米助成を減らすよう求めた。
同じ日の中日新聞(東京新聞)は「減反自体は2018年に廃止したが、大豆や小麦に転作すれば補助金を支給する制度に変えて事実上続けた」とした。大豆や小麦への転作助成は18年のはるか以前からあったので、明白な事実誤認だ。そして、減反が耕作放棄地の増加を招いたと決め付けている。
主食用米増産にかじを切っても耕作放棄地が減るとは思えない。増産が可能なのは転作というバッファー、つまり荒廃を免れた農地のストックがあるからだ。減反政策が畜産との連携や地域農業の「選択的拡大」に一定の役割を果たしてきたことも考える必要がある。米以外の作物の生産振興も視野に、多角的な議論を求めたい。
(農中総研・客員研究員/飯舘村地域おこし協力隊)
日本農民新聞 2025年8月25日号掲載