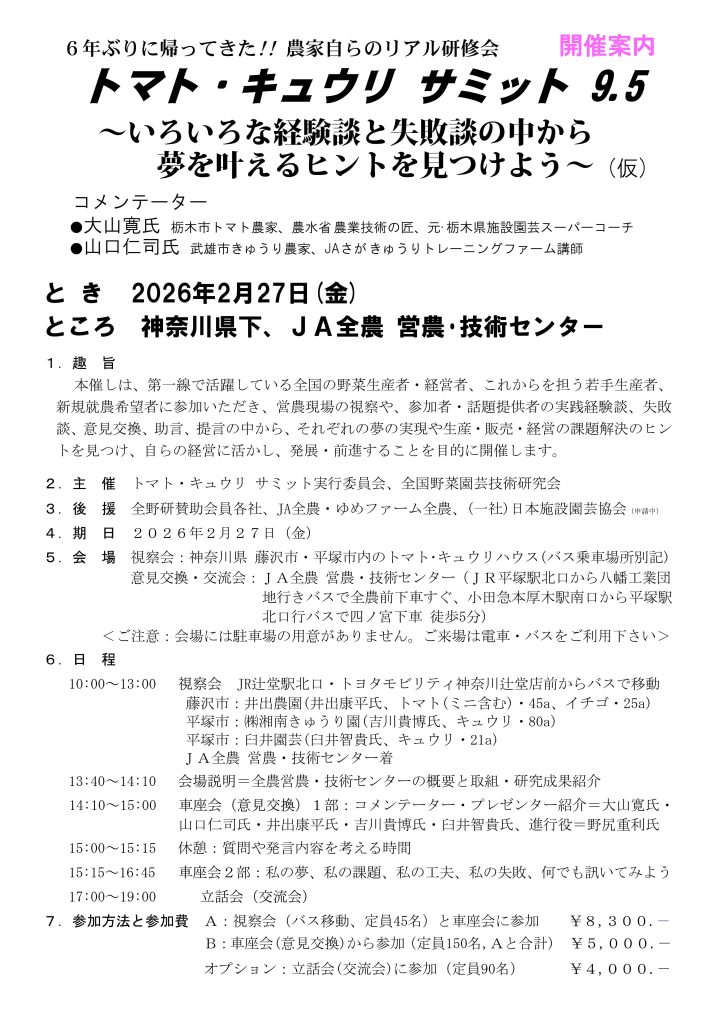〈本号の主な内容〉
■このひと
クロップライフジャパン これからの取組み
クロップライフジャパン 会長 岩田浩幸 氏
■JA共済連 令和6年度の取組みと成果
■かお
JA共済総合研究所 理事長の 小川良介 氏
■クローズアップインタビュー
林野庁長官に就任した 小坂善太郎 氏
 このひと
このひと
クロップライフジャパン これからの取組み
クロップライフジャパン
会長
岩田浩幸 氏
クロップライフジャパンは5月14日に開催した通常総会で新役員体制を決め、新会長に岩田浩幸氏(日本農薬㈱代表取締役社長)が就任した。岩田会長に、会長就任の抱負や2025年度のクロップライフジャパンの取組みなどについて聞いた。
続く世界人口の増加 農業維持発展の一助担う
■会長としての抱負を。
当会は昨年5月、JCPA農薬工業会からクロップライフジャパンに名称変更した。グローバルな潮流に沿って新たなステージに立ち、より大きな視点で活動を展開していこうという姿勢の表れだ。
「クロップ(作物)ライフ(生命)」のライフには、持続可能性の意味合いもある。農業現場では、適切な作物保護に寄与する新規農薬とともに、スマート農業や総合防除に利用できる新技術への期待が高まってきている。新名称には、当会が農薬だけでなく作物保護にかかわる革新的な技術の開発と普及、ステークホルダーとの連携強化を通じて、農業の持続的な発展を図り、より幅広く日本と世界の食と農業へ貢献したいという思いが込められている。
そうした中で今年5月、新会長を拝命した。昨年公表した「NEW VISION」に則り、安心安全な食の供給確保に向けて尽力したい。
世界人口は依然、増加の過程にあり、2050年には現在の82億人から97億人になると見込まれている。確実に、食料の確保は重要なポイントになってくる。日本も人口は減少に転じたものの、昨今のコメ需給問題を含め食料安全保障が大きな課題となっている。従来から議論されてきた食料自給率の向上を含め、より大きな流れの中で国内の農業を維持発展させていく必要があり、その一助を担う意味で、クロップライフジャパンの役割は大きい。会長として、その先頭に立ち、新ビジョンに掲げた「将来のありたい姿=目標」に向けて前進していきたい。
病害虫の北上と外来害虫・雑草がリンクし拡大
■足元の病害虫等発生への対応は。
気候変動、特に地球温暖化が問題となる中で、病害虫が北上し、グローバル化に伴い外来侵入害虫・雑草も増えている。これらがリンクして問題を大きくしているという認識だ。
具体的には、飼料用トウモロコシなどのイネ科作物に被害を与えるツマジロクサヨトウ、サクラやウメ、モモなどバラ科の果樹等に被害を与えるクビアカツヤカミキリといった問題害虫が各地で広がり、南米原産のヒユ科の多年草、ナガエツルノゲイトウなどの問題雑草も繁殖域を増やしており、的確な防除が必要になる。
作物保護資材を安定供給 環境負荷低減の創薬が重要
■今年度の取組みを。まず、農業生産性向上と作物保護技術について。
当会の新ビジョンで「将来のありたい姿=目標」として掲げたのは、①日本と世界の食料安全保障、持続可能な農業への貢献、②環境にやさしいイノベーションの推進、③安全の先にある安心な食生活を楽しめる社会–の3つだ。
目標実現のための4つの活動指針では、第1に、日本の農業生産性向上等に対応した作物保護技術の提供を打ち出した。まずは農薬を主体とした作物保護資材の安定供給に力を入れたい。特定外来生物などの難防除病害虫や難防除雑草が増えてきた中で、適切に使える農薬を農業現場に供給することは業界としての大きな使命だ。食料安全保障に寄与できるよう、スマート農業、総合防除の推進に向け、技術情報を適切にマッチングさせる必要がある。
■環境を守るための技術革新は。
化学農薬を主体とした日本の作物保護の創薬技術は非常に優れたもので、世界に誇れる分野だ。1980年以降、世界の農薬の3割程度を日本の農薬メーカーが創出してきたし、この10年ではそのウエイトが4割以上に上っている。
重要なのはイノベーションにより、いかに環境負荷を低減した農薬、より低薬量で高性能な農薬を創出するかだ。省力化による効率的な作物保護の実現で、カーボンニュートラル達成とともに農業の生産性向上に寄与することを目指している。
会の知名度アップへ 消費者、若い世代に情報発信
■会の名称の浸透と農薬に対する理解醸成は。
現状では「作物保護=クロップライフ」という結びつきに、もう一つ分かりづらいところがあるので、ホームページやYouTubeなどのSNSで知名度アップのための対外的な情報発信を積極的におこなっている。
副会長だった昨年、クイズ王の伊沢拓司さんと「食の未来を考える」をテーマにおこなった対談の動画を公開したが、消費者や若い世代の方に、農薬や作物保護の役割、有用性、農業や食の確保にどうつながるかを、第三者と語り合う中で理解してもらえるような手法も重要だ。農薬を日ごろ使っていただいている農業生産者と異なり、直接的なベネフィットを感じにくい消費者の理解向上には地道に取組んでいきたい。
■人材育成への取組みは。
国内のみならず世界においても日本の作物保護、農薬の技術は役立っている。クロップライフジャパンとしても、作物保護関連学会や有識者との交流やさまざまな勉強会等を通じて情報を共有し、グローバルな意識を持ち、食の安定確保に向けて積極的に携われる人材を育成したい。
広報など各委員会 SNS等を用い活動推進
■理事会の下にある委員会の活動は。
当会には5つの委員会があり、運営委員会はクロップライフジャパンの要の組織として、ビジョン全体に関し活動の方向性を決め推進している。
技術委員会は農薬の安全性、環境負荷などに関する国内外の規制の動きについて会員への情報発信や行政との情報交換を行っている。
安全対策委員会は生産者に対し、農薬の適正使用を啓発するとともに、農薬の安全性や役割についてホームページ等を通じた外部発信の一部を担う。
SNSの活用を含む情報発信を行う広報委員会は、より消費者に受け入れられやすい、業界のスタンスやビジョン、役割の発信に努めている。
国際委員会はグローバルな潮流を踏まえつつ農薬の輸出入活動を促進し、クロップライフインターナショナルとの連携を図っている。
JAグループと目標は合致 戦略的パートナーに
■JAグループとの連携について。
食料安全保障への対応、食料自給率の向上、持続可能な農業の展開、イノベーションに基づく適切な農薬・作物保護資材の使用、また農薬に関するファクトをどう伝えるか–が当会の主な活動だが、JAグループも生産者の代表として近い役割を担っておられる。国内農業の発展や持続可能性が中心のテーマとなる点も合致する。JAグループとは戦略的なパートナーとして、積極的に連携を図っていきたい。