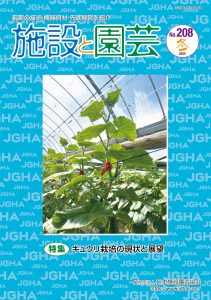〈本号の主な内容〉
■第9回 JA営農指導実践全国大会最優秀賞 を受賞して
JA兵庫六甲 三田営農総合センター 岡部樹 氏
■令和6年度 第9回JA営農指導実践全国大会
JA全中が開催
最優秀賞にJA兵庫六甲・岡部樹氏
■第16回 JA戦略型中核人材育成研修 全国研究発表会
JA全中が開催
■JA全農の JA直売所支援
JA全農 営業開発部 営業企画課専任課長
(JA直売所支援管掌) 播磨賢治氏に聞く
■『家の光』創刊100周年記念 第66回全国家の光大会
家の光協会が開催
「みんなで手をつなぐ協同の輪 食・農・地域に生まれる好循環」スローガンに
協同活動の素晴らしさを伝えるダンスコンテストも受付開始
 第9回 JA営農指導実践全国大会最優秀賞 を受賞して
第9回 JA営農指導実践全国大会最優秀賞 を受賞して
営農指導員として担うべき役割
兵庫県 JA兵庫六甲
三田営農総合センター
岡部樹 氏
JA全中が2月20日に開催した第9回JA営農指導実践全国大会で最優秀賞を受賞したJA兵庫六甲三田営農総合センターの岡部樹氏に、産地振興におけるJA営農指導員の役割を聞いた。
正品率・出荷予測精度の向上で高単価な黒大豆枝豆を
■今回の発表内容を簡潔に。
兵庫県三田市では酒米を中心とした水稲栽培を行っているが、コロナ禍をきっかけに、黒大豆枝豆への作付転換も進めることになった。
元々あった三田ビーンセンターを第2期三田ビーンセンターとして規模拡大し、組合員に黒大豆枝豆の作付を推奨してきた。第2期ビーンセンターが設立され1年を経ると、①虫害や収穫遅れによる正品率の低さ、②出荷予測が難しいこと、の2つの課題が発生し次の改善策に取組んだ。
①正品率の改善では、優良事例の共有や栽培暦の見直しをはじめ、栽培講習会や現地研修会を実施。また普及所と定点生育調査を行い、公式LINE等でタイムリーな情報発信を行った。
②営農指導力の向上では、Z-GISやモニタリング機器「露地ファーモ」等を導入したことで、営農情報を数値化・見える化。若手からベテランの営農相談員のスキルを平準化しレベルアップを図った。
③販売単価の向上ではZ-GISやデジタルノギスを使い、出荷時期・袋数の予測精度を向上。
新ブランド「六甲黒ゆたか」を立ち上げPRし高単価を追求し、部会販売高は1億円を達成することができた。
組合員との対話を重視して地域の課題を解決
■ご自身の営農相談員としての歩みは。
営農相談員としては11年目。最初の3年間は宝塚市を担当し、4年目からは三田市の支店に異動し現在に至る。部会では、トマト、キュウリ、白ネギ、うどを担当した。担い手不足等の地域の課題に対し、集落営農の立ち上げや新規就農者の呼び込み等を積極的に行っていた。
このような取組みの中で、地域と人をつなぐためにも、組合員の方としっかり対話することが大切だと実感するようになった。
黒大豆枝豆のメリット営農情報を可視化する
■黒大豆枝豆の作付転換において工夫した点は。
黒大豆枝豆の作付転換で最もハードルが高いのは、出荷調製に時間がかかること。黒大豆枝豆の出荷調製作業は全行程の7割強を占めるため、組合員からは大きな抵抗があった。
そこで第2期ビーンセンターでは、JAが選別作業や袋詰め作業等を行うことを組合員に繰り返し説明した。
また黒大豆枝豆の収支シミュレーションを分かりやすく説明したチラシを配布。支店ごとの作付提案会を開催し、個人を対象にした作付提案も実施した。
提案の際には、補助事業の活用で機械化を進めたことで大幅に出荷調製作業が省力化できること、作付転換で農業所得が向上することを強調して伝えた。組合員に何度も説明したことで、枝豆の作付につながったと感じる。
またZ-GISや露地ファーモの活用を通し、数字の見える化に重点を置いたことも重要だ。三田市では1~4年目の経験が浅い営農相談員が多いため、防除時期や収穫時期等の適切な判断がまだ難しい。そのためにも、感覚ではなく数字を見える化することが必要だと考えた。
例えば、Z-GISに圃場の播種時期を登録すると、積算温度をもとに作成された収穫目安表から防除基準日や収穫基準日が分かる。
スマートフォンにアプリを入れることで、防除、潅水、収穫時期を現場の巡回時に確認が可能となった。また収穫基準日をもとに販売計画に落とし込むこともできるようになった。
これらの取組みが営農指導力の向上につながった。
新ブランド名公募に500点 取引先と出荷情報を密に共有
■新ブランド「六甲黒ゆたか」では、どのような展開を進めてきたか。
黒大豆枝豆の新ブランド名を決めるため、令和5年に兵庫県の事業を利用し公募したところ、生産者や取引先も含め500点程の応募が来た。最終的に関係者と協議し「六甲黒ゆたか」に決定した。関係者とともにブランド名の公募から取組んだことが、新ブランドをみんなでつくりあげようとする雰囲気にもつながったと思う。また「六甲黒ゆたか」の認知度向上のために、メディアでの発信や取引先の視察受入れにも力を入れた。
販売計画を取引先にしっかりと共有することが、高単価を実現できた大きな要因だ。枝豆がどの時期に出てくるかが明確だと、取引先も値段が高い時期に当てはめていくことができる。商談でも数量をはじめ、異常気象による収穫の遅れ等は早めに情報共有し、迷惑をかけないよう心掛けた。
一方、規格外品の黒大豆枝豆は農福連携を通し、ベーカリーパンの原料や三田市の学校給食として使っていただいている。
生産者としては、育てた黒大豆枝豆は消費者の口に入れてほしいと思っている。地産地消やSDGsの考えも大事にしつつ、捨てるものを減らす形で進めていきたい。
生産者同士をつなぎ地域農業の振興を進める営農相談員に
■営農相談員として大切にしていることや今後の目標について。
営農相談員は、生産者同士をつなぐ役割も担っていると考えている。生産者同士は意外と横のつながりが少なく、JAが架け橋となる場合が多い。営農相談員は生産者の情報もたくさん知っている。
だからこそ、地域農業を守っていくためには、地域の組合員としっかりと対話することが重要になる。JAの営農相談員として、半歩前を行く気持ちで地域や組合員を引っ張っていきたいと思う。
営農相談員の目的は、地域農業の維持・発展だ。黒大豆枝豆の振興は手段であって、目的ではない。
今後は枝豆振興を手段に、早生枝豆や後作の提案もしながら、地域農業を維持することができる強い経営体をつくっていくことが目標だ。