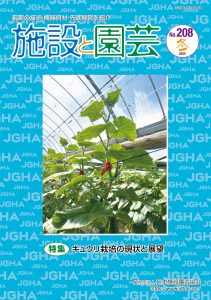〈本号の主な内容〉
■TAC・出向く活動パワーアップ大会2024 JA部門 全農会長賞を受賞して
JA山口県の担い手に出向く取組み
JA山口県 代表理事専務 水本房俊 氏
■JA人づくりトップセミナー
JA全中がWeb開催
■JA全農 第8回和牛甲子園
25道府県40校の〝高校牛児〟が集う
総合優勝に広島県立西条農業高等学校
TAC・出向く活動パワーアップ大会2024
JA部門 全農会長賞を受賞して
 JA山口県の担い手に出向く取組み
JA山口県の担い手に出向く取組み
JA山口県
代表理事専務
水本房俊 氏
JA全農が昨年開いた「TAC・出向く活動パワーアップ大会」は、担い手に出向く活動をより強調し、その活動基盤の強化、活動による担い手の所得増大、生産基盤の維持・発展、食料安全保障の強化に資する「食」と「農」への貢献をテーマに各地の優れた取組みを共有した。同大会でJA部門の全農会長賞を受賞したJA山口県の担い手に出向く取組みを水本房俊代表理事専務に聞いた。
県1JAで信頼関係再構築
■担い手に出向く体制づくりの背景は。
平成31年に県下12JAが1つになりJA山口県が誕生した。令和5年度末現在で組合員数が20万9681名、うち正組合員が6万6226名の組織になった。
本所のほか、それぞれの地域に11の統括本部を設置し、支所や営農センター機能の見直し、統廃合等を進めてきたが、この間に組合員から職員との関係が薄れてきたとの声が増えた。特に、担い手への出向く体制が築けておらず、従来からの農家との信頼関係が希薄化してきたことは大きな課題になった。
高齢化が進み農業人口が減少するなかで、担い手不足が最大の課題であり、今後の地域農業を守っていくための後継者育成が急務になっている。
そうした背景から、担い手のもとに出向いて行き、寄り添い、いろいろな課題をJAの総合事業を活かして解決していくため、令和2年度にTACを配置し拡充を図ってきた。
担い手総合対策室を設置し部門間連携
■TACの役割とJAでの位置づけは。
当初は本所営農指導部に担い手とJAとの繋がり強化を目的に、5名のTACを配置した。期中にはさらに3名を増員し、一日5件以上の訪問を基準として活動を開始した。
令和3年度は担い手支援活動のさらなる充実を目指し、TAC専門・責任部署として、「担い手総合対策室」を新設した。JA内での部門間連携を指導できるよう専務理事の直轄部署にして、同時にJAと中央会の共通部署として機能発揮に努めている。TACはさらに3名増員して11名体制になった。
増員の過程では営農指導員経験者など、法人の相談役になれるような職員を選任してきた。いろいろな意見や課題を聴き解決するスタンスで、必要なものはJAの各担当部署にもっていきTACの活動と繋いでいる。
これまで『TACの活動は大事なのだ』という意識の徹底に取組んできた。『TACとは何だろう?』から始まって、活動のなかで十分理解できたのは、「担い手総合対策室」が、横断的連携を主導し、研修等にも力を入れてきた成果だと評価している。
わかる化、見える化で活動を後押し
■活動の拡大、充実に向けた施策は。
TACを配置した当初は活動がなかなか現場に浸透しないという課題があり「TAC活動マニュアル」を作成した。TACの目的・役割・目標・評価基準などを示し、活動のわかる化を図った。
TACにはどのような役割があり、なにをめざすのか、効率的に活動するうえで必要なポイントを示している。半期に一度行う担当者の人事考課でもきちんと評価できるよう、わかりやすく評価基準を示した。頑張って活動しているTACをきちんと評価し、賞与や昇給、キャリアアップ等に反映し、担当者のモチベーションアップに繋がるように工夫している。
TACは何をしなければならないのか、方針と目標を掲げて担い手に寄り添っていく。それが農業所得の増大にも繋がると信じて動いてみる。その結果がさらなるJA利用にも繋がる。このマニュアルを通じてTACに限らず、担い手にもJA役職員全体にもTACが必要だということをアピールしてきた。
また、活動を見える化する独自の「TAC日誌システム」を構築した。基本は日々の活動を上司に報告するものだが、情報のなかには共有した方がよいものや担当者の手本になる例を記載している。関係部署や担当者が共有できるようにシステムの活用説明書を作成し、閲覧できる職員の幅を広げている。
このシステムのなかには、TACの活動状況を数値化した個人別活動実績やエリア単位や全体での集計状況がある。実績表では訪問件数、面談件数、重点項目の提案状況とその成果、情報連携の頻度などが確認できるようになっている。
表のなかには、どのような目的でどのような行動をしたのか、偏った活動になっていないかなど、活動のプロセスも見える化している。自分自身の活動手順の振り返りや管理者の指導に活かせるように示し、より効率的、効果的訪問ができるよう努めている。これら活動状況は、役員はもちろん本所や統括本部の全所属長に毎月配布し、広く周知している。
JAの中でも、まだまだTACとは何? という職員はいる。活動を知ってもらえるとTAC自身も頑張らなければという気持ちになる。みんなに認めてもらう仕組みづくりをすることは重要な仕事だ。
TACに対する一番の評価は、「JAはよく来てくれる」「TACはよくやってくれる」「TACのおかげでよくなった」という担い手の声だが、その声が全ての個人に届くかわからない。TACの活躍する姿をみんなにしっかり見てもらうために数値化した。
例えば、訪問や面談件数が増えた、集めた情報を関係部署に何件提供したなど、数値化できるものは数値化し、その目標を達成した者を評価していく。
情報連携の強化には、「情報連携シート」を活用した。TACが収集した情報のうち、TAC単独では対応できないことを当該担当部署や担当者に迅速に確実に繋ぐ。いつどの部署にどのような情報を繋いだのか、その対応はどうだったかを管理者が常に点検できるようになっている。
TAC間の情報共有、事例の共有を目的とした毎月のTACミーティング会議や、他部門との連携や情報共有を目的とした会議などは定期的に開催する。特に半期に一度行う担い手総合対策室全体会議は、全事業本部長、部課長などにも出席を求め、担い手支援に役に立つ情報の提供を受けている。
JA利用に繋がる好循環を目指して
■TAC活動の体制・環境づくりの成果は。
重点訪問先は、毎年各統括本部単位で見直しを行い、TAC1人当たり50先を基準に選定している。選定した先のJA利用状況を事業ごとに確認し、状況に応じてランクを分類し、このランクが上がるように活動する。その実績はTACそれぞれの評価にも結びついている。
これらの取組みにより、TACの活動の必要性・重要性の理解が深まり、TACに対する支援・協力も日々増してきた。TACの担い手に出向く頻度は毎年上昇し、1人当たりの訪問件数は令和3年度の505件に対して5年度は941件に増えた。
訪問件数の増加に伴って担い手からの相談とその対応、提案回数も当初の計画を上回ることができた。担い手との信頼関係ができると要望が寄せられ、出向く流れも出来て、さらに活動量が多くなってくる。販売面、購買面も改善され、JA事業の利用度向上に繋がってきている。
農業者の求めに応えることで、最終的にはJAのいろいろな事業に結びついてくる。その好循環を創りたい。その意味では信頼関係づくりはうまく出来ていると思う。
JA各部門が連携し、全体で担い手を支援
■TACの活動で強化していることは。
令和6年度からさらなる機能発揮を目指して、直接現場で指導できるTACエリアマネージャーを3名配置した。部門を繋ぐ総合事業マネージャーとしての役割も担い、担当者の指導、管理をはじめ、さらなる連携強化による充実したTAC活動が展開できるように努めている。今年度はTACの人数を24名に増員した。
担い手コンサルティングに関しては、令和4年度より信用事業本部の融資課が主体となって取組んできたが、営農経済職員も巻き込み、担い手コンサルティング活動を主導する部署が必要と考え、今年度より担い手総合対策室に「担い手対策課」を新設した。
担い手コンサルティング業務を指導する部署として、優良経営体や経営改善が必要な先に対し、経営者からのヒアリングや経営分析を実施して課題解決に向けた提案などを担当する。
農業資金に関しては、信用事業本部の融資課が主体となってコンサル活動に取組んでいるが、営農経済職員も巻き込み、担い手コンサルティング活動を主導する部署として担い手対策課を設けた。
専門部署とともに全体で取組み、経営をサポートし生産や販売とセットで提案していくことが重要だ。その意味では担い手コンサルは期待されていると思う。これから集落を保つためにはどうしたらよいのかを、様々な観点から助言できるコンサル活動を展開していきたい。
経営が成り立たなければ農業は続かない。そうしたコンサルをJAがしていかなければならないことをTACにも浸透させていかなければならない。
法人同士の連携もこれからの課題だ。労働力不足対策は部分的な作業ではすでに取組まれているが、JAが仕掛けをつくり調査しながら上手くコーディネートしていくことが一つのテーマだ。土地はあるが人手が足りないところに、手を差し伸べることによって、法人経営もよくなるし、安定的に農作物の供給もできる。その橋渡しをJAが行っていかなければならない。
農業生産を維持・拡大するためにJAはどう支援すればよいのか。足りないところを支援していく法人をJAがつくることも考えられる。
「総点検」で策定した「振興計画」を実践
■これからのTAC・JAの活動は。
担い手に出向く体制を整え展開していくなかで、農業就農者の高齢化や労働力不足、組合員や職員の減少に伴う関係性の希薄化など、改めて大きな課題であることを認識した。これらの課題に向き合い、5年先、10年先を考え、山口県の農業をJAとしてどのように支援していくのかという観点から「地域農業総点検運動」を昨年度から展開している。
現状を確認しながら今後の意向を聴き、それを踏まえてJAの支援策を検討する。現状把握から意向確認、それに基づいた継続支援や新たな施策へ。これからの地域農業を組合員とともに考えていくきっかけになる運動だ。
昨年度の第1ステージでは、生産部会や集落営農、農業法人などの担い手経営体を対象にした507先で実施した。第2ステージの今年度は、直売所の出荷者を中心として多様な担い手など5千先を対象に、全職員による出向く活動として展開した。6月からの第3ステージでは、中核的担い手約9千先を対象に実施した。
これらの調査点検結果を踏まえ、関係部署や連合会さらに県など関係機関と連携し、担い手不足を中心に課題解決に向けて支援策を一緒に検討している。
点検を行いながら、担い手のニーズに応えていけるような取組み、JAならではの地域支援活動として、農業資金、農作業リスクに対する補償、土壌診断や生産資材のコスト低減、労働力確保対策、事業承継などに力を入れて提案している。
この調査結果はこれで終わるのではなく、もっと深掘りが必要なところから、今後の出向く活動の的確な対策を講ずるためのベースになるものだと考えている。
JA内、担い手、組合員、地域の全てを繋ぐ
■持続的な農業へTACのテーマは。
われわれの取組みはTACの担い手に出向く体制を整えたところで、まだ道半ば。担い手の支援は実を結ぶまでに時間がかかり、難易度が高い。しかし最大の課題である新たな担い手の確保と育成支援は避けて通れない。次世代対策は同時に高齢者対策でもあり、これまで共に歩んできた組合員に最後まで寄り添う関係づくりと、その関係を次の世代にバトンを渡せるようにコーディネートをしていく。そのために事業継承計画の策定も支援している。
TACを中心にいろいろな事業が結びつくことによって、JAの総合力を本当の意味で発揮しなければならない。それぞれの地域や担い手に農業を切り口とした様々な提案をして、必要な支援を根気強く継続していく。
食料の大切さが注目されている今は、取組みのチャンスでもある。JAとしても再生産価格の確保も含めて、食の大切さ、価値を消費者にしっかり訴えていけば、まだまだ農業は持続できる。そのためにもTACの役割は非常に重要であり、期待されている。われわれはこれにしっかり応えなければならない。
TACはJA内、担い手、組合員、地域、全てを繋ぎ、手を取り合ってみんなを元気にし、お互いの「ありがとう」が日本で一番あふれるJAになるように活動を展開していく。