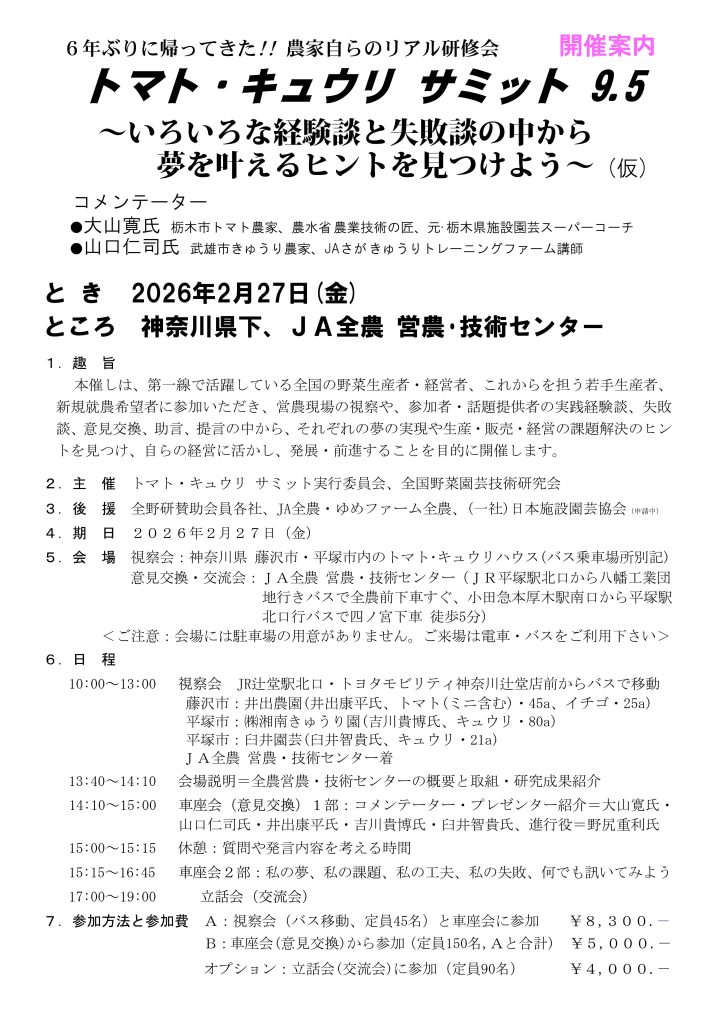〈本号の主な内容〉
■このひと
米穀流通の課題とこれからの展望
全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)
理事長 山﨑元裕 氏
■第6回 協同組合の地域共生フォーラム
日本協同組合連携機構(JCA)が開催
「災害をめぐる協同組合の役割と連携のチカラ
~暮らし続けられる地域づくりのために~」テーマに
■かお
JA全農 代表理事専務の 齊藤良樹 氏
JA全農 監事の 髙橋龍彦 氏
■第3回 JAバンク経営者フォーラム
農林中金が開催
 このひと
このひと
米穀流通の課題とこれからの展望
全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)
理事長
山﨑元裕 氏
米穀卸売業者が組織する全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)は今年3月、20年後を見据えた「米穀流通2040年ビジョン」を発表し、事業をめぐる中長期的な展望と取組み方向を提示した。今年6月理事長に就任した山﨑元裕氏に、課題と今後の展望を聞いた。
米の需給・価格をめぐる潮目が変わった?
■最近の米をめぐる情勢について。とくに今夏は〝令和の米騒動〟とも言われる状況があったが。
ちょうど新米出回り前の端境期に大きな要因が複数重なったことから、米需給にタイト感が表出した。消費者に不安が広がり米穀販売業界も対応に追われた。
今回の状況は、大不作による〝平成の米騒動〟とはまったく異なる。米流通量の過不足により価格が上下することは従来からあるが、今回の場合、結論はまだ出ていないものの現時点では、いよいよ潮目が変わってきているのかなという感触を持っている。
販売業者間取引相場の高騰については、通常なら年越し前に取引量が増えて相場が落ち着いてもおかしくないのだが、現状からは、この価格水準のまま年を越すようにも思われる。
昨今、社会への影響力はマスコミに加えSNSも大きくなっており、現在も米価格は気にかけられている。来年4~5月頃にはまた注目度が上がり、家庭内在庫の需要が高まることも考えられる。一方では余る可能性も十分にあり、なかなか見通しはつかない。
米消費量は、様々な関係機関の尽力もあり現在のところ下げ止まった感がある。インバウンド需要も+αの増加要因となっている。おにぎり屋が増えて若者の人気を集めているといったよい傾向もあるようだ。
そこへきて米の価格がこれだけ急上昇すれば、買い控えが起きがちになる。外食業界でも、多くの食材が値上がりするなか米もとなれば、メニュー変更や量を減らすことにつながる。こうした状況が続けば、また一気に米余りということにもなりかねない。
これだけ米に関心が集まっているいま、米、ごはんについて改めて考え議論する機会につなげることが望ましい。米の適正価格のあり方についても議論が広がるとよい。それは生産者のためにもなることであり、我々としても発信に努めていきたいと考えている。
「魅力的な米穀流通の姿」に近づけるために
■全米販は今年3月、「米穀流通2040年ビジョン」を発表した。中長期的な課題について。
㈱日本総合研究所とともにまとめた「米穀流通2040年ビジョン」では、最悪の予想図となる「現実的シナリオ」と、魅力的な米穀流通の姿を描いた「野心的シナリオ」の2つを提示した。
中長期の課題として第一に考えなければならないことは、米生産力の減退問題だ。現状を看過し続けた場合の「現実的シナリオ」では、2040年の国内需要量は2020年比41%減の375万t、生産量は米生産者の減少などにより50%減の363万tになると試算された。国内需要量を国産だけでは賄いきれなくなり、米穀流通は営業赤字に転落するおそれがあるという数字だ。
一方、「野心的シナリオ」は、「需要拡大」「生産支援」「流通改革」といった打ち手を実現することにより、2040年の国内需要量722万t(2020年比+13・4%)、米穀市場規模5・97兆円(同+18・0%)が見込めるとしている。
将来の米穀流通を、より「野心的シナリオ」に近づけるため取組みを強めたい。
その具体策は、「需要拡大」では、多角的な米需要の創出や、輸出などによる市場の育成と拡大があげられる。
「生産支援」では、担い手の確保、出口の開拓、効率化支援などがある。我々も、産地が作ったお米を預かり実需につなぐ従来の業務範囲を広げ、生産サイドにも入っていく必要を感じている。
「流通改革」では、持続可能な価格形成への取組みや、垂直方向・水平方向の連携など関係者の役割再定義が求められるだろう。製粉メーカーが商品を開発・販売する麦の世界のように、米についてもメーカーのような感覚でマーケットに入り込んでいく必要があるのではないか。
産地に入るにもマーケットに入るにもパートナーが必要で、垂直・水平方向の連携をいかに進めていくかが重要となる。
全米販の取組みは改正基本法の方向と合致
■改正された食料・農業・農村基本法への評価と、次期基本計画がつくられているなか国に求めていきたいことは。
食料安全保障が前面に打ち出された改正基本法の方向性は、我々の問題意識とまさに根を同じくしている。全米販が取組んでいくことは、改正基本法がめざすところと合致すると考えている。
したがって、国に求めることというよりは、米業界もきちんと取組んでいると信用いただくことがまず大事。そして壁に当たった場合には、相談し、支援もいただきながら進んでいければと思う。
同じところをめざし得意分野生かしながら連携を
■生産者、JAグループへの期待は。
改正基本法の下、持続的な食料安全保障の確立へ向け、生産者、JAグループのみなさんにはぜひ頑張っていただきたい。我々自身も、これまで以上に産地とマーケットをつなぎ、お互いの要望を伝えるなどしながらお手伝いしていきたい。
いまは、その土地で米生産をいかに続けていただけるかという持続性確保の問題が重視されてきている。とてもおいしいこのお米は5年後10年後も食べられるのか、数年後には食べられなくなるかもしれないのか。マーケットサイドがこうした情報を求め、今後も安心して供給してもらえる産地に重きを置くようになってきている。
産地の持続性を確保しておいしいお米を作り続けていただくために、我々としていかにサポートできるかが重要だ。
また、物流問題は我々にとっても大きい。共同輸配送や共同保管といった策も考えていく必要があるだろう。グループ化により労力やコストを抑えられれば、産地にもメリットがある。会内では、個別に完結しようとする自前主義はもう限界に来ているから脱却しようと呼びかけている。
農協と我々とは、地域における役割が違うだけでめざすところは共通していると思う。そのことをお互い認識し、いかに連携しながら取組んでいくかに、より力を入れていきたい。
全米販の組合員数は北海道から沖縄まで約140。産地に近い卸、集荷も行う卸、消費地でマーケットに近い卸とその特性は多様で、組織形態も株式会社、組合と様々、規模も千差万別だ。多様性に富む組合員が、それぞれの得意分野を生かしながら水平・垂直連携を行っていければと思う。