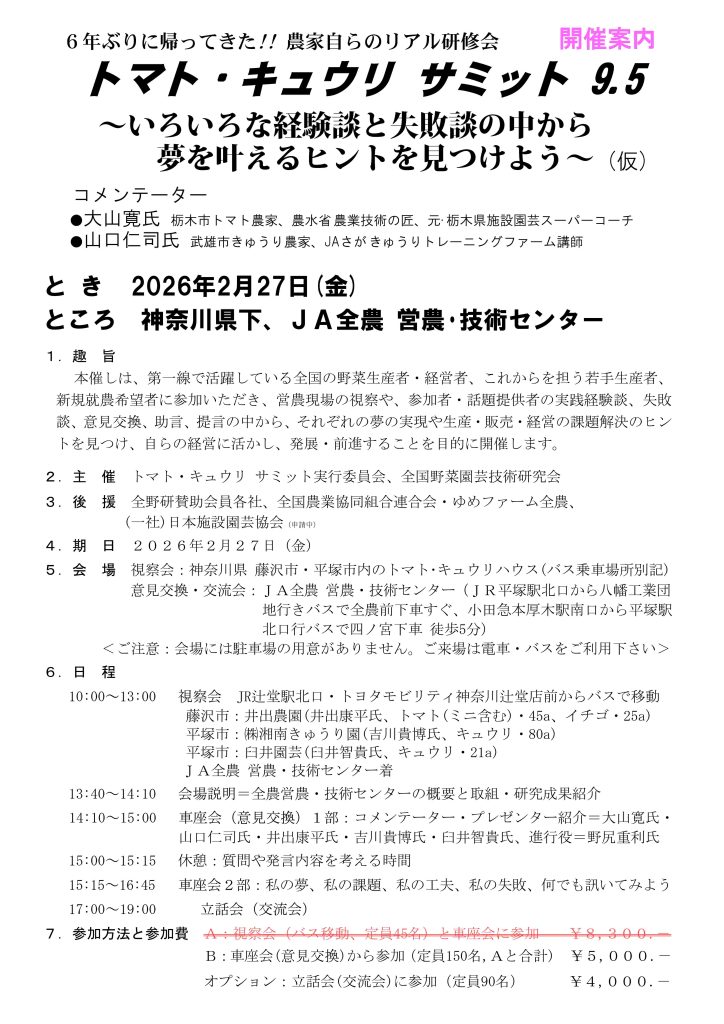洪水が頻発し治水についての認識は高まりつつある。
記録的な豪雨が増加しており、新聞情報では、川で洪水が起きる一歩手前の氾濫危険水位を超えた川の数が、2014年は83であったものが、19年には403と5倍近くにまで増加しているという。
こうした状況・情勢を踏まえて注目されているのが「流域治水」という考え方である。
これまで治水の中心的役割を担ってきたのはダムと堤防であるが、ダムの貯水容量や堤防の高さは過去の降水量を基にしており、近年の豪雨への対応は難しくなってきているとされる。
流域治水には「危険な浸水想定区域」にある住宅等を安全なエリアに移転させることや、「災害危険区域」にある老人ホームなどの建設を禁止することも含まれるが、メインとなるのが農業用ため池や田んぼ、草原や湿地、森林や緑地の貯水機能の活用と、都市におけるビル地下に貯水施設を整備する等の「内水氾濫」対策だ。
この「河川治水」から「流域治水」への転換が報じられて思い起こすのが、徳川第八代将軍吉宗による治水での関東流から紀州流への転換である。
関東流は伊奈流とも呼ばれるが、江戸時代前期は洪水の大流量に対して洪水を完全に押さえ込んでしまうのではなく、堤防からの越流を許す乗越堤や霞堤を用い、防げる範囲内で洪水を防ぎ、防げない規模の洪水に関しては、その越流を容認する考え方に立った。
これを強固な堤防によって川を統御しようとする紀州流にシフトしたもので、河川の屈曲を廃止して直線的に改修し、洪水を一気に押し流すようにし、これによって農地をはじめとする土地の利用効率の向上を可能にした。
今般の流域治水は関東流による治水に通じるところが多く、1716年に開始された吉宗による享保の改革から約300年を経過しての〝先祖返り〟的転換でもある。
新潟県では15市町村の1万4640ha(2018年8月時点)の田んぼでの貯水機能向上に取り組んでいることが報告されている。また農研機構農村工学研究部門では、稲の減収なしに貯水機能を発揮させる目安を明らかにするとともに、収量が減らない貯水期間を割り出し、手軽に水を貯められる器具を開発する等の成果が発表されている。気候変動により先行きの情況の悪化が懸念される中、さらなる研究・開発を期待したい。
このためにも特に触れておきたいのが「土中環境」という概念だ。
これは㈱高田造園設計事務所代表の高田宏臣氏が打ち出しているもので、現代は「健康な大地本来の浄化機能、貯水機能などの大切な働きを失っ」てしまっていることから、「土中の環境から自然界全体を健康にしていく。そんな視点と技術を再び見直すことがとても重要で不可欠」としている。そこで強調されているのが「土中の水と空気の循環という視点」であり、河川の流れは川底の伏流水および地下水と連動しており、水が河川と伏流水と地下水の間を円滑に行き来するのが健康な状態であり貯水能力も高いとする。
江戸時代の伝統的な知恵を生かし、土中環境というあらたな視点も加えてより強靭な治水対策が構築されていくことが望まれる。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2020年10月5日号掲載