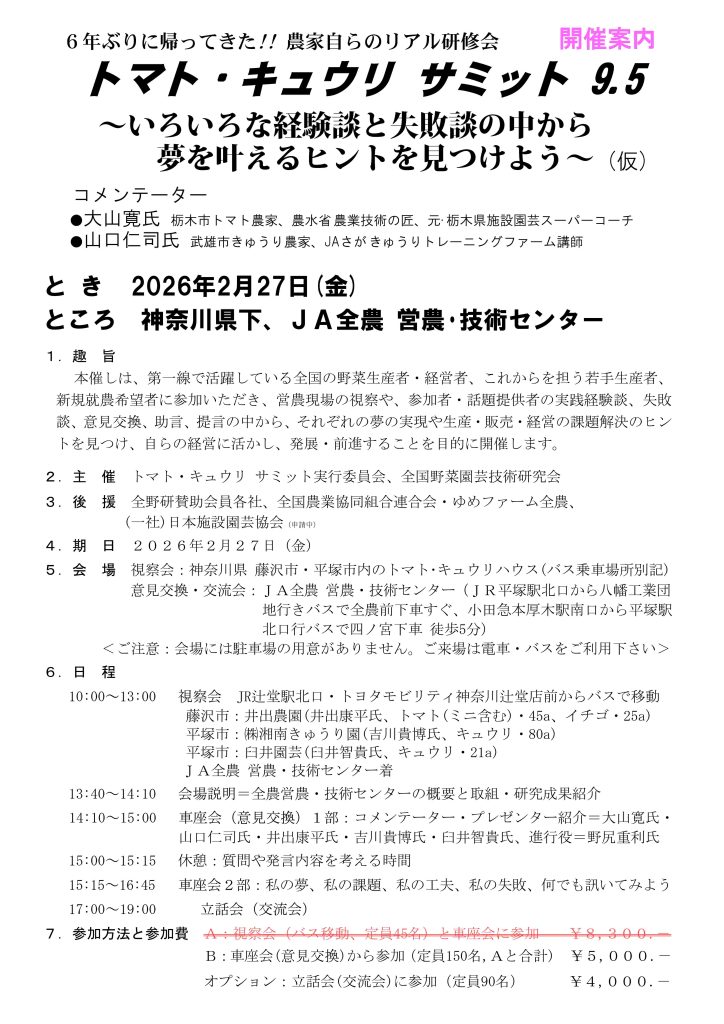「4月は残酷きわまる月だ」。新型コロナウイルスで出鼻をくじかれた新社会人らのニュースを見て、そんな言葉を思い出した。
英国の詩人エリオットの代表作「荒地」の冒頭の1行。心躍るはずの季節が「残酷」とは逆説的だが、新たな命の芽生えはさまざまな苦悩の始まりでもあるという意味か。いずれにせよ希望に胸を膨らませて第一歩を踏み出そうとした若者らに残酷すぎる春だ。
先月末に閣議決定された食料・農業・農村基本計画も新型コロナの悪影響に言及した。具体策には踏み込んでいないが、平時からリスクに備える必要性を指摘し、中長期的な課題として検討するという。
ここ数年の農政は「農業の成長産業化」を掲げ、輸出やインバウンド需要への対応を奨励してきた。日本の農産物は高品質なのだから海外の富裕層に売ればいい、人手不足は外国人で補えばいい–そんな風潮があった。
今回のコロナ禍が、そんな思惑を吹き飛ばした。揚げ足を取る気はない。ただ、経済のグローバル化を前提とした成長戦略が大きなリスクを伴うことを知るべきだろう。パンデミック(感染症の世界的大流行)の背景もグローバル化である。
グローバルな危機の克服にはグローバルな連帯が必要だ。誰かを非難したり、差別したりしている余裕はない。自分を守り、身近な人を守り、社会を守るため一人一人に何ができるかを考え、国や自治体の指示を待つのではなく主体的に行動したい。そして、苦境に陥った人々のことを思い、自分なりのやり方でサポートしたい。少なくとも日本は個人の自由が保障される民主主義の国なのだから。
「荒地」が発表された1922年は第1次世界大戦終結の4年後で、詩にも荒廃した欧州の状況が反映されている。同じ年にワシントン海軍軍縮条約が締結され、2年前には国際連盟が発足するなど世界は連帯の道を模索していた。一方でヒトラーやムッソリーニが頭角を現し、スターリンが独裁体制を固めたのもこのころだった。その後の歴史はご存じの通りだ。
エリオットは別の詩で「正しく種まくことを考えよ」とも書いた。残酷な現実は、正しい種をまくチャンスでもある。人類全体が試されている。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2020年4月25日・5月5日合併号掲載