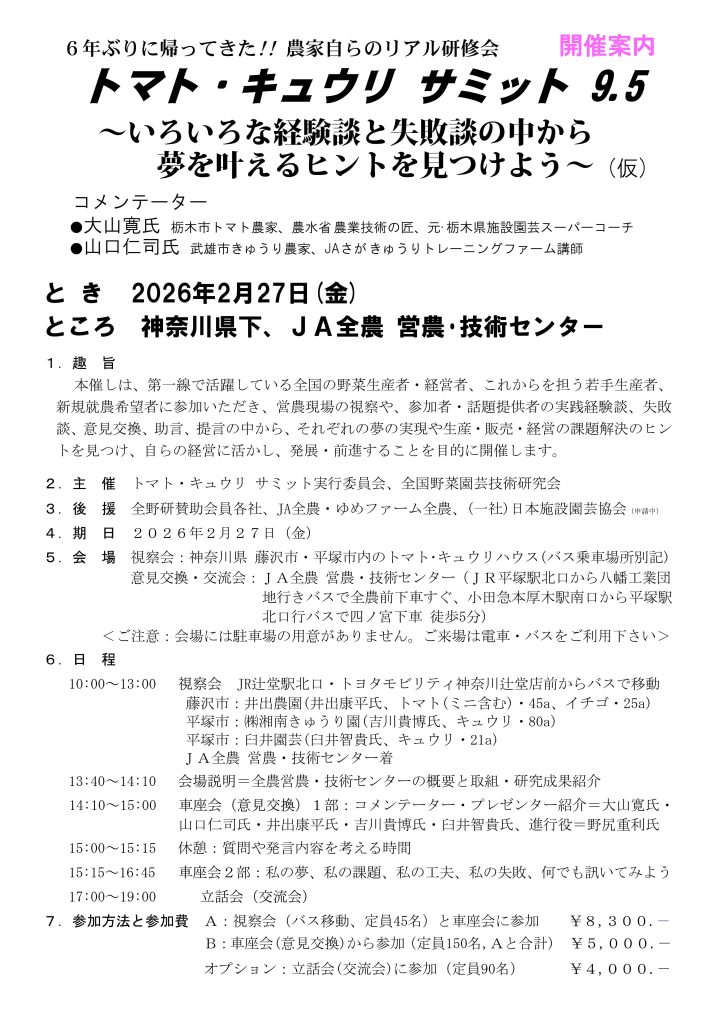〈本号の主な内容〉
■アングル
日本の施設園芸の将来像
(一社)日本施設園芸協会 常務理事 藤村博志 氏
■JA全農 令和7年度事業のポイント
園芸部 鈴木貢 部長
■イチゴ定植期の病害虫と防除対策
栃木県農業試験場 研究開発部 病理昆虫研究室長 山崎周一郎 氏
■施設園芸新技術セミナー・機器資材展in愛知 開催概要
日本施設園芸協会が9月4~5日、愛知県豊橋市内で開催
「施設園芸・植物工場における先進技術と東海(愛知県)の地域農業を支える施設園芸」テーマに
 アングル
アングル
日本の施設園芸の将来像
(一社)日本施設園芸協会
常務理事
藤村博志 氏
施設園芸を取り巻く状況は、栽培施設の設置面積の減少が続きピーク時の7割になるなど、海外の先進国が構造改革を進めている中で、経営規模や新技術の導入で大きな差が付き始めている。これに対応するため、(一社)日本施設園芸協会は今年、5年先、10年先の将来像を描く「施設園芸の将来像に係る懇談会」を設置し、政策提言することにしている。同協会の藤村博志常務理事に聞いた。
規模拡大・新技術導入に遅れ
■日本の施設園芸と海外の現状は?
日本の施設園芸は世界をリードする立場にあったが、近年はその将来像が見えづらくなっている。全国の施設園芸面積は1999年の5万3000haをピークにして減少が続き、現在は3万7000haという状況だ。
農水省のデータをみると、施設園芸農家数は2005年の21万戸が2020年は14万戸になった。この間に面積も同様に減ったため、1経営体当たりの経営規模は21aが20aと変化がない。経営規模別には1ha以上の層の面積は増えているが、増える数よりも減る数が大きく全体として減少が続いている。
栽培施設の内容的にも例えば高度な環境制御を取り入れた温室が報道面で脚光を浴びているが、その面積は1300haで割合は、施設園芸の3.4%に過ぎない。将来的な施設園芸生産を考えると、所得=反収をあげるためには環境制御を積極的に行うことが必要になるが、一部の先進的な農業者以外は、規模が小さいこともあって、設備投資を伴う新しい技術の導入は進みづらい。大変難しい課題ではあるが、施設園芸の特徴を生かせる環境制御は大きなハウスだけが導入するものではなくて、小さなハウスでも、環境制御をはじめとする先進的な技術の恩恵を受けるために、これまでの施設園芸の抜本的な見直しが必要と思う。
一方、施設園芸の産業化に取組んでいるオランダや韓国では農家数が減少しても面積は増加している。経営規模は拡大しオランダは2.2ha(20数ha経営規模の農業者も)、韓国は1haと大きく、さらに団地化やクラスターの形成によって再生可能エネルギーの共同利用やスマート化技術の導入を促進して、より高いレベルの収益性と持続可能性の両立を図っている。
日本も点で見れば数ha規模の経営があり、先端を行く経営は環境制御に加えて栽培データの活用などスマート化が進んでいる。しかし面的な広がりがなく、その段階を目指す中間層が非常に薄い。1ha以上の層が増えているので、その拡大をもっと加速化する必要がある。その際、スマート化による生産性向上と再生可能エネルギーの活用が求められる時代、1経営体の規模も1ha規模を超える拡大を目指すだけでなく、地域の施設園芸農家が連携して、地域で標準化された施設・設備を取り入れた団地化への取組みが重要なカギを握ると考えている。
日本が食料安定供給と地域の活性化を実現するためには、ベースには農業・農村における所得と雇用確保の場が不可欠となっている。その中でも若い人たちが夢をもって農業に取組んでもらうために、その中核になるのは、消費ニーズを常に意識して労働集約型で収益性が高い施設園芸だと考えている。それとまとまった農地の下で展開されるスマート化された土地利用型農業や畜産との連携によって、地域をみんなで守っていこうと意識すれば労働力・エネルギー等の友好活用や新たな6次産業化への展開も期待される。
残念ながら、こうした方向への歩みが遅れており、この傾向が続けば施設園芸技術の継続も危うくなる恐れがある。また、生産現場が変わらなければ、これまで施設・機器を開発し、供給してきた企業も農業分野への積極的な投資を続けることが難しくなることを危惧している。
夢を持てる施設園芸の将来像、方向性づくり
■日本の施設園芸を再び盛り上げるには?
施設園芸の発展には将来像と方向性が必要だ。
今、現場は、スマート化を通じて収量の確保や生産性の向上のみならず、数年後の脱炭素化への取組みが求められている。それをどう実装するかが課題になっている。日本の場合、個々の技術はすごく進んでいるが、まとまって新しい技術を使うためのシステム化や地域内でのパッケージングの思考が弱い。
これまで日本の施設園芸は各地域や個々の農業経営に対し、きめ細かな対応を行ってきたが、全体として標準化・汎用化が進まず、施設園芸という産業でみると結果として規模拡大の遅れにより、国際的な競争力が低下していると感じている。今後、農業者の所得と雇用の場を確保するには儲けるための規模拡大や団地化、新しい技術の導入による生産性・生産力の向上は必須である。これには地方自治体や農業団体等による地域の将来像作りと連携への仕組み作りのもとに、地域内の農業者の合意形成とともに、企業、大学、国等が一体となって、技術の標準化や人材育成等、新技術を低コストで、効率的・効果的に導入する取組みが欠かせない。
当協会は今年、「施設園芸の将来像に係る懇談会(将来懇)」を設けた。まずは施設園芸・植物工場に造詣の深い学識経験者に集まっていただき、将来像のたたき台作りを開始した。
今後、そのたたき台を先進的な農業者や当協会の会員企業を中心に、関連企業、行政・研究機関、農業団体等と意見交換を行い、年明けに政策提言としてまとめたいと考えている。次世代を担う若い農業者が夢を持てる施設園芸の姿や企業サイドにも投資を呼び起こす提案にしたい。
省エネ技術、環境制御などのきめ細かな高度な技術の導入や、直近の高温・気候変動への対応、さらに施設園芸で大きな負担になっている労働時間の削減に向けたロボット化など、今後普及が進むと考えられる技術についても、研究開発のみならず効果的な社会実装につながる評価体制のあり方も検討が必要である。
また、農業者が儲けるために必要とする専門的な技術・知識を学んだり、高いレベルでコンサルを行う支援体制も、全国の大学・民間企業の力も借りながら、国と地方自治体が連携して取組んでいくことが重要だ。
日本のハウスの大宗を占めるパイプハウスから、これまで培ってきた次世代施設園芸事業やスマートグリーンハウス展開などの事業成果、開発がすすむことが期待されるゼロエミッション型ハウスも考慮し、規模拡大や団地化に向けて、現在の経営規模に係わらず連携・協力を前提に新時代の施設園芸の実現に繋げたい。その先には、日本が競争力を引き続き保ちながら、国内の食料安全保障のみならず、世界の食料安定供給にも貢献する技術の先頭に立つのが植物工場を含む施設園芸分野だと考えている。
生産性の高い経営ができる人材育成
■特に重要な課題は。
国内の人口が減少する中で農業者の人口が減ることは仕方がない。しかし日本が得意としている品質の良い農産物を安定供給することはとても重要で、その基盤になる人づくり、農業の持続と地域の活性化に直結する新しい農業者の育成は一番の課題だ。
当協会は野菜流通カット協議会という加工業務用の野菜を取り扱う事業者と関わりが深い。この分野では安定した品質で必要な時に必要な量をきちんと出せる農業者や産地でなければ信用を得られない。
多くの野菜が1年中食卓に上るようになってきた。トマト、キュウリだけでなく野菜の安定供給に施設園芸が果たす役割は大きくなっている。
センサー技術が発達したことで栽培環境データの収集と記録は広く行われるようになったが、そのデータを農作物の収量増大や品質向上にいかにつなげるかは課題で、現状では十分に活用されていない。
高性能な機械や設備は高価であるが、データの活用によって収量や品質に反映させることで十分な価値を生む。そのためには技術を理解し、経営的に活用できる人材の育成が不可欠である。
当協会で一昨年視察した韓国は、スマート農業を推進する一環として次世代の青年農業者を育成する施設団地「スマートファーム革新バレー」を設置している。教育実習とあわせて修了後に一部の学生が経営を行う賃貸施設、企業が開発した新技術の実証用施設も同居し、最新技術を利用した栽培と経営を学べる。4拠点・合計120haという規模で、毎年約200名の新規農業者を輩出する。日本でも一部の大学や企業が最新技術の研修を運営しているが規模と育成の集中力に大きな違いがある。
こうした新技術の活用を前提とした仕組みが日本にも必要だ。企業・大学・行政が連携し、地域や県境を超えた育成ネットワークを構築することで、若い農業者が夢を持てる施設園芸の未来が開かれる。人材育成は、農業発展と地域の持続可能性を支える要である。
市場は国内のみならず海外にも
■規模拡大、連携、スマート化が生むものは?
産業としての施設園芸を考える時に、国内のみならず海外も市場として視野に入れる必要がある。これまでは国内の東京や大阪、中京の市場へ出荷することを各産地が競っていたが、冷凍技術や品質保持技術のレベルが高くなったことで、日本よりも経済力がある海外を目指す経営も考えられる。
今後の施設園芸は農産物の生産だけではなく、栽培技術・流通・販売・経営まであらゆるものに付加価値がある「企業的な農業」へと進化できる。
オランダではデータ活用するためのノウハウを有料で提供するコンサルタントが存在する。そして「料金は高いが、それ以上に儲けることができる」と利用する農業者は多い。
生成AIに代表されるようにシミュレーションの技術が急速に発展し利用が進んでいる。世界のどこからでも栽培環境のデータが得られ、作物の状態が見えるカメラ、気象情報を使ってハウス内の作物の生育予測ができる。日本のハウスの栽培支援は、世界中の栽培環境をシミュレーションや遠隔技術によって日本から海外の農場へも対応可能になるのではないか。
例えば東南アジアにハウスを建て、日本から地元の人たちと繋がって、いろいろな相談を聞きながら、日本のきめ細かな生産技術をベースにした指導を行うことも可能となっている。
将来は日本で農業経営を確立し、世界を相手に経済活動を展開する気概のある農業者が多く出てくることを期待したい。
日本の施設園芸は、優れた技術力という宝を持ちながらも、それを活かすための構造改革や政策支援が不足していると感じている。平均経営面積20aという現状から脱却し、標準化・規模拡大・スマート化・脱炭素化を進めることで、若い農業者が夢を持てる産業へと変革できる。新しいものにチャレンジしながら新たな施設園芸に取り組むことは、DXの時代の生産・流通・消費等への変革や農業の支援のあり方も含め、農業全体によい影響をあたえるのではないか。