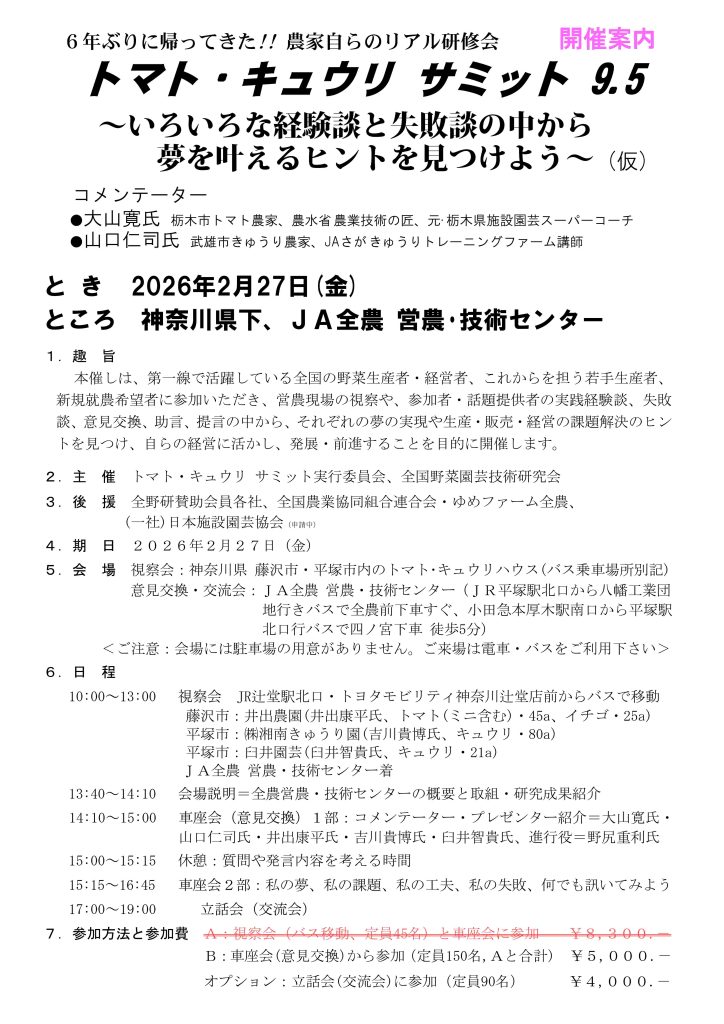コロナ禍で今夏の帰省は断念したが、筆者の生まれ故郷は北海道函館市。例年なら夜景見物などの観光客でにぎわっているはずの函館山のふもとに、小さな石碑が建っている。第2次世界大戦中の「学徒援農」の記念碑だ。
日本の敗色が濃くなった1944年から翌年の終戦まで、食料増産のため約20万人の若者が北海道の農業地帯に送り込まれた。戦地へ出征した「学徒出陣」は大学生が中心だったが、援農は10代半ばの少年たち。軍需工場などで働いた「学徒勤労動員」の農業版である。
当時14歳だった父も、函館から十勝へ派遣された。地平線まで広がる畑で未明から日没まで続く作業に嫌気がさし、友人と2人で馬を盗んで逃げだした。すぐにつかまって厳しい制裁を受けたそうだが、父はその体験を懐かしそうに語った。ただ「あんな時代が二度と来ないようにしないとな」と付け加えるのも忘れなかった。
3歳下の母にとって、戦時中の記憶は「ひもじい」の一言に尽きる。空腹で何もする気になれず、壁にもたれて食べ物のことばかり考えていた。戦争が終わり「これでおなかいっぱい食べられる」と思ったのに配給の食料は増えず、がっかりした–そんな話を聞いた。
大半の日本人にとって大戦は「飢餓との戦い」でもあった。戦場で亡くなった軍人・軍属は約230万人だが、その6割強は餓死・病死だったとされる。日本軍は物資の補給を軽視してやみくもに戦線を拡大し、米軍はその補給路を徹底的に断った。多くの日本兵は前線で孤立し、戦わずして飢えと病に倒れたのだ。
「銃後」も同じだ。日本経済は1931年の満州事変を転機に戦時体制へ移行していった。あらゆる資源が軍需部門へ集中的に投下され、食料生産を含む民生部門はその犠牲になった。国民は「ぜいたくは敵だ」「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」と耐乏生活を強いられたが、精神主義でつくろいきれなくなった結果が学徒援農だった。
75年前、民主主義は「生存への希望」そのものだった。民意を顧みない政治は、人命もおろそかにする。今はどうだろう。20年前に亡くなった父や、実家で一人のお盆を迎えている老母の顔を思い浮かべながら考えている。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2020年8月25日号掲載