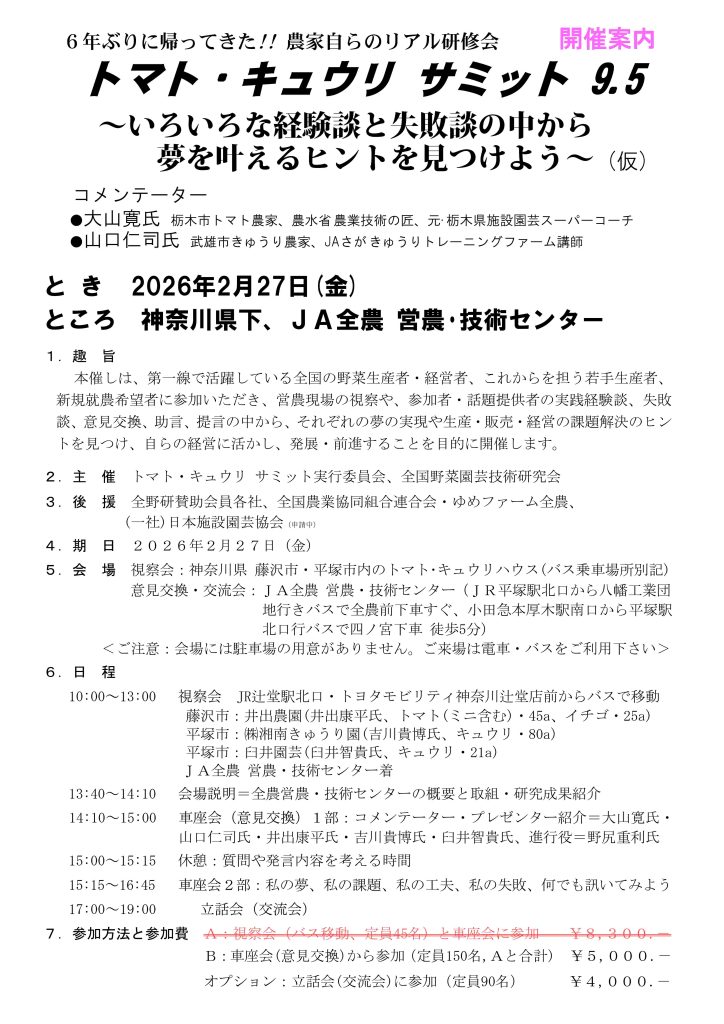東京・新宿などで上映中の記録映画「福島は語る」(土井敏邦監督)を見た。インタビューだけで構成された3時間近い長尺ものだ。途中で眠ってしまうかも――と案じながら見たが、全く無用な心配だった。福島原発事故でかけがえのないものを失った人々が絞り出す言葉の一つ一つが胸に突き刺さり、身じろぎもできなかった。
双葉町から避難し、会津地方の小学校に転勤した女性教諭。3月11日に全校一斉で行われる「黙とう」が耐えられず、被災地の児童を連れて学校を出た。
「何する?」「アイス食べたい!」「よし、先生がおごるぞ!」。アイスを食べながら話すうちに、心の傷があらわになる。放射能や賠償金を巡るいじめ、望郷の思い、離別の悲しみ。それらを胸の奥深く押し込め、平静を装うことが子どもたちのサバイバルなのだ。それでも彼女は授業で原発事故のことを話す。「あなたの役割は?」と土井監督に問われ「伝えること」と答える。
帰還困難区域となった飯舘村長泥地区で石材業を営んでいた男性。後継ぎとして頑張っていた息子が原発事故で心を病み、アルコール依存症や糖尿病にむしばまれて30代で亡くなった。今も長泥の工場に通い、設備のメンテナンスを続ける父親は淡々と経緯を語るが、最後はこみ上げたものを抑えられずに涙をぬぐう。「泣かないことにしていたんだが……おれの人生はこんなふうに生まれたのかなって。でも、おれより不幸な人はいっぱいいるんだぞ、土井さん」
土井監督は三十数年にわたり、パレスチナ難民を中心に「土地を奪われた人々」の声を伝え続けてきたジャーナリストだ。上映後のトークショーでは「言葉の力を信じて、この映画を作った」と語った。かつて報道界の片隅にいた筆者も、改めて「言葉の力」を感じた。同時に、こうした言葉を我々はきちんと受け止め、伝え続けていけるのかを自問せずにはいられなかった。
東日本大震災と福島原発事故から8年。今年も3月11日前後には関連報道が津波のように押し寄せ、そして引いていく。特別に掲載日を繰り上げてもらったこのコラムも、その波の一部だ。さて、東京五輪に沸き立つ来年はどうだろう。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2019年3月15日号掲載