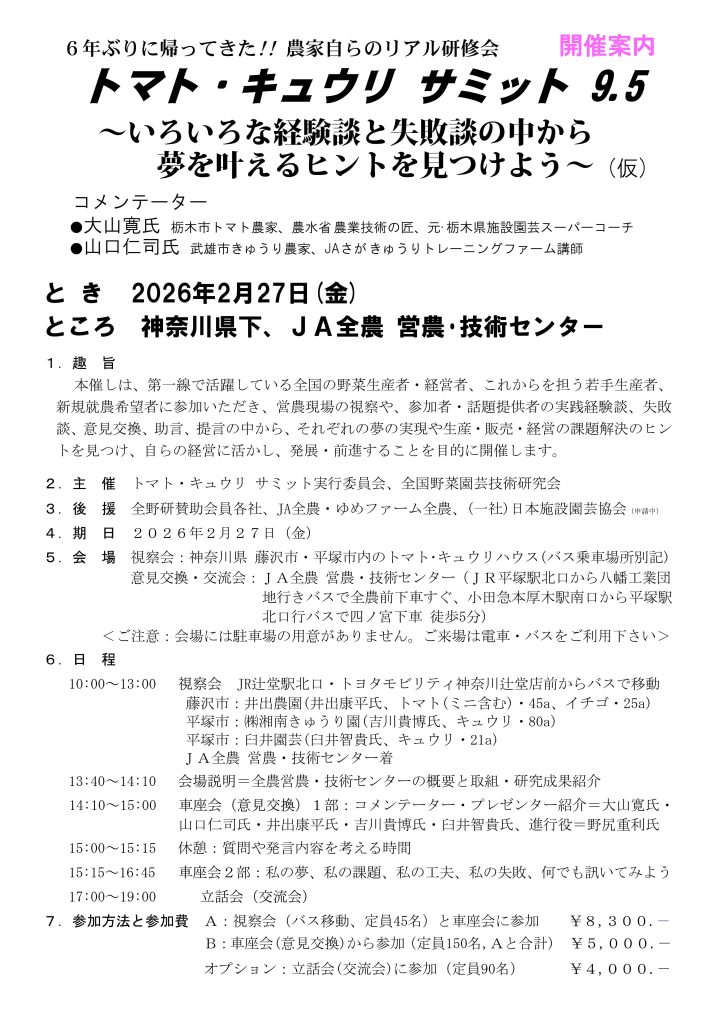英国の歴史家ホブズボームは「長い19世紀」と「短い20世紀」という時代区分を唱えた。前者はフランス革命の起きた1789年に始まり、後者は第1次世界大戦が勃発した1914年から冷戦終結の91年まで。世界史の潮流を踏まえた説得力のある説だと思う。
90年代前半は日本国内でも大きな変化があった。バブル崩壊で経済が長期低迷に陥り、成長力回復のための規制緩和など新自由主義的改革が加速した。農業でも91年発効の牛肉・オレンジ自由化が市場開放の口火を切り、93年末のウルグアイ・ラウンド(UR)実質合意に至った。これも、根底には自由貿易が経済成長を促すという経済理論がある。
UR農業合意が発効した95年には旧食糧管理法が廃止され、米麦の民間流通を基本とする食糧法が施行された。食管法は戦時統制下の42年に制定されたが、その原点は米騒動から生まれた21年の米穀法。つまり、米政策の「20世紀」は21~95年だったといえる。
「総力戦という20世紀の怪物」(ホブズボーム)と、その落とし子である社会主義国家の誕生(1917年のロシア革命は第1次大戦を契機に起きた)により「自由な市場経済」への信頼が揺らいだ。政府による規制や再分配など社会主義的な要素を組み込んだ「修正資本主義」は農政にも反映された。
では、21世紀はどうだろう。とりあえずは古典的な資本主義が復活したように見える。農業を含むあらゆる分野で規制緩和が推進され、たとえば働く人の4割はいまや非正規雇用だ。農家も担い手と土地持ち非農家への階層分化が進む。
こうした分化が「分断」になれば、社会は不安定化する。日本はまだ比較的平穏だが、海外では格差の拡大や中間層の没落を背景に排外主義やポピュリズムが高まる。気候変動などグローバルな課題はそっちのけで「自国ファースト」の短絡的な主張を掲げる政治家が熱狂的に支持される。
そんな世界を見ていると「21世紀」も短命で終わるのでは–と思えてくる。問題はその先だ。「20世紀に生まれた最後の新成人」たちの晴れ姿を見ながら、もやもやした思いをぬぐえなかった。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2020年1月25日号掲載