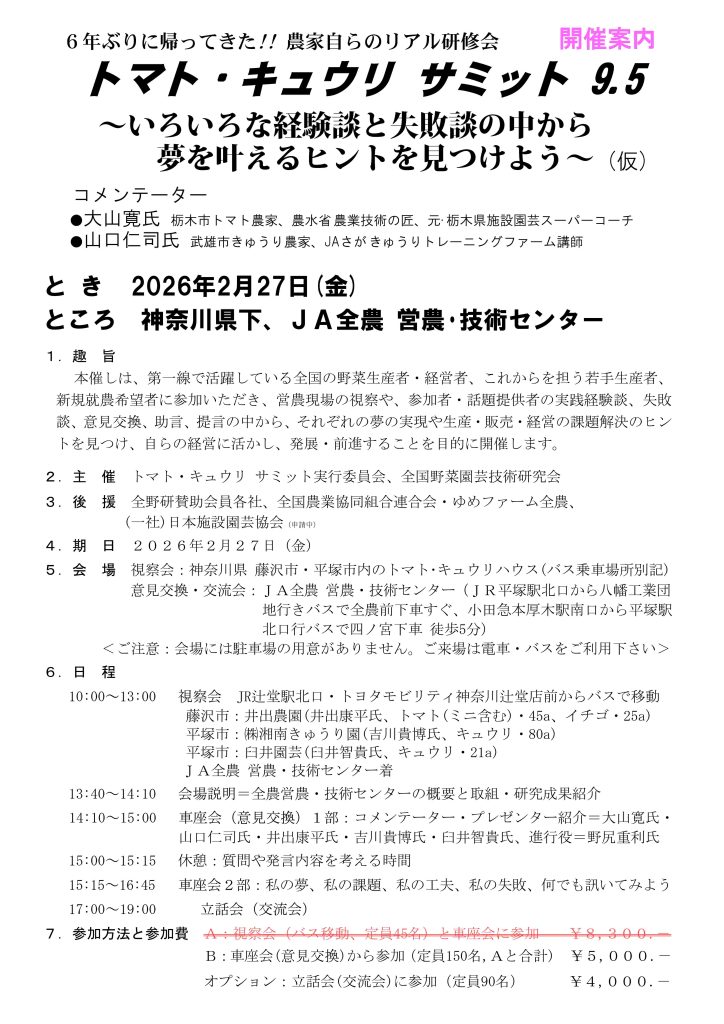以前、行きつけの居酒屋でベトナム人の若い女性が働いていた。名前はリンさん。「まだ勉強中」の日本語は少し怪しかったが、接客態度は明るく好感が持てた。「国に帰ったら日本語を生かせる仕事をしたい。日本にもまた来たい」と笑顔で話した。
1年ほどで姿を見なくなったが、コンビニなどでもグエンさん、ドンさんなど、ベトナム人らしい名札の従業員が増えた。逆に中国系らしい漢字の名前は少なくなった。世界第2位の経済大国は、もはや外国人を呼ぶ側になりつつある。
「労働者を呼んだつもりが、来たのは人間だった」。スイスの劇作家マックス・フリッシュがそう書いたのは50年以上前。スイスも小国ゆえの労働力不足に悩み、イタリア・スペイン・ポルトガルなどからの移民で補った。
ドイツはトルコ人、フランスはアラブ系など、欧州の先進国は多くの異民族を受け入れてきた。経済的な理由ばかりでなく、内戦や民族紛争から逃れてきた難民も多い。それが欧州社会に摩擦と分断を生じさせ、テロや排外主義の温床になったことは否めない。
「だから外国人受け入れは制限した方がいい」とは言わない。冒頭で紹介した留学生のアルバイトも含めれば、日本でほ既に128万人の外国人が働いている。定義の仕方次第では「移民大国」と言っていい状況だ。
それでも政府は「移民政策はとらない」と強弁し、昨年1年間で7000人以上が失跡するなど問題の多い外国人技能実習生制度を残したまま在留資格の拡大に踏み切った。一方で家族の帯同や社会保険の適用は厳しく制限する。これは「欲しいのは労働者で、人間ではない」と言うに等しい。
人口減少に悩む広島県安芸高田市は、外国人の移住に地域の将来を託した。外国人を「いつか帰ってしまう人たち」ではなく、違いを認め合いながら支え合う恒久的なパートナーと位置付ける。浜田一義市長は「『多文化共生』は私たちの必修科目」とまで言い切っているそうだ(芹澤健介著「コンビニ外国人」)。
異なる文化の人々を受け入れるのは決して簡単なことではない。だが、いまや避けては通れない。制度論以前に、国民一人一人が覚悟を問われている。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2018年11月25日号掲載