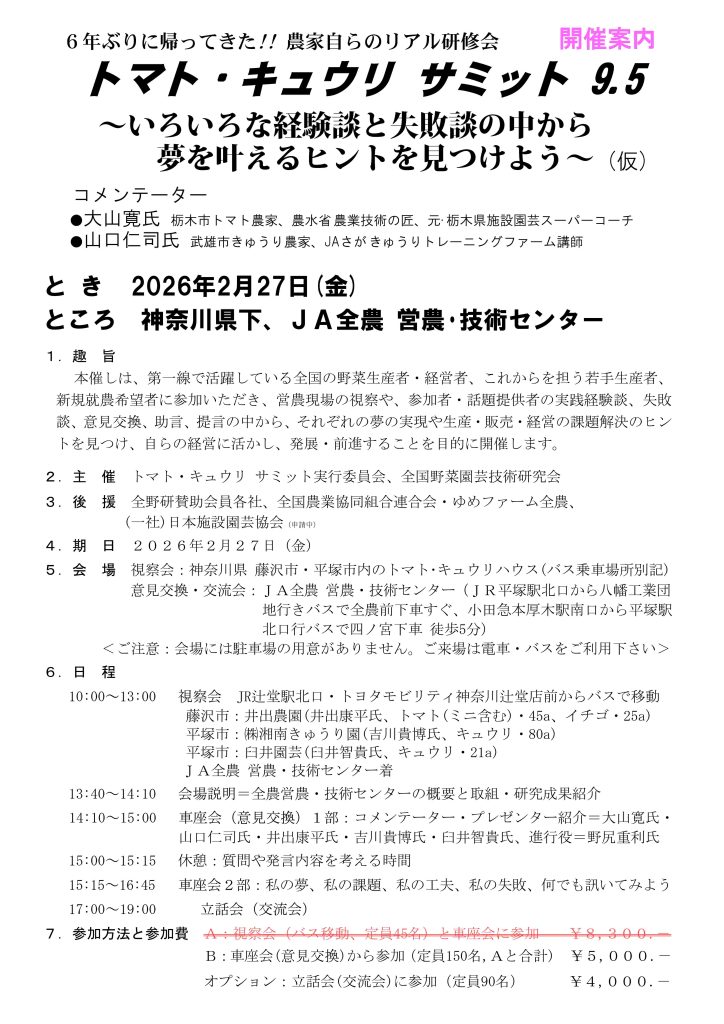農地中間管理機構(以下「農地バンク」)の見直し方針が決定した。来年が農地中間管理機構法で定める、施行後5年を目途とする制度見直しの年となっていることにともなっての見直しではある。農水省の見直し方針案を了承するにあたって野村哲郎・自民党農林部会長が述べた「基本は(地域農家の)話し合いだ。人・農地プランがないといけない。そこに尽きる」との見解は重要で、まさしく的を突いた発言だ。
この数年、農地集積の停滞は明らかで、農地バンクの大幅な見直しは避けられない状況ではあった。すなわち2014年の施行時50.8%であった担い手への農地集積率を、23年度までに8割とする政府目標に対し、17年度は55.2%にとどまり、担い手への集積面積で見ても17年度1万7244haと前年に比べて11%も減少している。集落営農組織の法人化時に、各構成員が機構をつうじて新設法人に農地を貸し付ける等の動きが一巡したと見ることもできるが、基本的には農地の出し手の掘り起こしに窮していたというのが実情で、県レベルでの農地調整一元化の限界が明らかになったにすぎないと見る。
農地バンク見直し方針として打ち出された柱が、(1)「人・農地プラン」の記載内容の見直し、(2)地域の話し合いの活性化、(3)助成制度との連動、である。(1)は、各農地の耕作者の年齢、後継者の有無などを書き込んだ農地マップを作成することを中心とする。これをもとに地域実態に応じて市町村、農業委員、JAなどがコーディネーターとして積極参加して地域での話し合いを活性化しようとするもので、(1)、(2)は一体であり、セットである。
この「人・農地プラン」について、規制改革推進会議が農地バンク創設時の議論の中で、企業の参入を阻害するものであるとして、プランの法制化を訴える農水省に反対して見送りとさせた経過がある。今回、同会議はプランの「活性化が必要」であると主張を一変させた。この間、プラン作成するための地域での話し合いの気運がしぼんでしまっているとともに、「市町村の職員は不足し、話し合いのきっかけだった米の生産数量目標の配分もなくなり、ますます動員が難し」くなっているとの指摘もある。
今回の一連の動きを見て痛感するのは、地域のことは地域が主体となって取り組まなければ解決は困難だということである。農地問題にとどまらず農業・農政問題全般を県レベル、さらには国レベルに持ち上げて解決をはかろうとするほどに、効率化重視と同時に画一化を余儀なくされ、ひいては規制改革推進会議が象徴するように地域の実情を無視し市場化・自由化の対象としてしてしか農業・農村を見られなくなってしまう。行政に問題があることは確かであるが、一方ではここまで行政への依存を強めてきた農業・農村側の問題も大きい。「人・農地プラン」の見直しをきっかけに、農業者主体で地域の話し合いを活性化させていくことからの見直しが、今こそ必要といえる。こうする中で農業者が誇りを取り戻し、地域農業の振興を基本していくところにしか、真の農政改革の入り口はない。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2018年12月5日号掲載