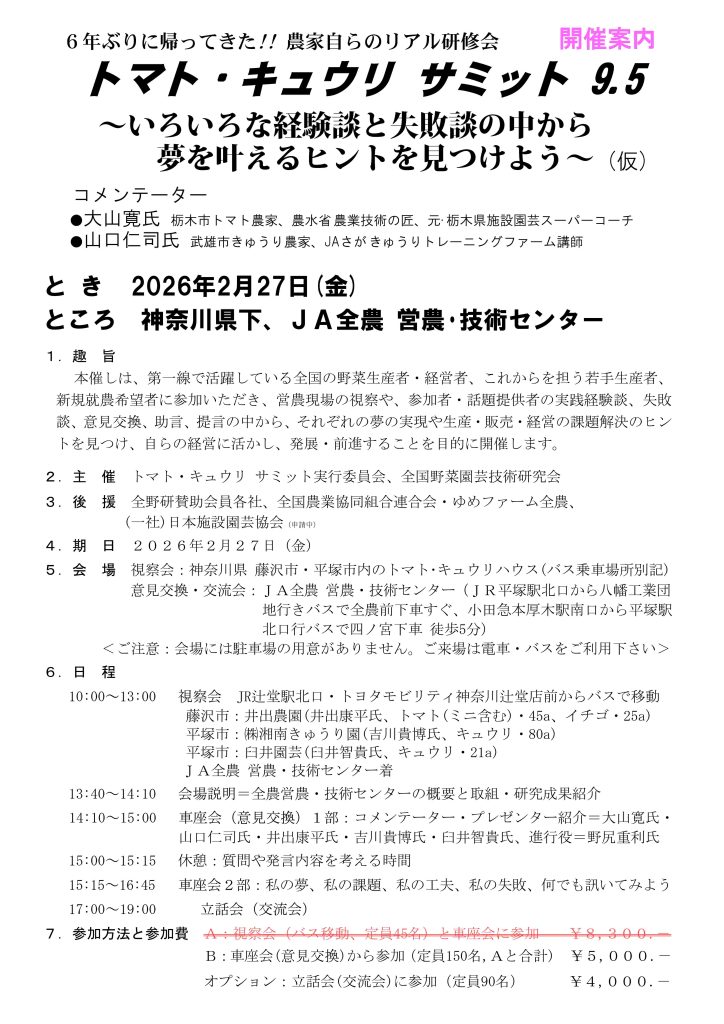過ぐる一年を一言で凝縮すれば「加速する輸入自由化圧力の増大」ということに尽きよう。TPP11そしてEUとのFTAが発効し、最大の懸案であった日米交渉も8月の首脳会議で大枠合意して、この1月1日から発効した。日米交渉決着に際して政府は「共同声明に沿った結論が得られた」と強調する。しかしながら肝心の自動車と部品についての関税撤廃は先送りされる一方で、牛肉・豚肉関税は発効時からTPP国と同税率にする等、米国に一方的に旨味のある内容で押し切られたというのが実情だ。しかも農産品については再協議規定が設けられており、いつでも米国はエスカレートさせた要求を突き付けることができるように措置されるなど、日本の米国従属は強まるばかりだ。
日米貿易協定に伴う国内対策費3250億円の補正予算とともに、20年度当初予算が決定したが、和牛をはじめとする農畜産品の輸出拡大を目玉に、畜産農家への機械導入や施設整備の支援等による国内農業の生産力強化が打ち出されてはいるものの、基本政策に変わりはなく、日本農業の将来への不安が払しょくされるどころか、ますます不安は募るばかり、というのが正直な感慨である。
こうした情勢ではあるが、国際家族農業の10年の開始や小農権利宣言にともない小農、家族農業重視の動きや、11月に練馬区で開催された世界都市農業サミットに象徴されるように都市農業を評価する動き等、あらたな流れが顕在化しつつあることも確かだ。しかしながら農政の方向を転換させていくだけのインパクトのある動きを形成するには至っていないのが現状で、こうした流れを本格化させていくことが新年の基本課題となる。
そこでこの課題に取り組んでいくにあたって最大のポイントとなると考えるのが、SDGsと農政との距離感である。SDGsについてはあらためて述べるまでもないが、国連で15年9月に採択された「持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals」のことで、30年に向けて持続可能な開発のための17の目標と169のターゲットが設けられている。ここで言いたいのは同じ国連の決議であっても、家族農業の10年については大規模化、効率化を至上命題とする政府にとっては、本格的に取り組む意思は希薄と言わざるを得ない。また小農権利宣言については”南“の問題であると理解しているようにうかがわれる。ところがSDGsについては先進国各国も賛成・推進していることに平仄を合わせて、我が国も政府が率先して旗振りに努めており、SDGsが強調する「持続可能性」を正論とする取組については農政も否定できない状況に置かれているということである。
逆に言えば、「持続可能な農業」という枠組みの中で、日本農業の未来を確保するために必要な政策は何なのか抜本的な整理が求められているということである。地域農業の振興、環境保全型農業の推進と合わせて家族農業・小農も含めた多様な担い手の確保がその前提となり、そのための施策が重要となる。令和2年を農政転換の年にしなければならない。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2020年1月5日号掲載