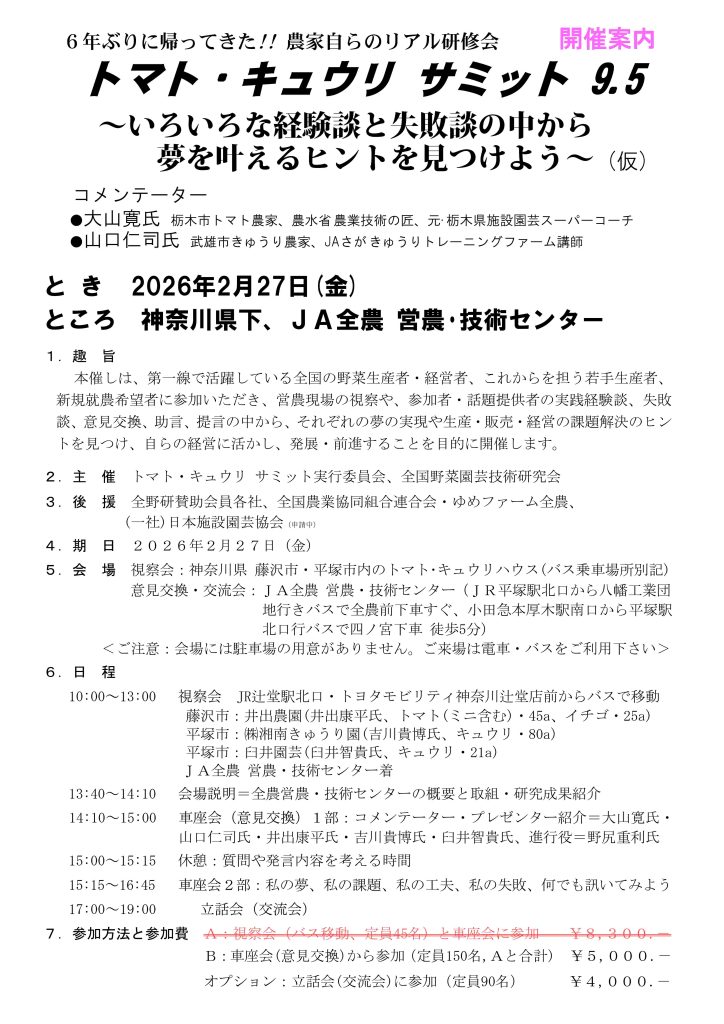家内の実家は長野県伊那市で、95歳になる母親がまだそこそこに元気にしている。できるだけ顔を見せるために、毎月、車を走らせている。母親に会う楽しみが基本ではあるが、そのついでに顔を出すことにしているいくつかの一つが、伊那市の郊外、ますみが丘にある産直市場グリーンファームで、都度、会長の小林史麿さんと小一時間は話し込んでくる。
グリーンファームは随分と知られるようになってはきたが、手短に紹介しておけば、農免道路沿いの飼料畑の中に、1994年にオープンした農産物直売所で、個人経営による「見なし法人」である。200平方mの売り場からスタートし、その後必要に応じて増設を繰り返してきた。本年1月には隣の敷地に新店舗を建設・移転したが、新たな店舗とはいえ、多品種の野菜・果実と花草木、ハチノコ等特産物や薬草、生活用品に農具、書画から骨とう品まで、まさに生活・暮らしに必要なものすべてが並べられており、雰囲気も含めて以前と変わらない。店舗の向かいは“家畜園”となっており、アヒル、ヤギ、ウサギ等々がいて、飼育・販売されている。ヤギはレンタルも行われており、レンタルヤギは百数十頭におよぶ。また旧店舗の敷地は駐車場になるとともに、奥には横長に小屋が連なり、ヤギ等の家畜に加えて、生まれて間もない子猫が入った、「里親を探しています」と書かれたいくつかの籠が置かれており、これを取り囲む子どもたちでいっぱいだ。
年間売上高が10億円超であることもさりながら、年間の来店客数は50数万人と、いつ行ってもにぎわっているのがすごい。特に連休やキノコの販売時期などは大変な混雑となる。何でも生活に必要なものがリーズナブルな価格で購入できると同時に、とにかく見るだけでも楽しく、そこにいるだけで当地の文化が身に迫ってくるような感じを受ける。
先日、小林さんとやりとりしていて、2000名を超える出荷者会員がおりながら、規約はない。よくこれでまわるな、という話になった。(1)生産者、地域は限定しない、(2)出荷時間は生産者の都合に合わせる、(3)委託手数料は20%とする、(4)代金決済は週1回、(5)取り決め・申し合わせ事項等は基本的に設けない、という5つの原則があるだけ。店舗の中は雑然とした感じがしないではないが、置かれているもの、並べ方、ポップ広告等には必然性があり、また清掃等も徹底されているなど、よく見ると整然としていることが分かる。
小林さんによれば、運営方針や規約があるほどに出荷生産者は売り先に対する依存度が高まり、価格・金でしか売り先を考えなくなるという。逆に規約がないからこそ出荷者どうしが自分たちの直売所をどうしたらいいか自ら考えて行動するようになるらしい。一見すると管理していないように見えながら、自主管理を中心に運営されているところがミソだ。
個人経営の直売所ながら、協同活動の本質を体現しているといえる。ここで思い起こすのがイタリアの農協である。イタリアでも大きな農協がないわけではないが、多くは組合員が増えると分裂して新たな組合を作るという。分裂する目安は50人前後で、「大きくなると自分の組合ではなくなる」のがその理由だ。規模は二の次、関係性の大事さを教えている。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2019年9月5日号掲載