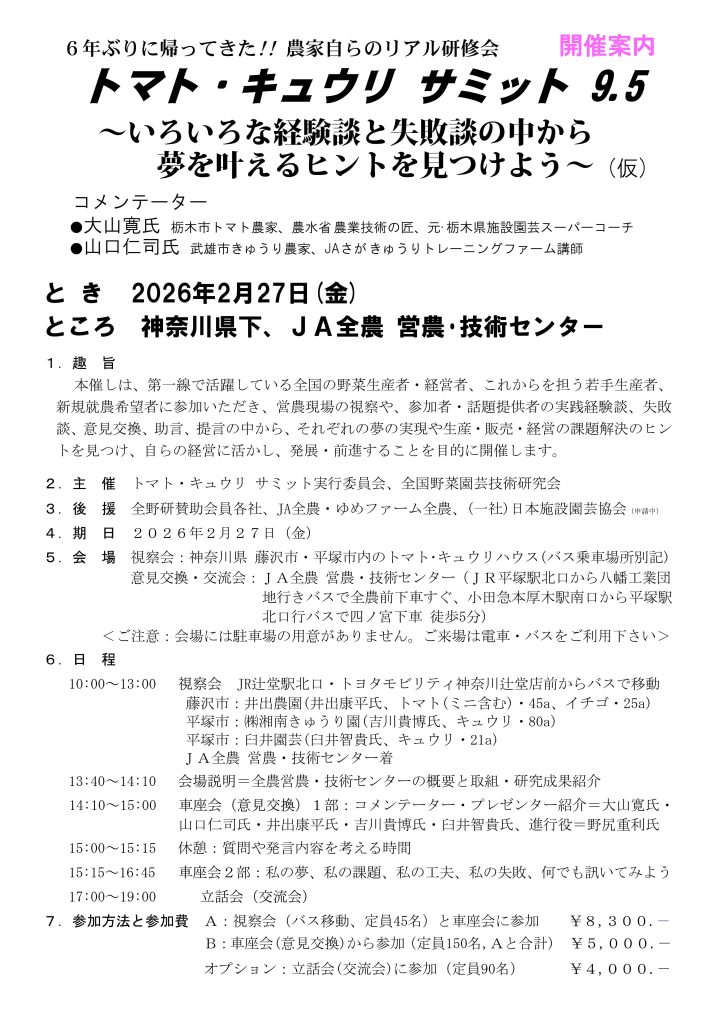大阪大学の坂口志文特任教授が、米国の研究者2人と共同で今年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。免疫機能の過剰反応を抑える「制御性T細胞」の発見という業績が評価された。
免疫は生物の体を異物から守る仕組みだが、時に暴走する。代表格が食物アレルギーだ。食品に含まれる特定の物質(アレルゲン)を免疫細胞が「敵」と認識し攻撃することで、さまざまな症状を引き起こす。命にかかわる場合もある。
免疫の本質は「自己と非自己の識別」とされる。生命を維持するには常に外界と物質をやり取りしなければならない。有用なものは取り込んで「自己」の一部とし、有害なものは「非自己」として排除する。その基準が厳し過ぎると、かえって命を脅かす。極端な場合、自分自身の体を免疫細胞が攻撃するようになる。関節リューマチや1型糖尿病などの自己免疫疾患だ。それを抑えるのが免疫の「自己寛容」という機能で、制御性T細胞はそれを担っている。
坂口さんの先輩にあたる免疫学者で、優れた文筆家でもあった多田富雄さん(故人)は自己と非自己を厳密に区別しない「あいまいさ」が生命の本質的な属性だと考えた(著書「生命の意味論」など)。そして、それを生物個体だけでなく人間社会にも当てはめて論じた。つまり、あいまいさや多様性を受け入れない不寛容な社会は生命力を失うことになる。
7月の参院選で「日本人ファースト」を叫ぶ参政党が躍進し、自民党も「違法外国人ゼロ」を掲げるに至った。そして「奈良公園でシカをける外国人がいる」など根拠不明な排外主義的発言を重ねる高市早苗氏が自民党総裁に就任し、21日には衆参両院の首相指名選挙で選ばれ、内閣総理大臣に就任した。今後、外国人の入国や在留への規制はさらに厳しくなるかも知れない。
人口減少と少子高齢化が加速し、労働力不足が深刻化する日本。農業を含む産業や福祉などの現場では、海外からの助っ人に頼らざるを得ない現実がある。外国人を「非自己」として排除するのではなく、仲間として迎え入れる寛容さが今ほど求められる時代はない。日本社会が自己免疫疾患で自滅しないか心配だ。
(農中総研・客員研究員/飯舘村地域おこし協力隊)
日本農民新聞 2025年10月25日号掲載