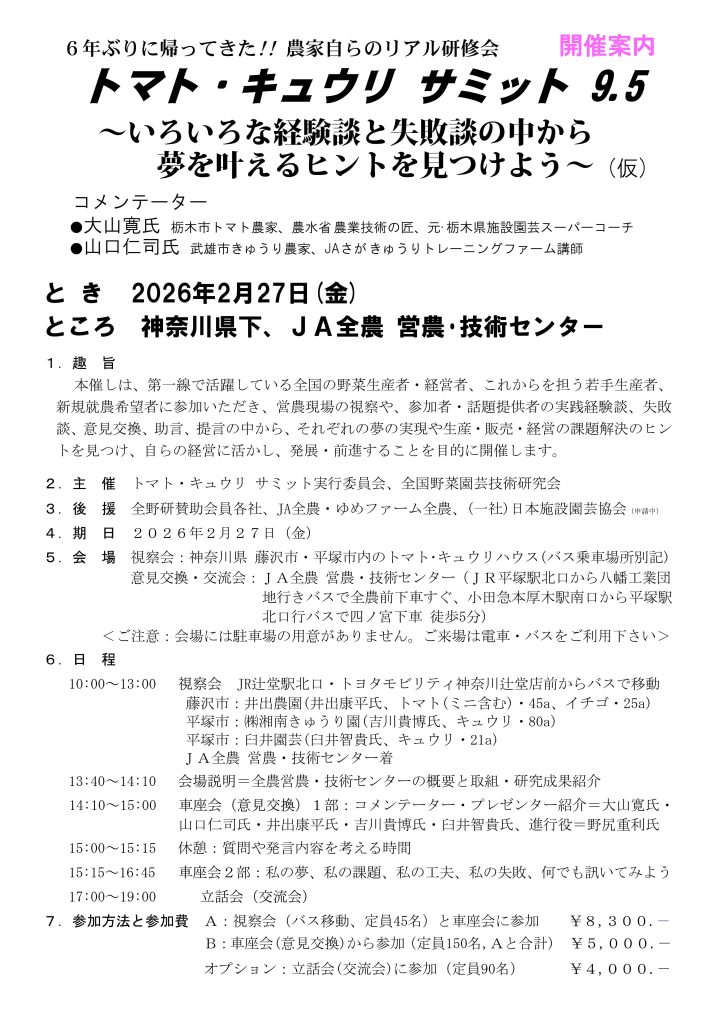生産性の向上、生産コストの低減をねらいに、農水省はスマート農業技術の導入によって、担い手への農地の集積・集約化の旗振りに懸命だ。スマート農業技術はまずは営農上の負担軽減に有効としており、高齢者対策をも含めて、スマート農業技術は実質、最大の担い手対策として位置づけられている感もある。手作業に馴染んできた高齢者にとって体力低下は避けられず、機械力でカバーするしかないのも確かである。筆者も週末は10aほどの畑で作業をしており、30年以上も鎌を使っての草刈りにこだわっていたが、このところの温暖化も加わって、刈払機をとうとう購入して酷暑をしのいでいるのが実情だ。
スマート農業技術よりも機械化と言うほうが適切かもしれないが、思い浮かぶのがスウェーデンのウプサラにある農業試験場だ。10年ちょっと前の話であるが、長らく新聞社に勤めていたウプサラに住む友人が、定年後、農業試験場に勤め始めたことから、案内してくれたものだ。彼の仕事は、農家が持ってきた土壌を分析し、不足成分等を判定して、必要な肥料についてのアドバイスだ。ここでの主要なサービスについて聞いてみると、航空写真と農家が持ってきた農産物の生育状況を見て、耕起から種まき、収穫まで、いつどのような作業をするかの指示がメインで、ほとんどの農家はこれに従って農作業を行っているという。言ってみれば農作業は機械が行い、観察や判断は農業試験場が受け持ち、農家がやるのはもっぱら機械のオペレーション。こんな農業はおもしろくない、というのがその時の感想であるが、デジタル化の進展は、これをどう変えていくのだろうか。
そんなことを考えている時に届いたのが『日本農史研究』(農文協)なる徳永光俊著の上下二冊本で、上は「『生きもの循環』と農法」、下が「『創発する風土』と農学」である。ここでは、日本で培われてきた「農法」は、欧米の工業生産をモデルとして作り上げられてきた「農業技術」とは異なり、「お天道様の下で、大地の上で、農業者は農耕を行う『天・地・人』の関わり」であり、現場の農業者と研究者が「相互に交流しながら、相補的に進んできた」ものであるとする。そしてこれら「農法」は「生きもの循環」を基本原理としており、これは「日本列島で代々伝えられてきた『おかげさま・おたがいさま』『いただきます・ごちそうさま』という日常的な和語の世界」であるとする。まさに「農法」は、自然の摂理に沿いながら、霊感ともいうべき感性と研ぎ澄まされた身体感覚をもっての農の営みの中から育まれてきたものであるように受け止めた。こうした「農法」が今、忘れ去られようとしてはいながらも、一部、自然農法や有機農業等に凝縮されて現在に引き継がれており、「農法」はまさに〝日本の財産〟であると言っても過言ではない。
これからの日本農業の担い手は、デジタル技術やデータを駆使しながら大型機械をオペレーションする大規模農家と、小農や移住者等による自給的な小規模農家に分化していくのであろうか。少数ながら生産シェアの大宗を占める大規模農家と、自然農法や有機農業等の伝統農法にこだわるたくさんの自給的農家とが棲み分けしながら、あらたな集落が形成される姿を想像すると、案外と面白いようにも思う。関係人口の創出が大課題となる。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2025年10月5日号掲載