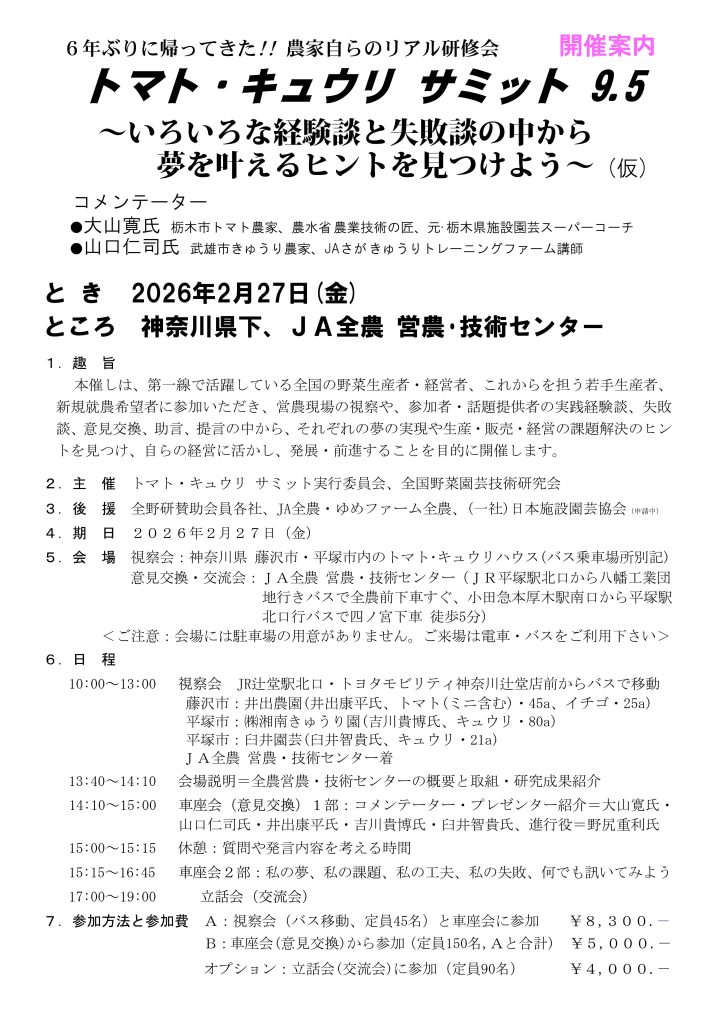子ども食堂は2012年に東京都大田区でオープンした「だんだん」が第1号とされる。数年後にはメディアで取り上げられ、注目を浴びるようになった。その後は右肩上がりに増え続け、今では中学校の数より多い全国1万ヵ所以上にあるという。
21年に豊島区の「要町あさやけ子ども食堂」を訪問した。コロナ禍で食事の提供は自粛していたが、企業などから提供を受けた食品を母子らに手渡ししていた。主催者の男性は仕事を引退し、伴侶にも先立たれて孤独を感じていたが、その伴侶の友人たちの協力で子ども食堂を開き「自分自身が救われた」と話していたのが印象的だった。
同じ年に「農政ジャーナリストの会」は食の格差をめぐる研究会(4回シリーズ)を開いた。講師の一人は子ども食堂の開設や運営をサポートする認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの湯浅誠理事長(当時)だった。湯浅氏は、子ども食堂の意義は貧困対策にとどまらず「無縁社会の中につながりをつくる」ことだと強調した。
一方、同じシリーズの研究会で「子どもの貧困」研究の第一人者である阿部彩・東京都立大教授は、その限界を指摘した。市民の自発的な活動である子ども食堂は有意義な取り組みではあるが、問題を抱えるすべての当事者を包摂することはできない。根本的な解決は、やはり給食無償化など公的な次元で図られるべきだと主張した。
そんな議論を思い出したのは、今月13日付の朝日新聞に掲載された「だんだん」店主、近藤博子さんのインタビューを読んだからだ。近藤さんは「こども食堂」の名前を今年4月以降、使っていないという。食事の提供は続けているが、貧困や社会的孤立などの問題が改善されないまま、子ども食堂に解決を求めるような風潮に怒りを覚えたからだそうだ。「大事なのは子ども食堂という『活動』ではないですよね」という言葉が痛切だ。
給食無償化は来年度予算の概算要求に(金額を明示しない)「事項要求」として盛り込まれた。一歩前進だが、小さな一歩でしかない。子ども食堂の13年を振り返り、この社会のあり方を根本から考える必要がある。
(農中総研・客員研究員/飯舘村地域おこし協力隊)
日本農民新聞 2025年9月25日号掲載