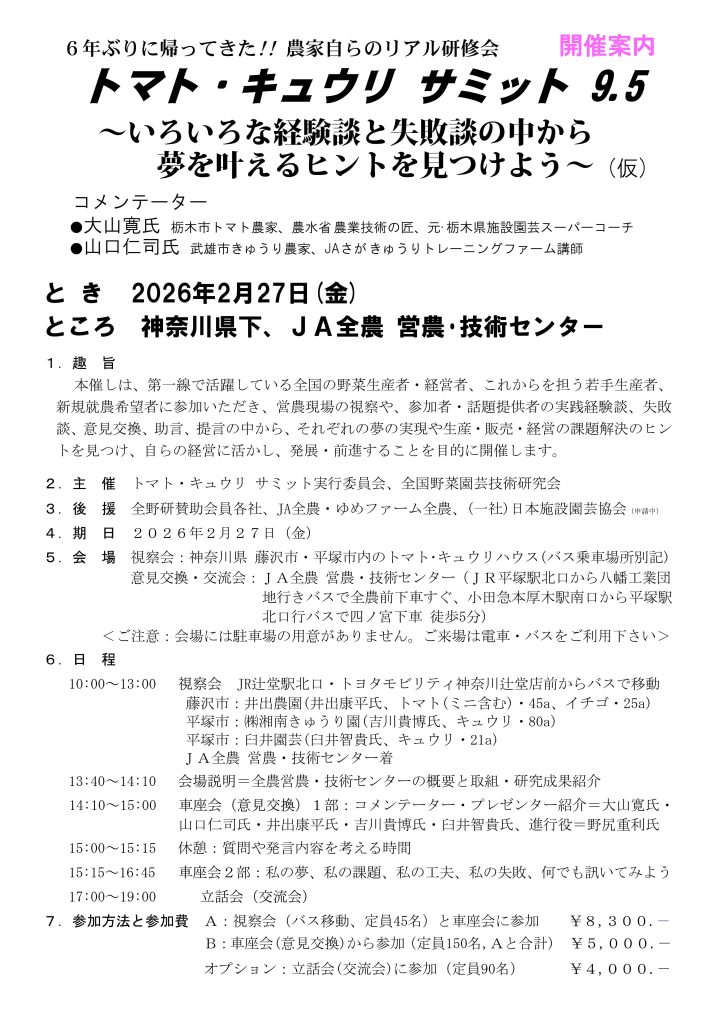20日に投開票された参院選では「令和の米騒動」を受けて米政策が主要な争点になった。各党の主張はさまざまだが「減反(生産調整)をやめて主食用米を増産」という点はほぼ一致していた。
昨年からの経緯を振り返れば、当初は農水省が「生産量は十分だったが、流通が目詰まりを起こした」と説明。しかし、新米が出回る秋になっても高値が続いたため「流通の問題ではなく、生産が足りない。長く続いた減反政策が原因だ」という見方が広がった。
本当だろうか。長い目で見れば、減反政策にもかかわらず米価は下がり続けてきた。米生産者の高齢化と減少(後継者不足)による生産基盤の弱体化も、昨日今日始まったことではない。その長期的な問題と目先の米価高騰を直ちに結び付けていいのか。
先日、NHKラジオの番組で物価研究の第一人者、渡辺努・東大名誉教授がこんなことを話していた。「値上がりの原因が供給減少なのか需要増加なのかを見極めるには、取引量を見ればいい。今回の米価高騰は取引量が増えているから、需要側に要因がある」
確かに、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構(米穀機構)が公表する1人あたり精米消費量(月別)は昨年度、ほぼ一貫して前年同月を上回った。減ったのは最後の今年3月だけだ。高値で購入意欲が減退したか、家庭の米びつが満杯になったのだろう。
高騰の直接的原因は、やはり南海トラフ巨大地震情報を受けた買い急ぎやインバウンド消費の急増など需要側にあったのではないか。一部には値上がりを見込んだ流通業者の「思惑買い」もあっただろう。もっと多角的な分析が必要だ。
需要も長期的には毎年10万㌧のペースで減り続けてきた。安易に増産すれば、今度は暴落するかも知れない。「余ったら輸出すればいい」という人もいるが、どこが買ってくれるのか。主食用米に急旋回したら飼料用米や加工用米、酒米、国産小麦などの需要者は困るだろう。もっと冷静に、総合的に考えた方がいい。
(農中総研・客員研究員/飯舘村地域おこし協力隊)
日本農民新聞 2025年7月25日号掲載