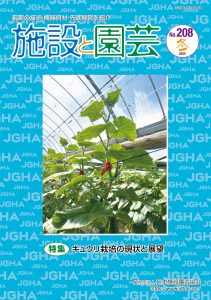気になる言葉の一つに「生産性」がある。たとえば「賃上げの前提は生産性向上」「(関税や補助金による)日本の農業保護水準が高いのは農業の生産性が低いから」などと言われる。労働生産性と土地生産性を区別する必要があるが、少なくとも前者について日本農業の生産性が低いと思っている人は多いだろう。
筆者もそうだったが、今月10日に開かれた農政ジャーナリストの会総会の記念講演で古屋星斗リクルートワークス研究所主任研究員の話を聞き、考えを改めた。全体の趣旨は少子高齢化による働き手不足に警鐘を鳴らすものだったが、その中で「農林水産業の時間あたり労働生産性は1994~2023年に71%上昇し、これは製造業に次ぐ伸び率」と古屋氏は指摘した。
確かに基幹的農業従事者(農業を主な仕事とする人)は95年からの30年間で半減したが、多くの作物で生産水準はそこまで落ち込んでいない。留保を加えるなら、労働生産性の分子は付加価値(生産額-生産費)であって生産量ではないし、分母の労働量(働き手の数×労働時間)も基幹的従事者以外の家族労働やパートがあるから厳密な計算は難しい。ただ、農業者が生産性向上を怠ってきたわけではなく、むしろ懸命に生産を維持してきた努力は評価されていい。
古屋氏の話を聞き、少し前に読んだ「日本経済の死角」という本を思い出した。著書はBNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏。日本人の労働生産性は過去30年間かなりのペースで上がってきたのに実質賃金が低迷を続けているのは、企業が利益を賃上げや設備投資に回さず内部留保としてため込んできたからだと論じている。つまり「賃上げの前提は生産性向上」ではなく「生産性が上がっても賃金を上げない」ことに問題がある、というわけだ。
直ちに結びつけるのは早計かも知れないが、二つの話には「現場で汗をかく人が報われない」という共通の構図がある。あらゆる分野の担い手が減る中、生産性向上は必要だ。しかし、正当な報酬が支払われなければ、担い手はますますいなくなってしまう。社会全体の課題として考えるべきだろう。
(農中総研・客員研究員/飯舘村地域おこし協力隊)
日本農民新聞 2025年6月25日号掲載