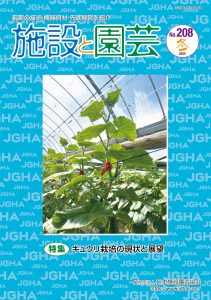〈本号の主な内容〉
■アングル
JA厚生事業とJA全厚連の事業のこれから
全国厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 歸山好尚 氏
■令和7年度 農業倉庫保管管理強化月間
農業倉庫基金/JAグループ/JA全農
「保管米麦の品質保全とカビ防止・防虫・防鼠」「保管米麦の水害事故の防止」「自主的衛生管理の実行」を重点に
■JAグループ版スマートシティ(スマートアグリコミュニティ)を実証中=JA全農
 アングル
アングル
JA厚生事業とJA全厚連の事業のこれから
全国厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長
歸山好尚 氏
JA全厚連は3月5日に開催した臨時総会で、令和7年度から9年度までの第11次3カ年計画と、令和7年度事業計画を決定した。これからのJA厚生事業のあり方と展開方向、取組みのポイントを歸山好尚理事長に聞いた。
診療報酬改定も減益
■令和6年度はJA厚生事業にとってどのような年だったか?
昨年7月、私が理事長に就任したときは、1月1日に発生した令和6年能登半島地震の被災地に、各厚生連の災害派遣医療チーム(DMAT)を迅速に派遣したことが評価され、農林水産大臣から各厚生連に対して感謝状が贈呈されたタイミングと重なり、改めて各厚生連病院の新年早々の尽力に敬意を払うとともにその使命感の強さを再認識する機会となった。
今は、コロナ禍で医療機関がこれまでにないほどの機能発揮を求められた大変な時期に、補助金の交付を受けながら病院経営を繋いできた時期とは少し様子が違ってきている。
どこかの国で新しい感染症が流行れば、あっという間に世界中に広がるパンデミックの恐れはなくなっていないが、コロナ禍が落ちついた今、その危機意識が少し薄れつつある。
私達に日常生活が戻ってくる中、昨年6月に厚生労働省により診療報酬が改定された。しかし、その改定内容は医療機関をとりまく今の環境までを充分見通せておらず、結果として厚生連病院のみならず、多くの病院が危機的状況に陥っている。
コロナ前の水準までとはいかないが、患者が病院に戻ってきているものの、物価は広範に上昇しており、費用が大きく増えてしまっている。診療報酬が抑えられている中では、診療は増えても費用増加がそれを上回るため、増収減益となってしまっている。
昨年10月から自民党の「農民の健康を創る会」の議員の皆様に医療機関の窮状を訴えていく中で、12月には厚生労働省の補正予算が組まれるに至ったものの、もともとの診療報酬の見直しが必要なことに変わりはない。
病院経営をしている厚生連のうち8割以上が当期利益で赤字であり、黒字を見込んでいる厚生連は14%ほどである。
診療報酬の改定は2年に1回と定められ、次の改定は来年になる。それまで病院経営が保てるか否かの問題になるのではと、とても心配している。
地域病院の役割分担の動き進む
■全国の医療現場の状況は?
現在の日本では、年間出生数が72万人というニュースにもあったように人口減少が進みつつある。特に厚生連が置かれている地域、農村の人口減少は著しく、患者数が下降線を辿っていく中で地域医療を維持していくことが大きな課題となっている。
厚生労働省は、人口減少に対し公立病院、公的病院を含めて関係者が地方自治体と協議して、それぞれの病院が担う役割を分担していくことを地域医療構想として推し進めている。地域の病院がきちんと維持できるように支援しながら、共生を保っていく方針だ。
具体的には自治体も関わりながら、地域の中で病床を減らしつつ病院ごとに急性期、慢性期等と役割を担いながら専門化していくことで、上手く経営を続けられないかを模索しているのが現状だ。実際こういった動きは活発化しており、厚生連病院は主に地域の基幹病院として検討を進めている。各厚生連や病院が経営に苦労している中で、全厚連が取組むべきことは、各厚生連の置かれている地域の実情をしっかりと政府、行政に訴えていくことはもちろん、他の医療団体とともに行政に働きかけて実情に即した制度改定をし、診療報酬も変えていくことである。
地域医療を守るための業務効率化を支援
■中長期を見通した取組方向は?
人口減少に伴う患者数や受診者の減少、医師・医療従事者・スタッフの不足に加え、医療現場での働き方改革への対応や物価高騰など、厳しい経営環境におかれている厚生連が、地域において必要な保健・医療、高齢者福祉サービスを提供できるように、引き続き支援を行っていく。
地域医療の存続には、地域のニーズに応じた効率的で質の高い医療供給体制を確保する必要があり、特にすでに述べた地域医療構想を基にした病院機能の分化と連携、病院の再編・統合がポイントとなる。今後も厚生連病院が地域医療の要として存続できるように、政府が進めるICTやAI等の活用についても、新規の取組みや優良事例の共有により業務を効率化していくのを支援していく。また、システム導入費用や改修費用の削減についての支援も行う。
事業・経営支援、制度対応支援を強化
■重点的取組みの柱は?
繰り返しになるところも多いが、重点的に取組む事項は「事業・経営支援」「制度対応支援」「制度改正要望」「人材育成」の4つある。まずは、厚生連に対する早期支援をはじめとする「事業・経営支援」に最優先で取組んでいく。また、「制度改正要望」もわれわれの役割として重要だ。
「事業・経営支援」では、厚生連の経営改善に向けた施策の提案などに取組む。特に赤字を余儀なくされている厚生連へは、これまでの知見をもとに改善に向けて協力し、提案できるところはしっかりと提案していくつもりだ。
「制度対応支援」では、法人税非課税措置に係る要件管理の徹底を図っていく。
また、特別交付税交付金の対象となる厚生連へは、他の厚生連が行っている市・県との協議の状況に関する情報提供などに取組んでいく。
「制度改正要望」では、自民党議員連盟「農民の健康を創る会」を通じて、政府等に対する要請活動を展開する。日本赤十字社や恩賜財団済生会と連携し、医師偏在の解消、診療報酬の改定などの要請活動を実施していく。
「人材育成」では、業務の基礎となる研修受講や資格取得を励行する。ジョブローテーションや各部署のOJTのほか、会員厚生連との人事交流を通じ、本会職員の育成を図るとともに、厚生連からの受入出向や厚生連職員の教育研修を実施する。
また、厚生連の経営幹部及び将来の経営幹部を対象とする研修を引き続き企画・実施することにより、各厚生連職員の資質向上に資する。
政府への要請活動と併せ、デジタル化支援等を推し進める
■このなかでも目出しとなるような実施事項は?
昨年10月から、「農民の健康を創る会」を通じて、補助金獲得の要請活動を展開し12月に補正予算が組まれた。まずはその中で我々が獲得できるものについてその利用漏れがないように取組んでいく。具体的には、生産性向上に資する設備導入等の取組みを進める医療機関等に「生産性向上・職場環境整備等事業」補助があり、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関を対象に「病床数適正化支援事業」補助がある。今後、補助の詳細情報や申請期限等について公表される予定であり、迅速な情報提供により補助金を最大限活用できるよう支援していく。
一方で、厚生連事業を理解してもらう手段として、ホームページだけでなくPR動画をアップするなど、多様な情報発信にも取組んでいきたい。
病院経営のデジタル化も、全厚連で得た情報を共有し、その評価を病院側と一緒に考えていければと考えている。また厚生連ごとの優良事例を上手く共用化し、活用できればと考えている。またそれぞれの厚生連、あるいは病院ごとにコストダウンのために収集している情報について、この厳しい環境の中で協同組合であることのメリットを生かしてその機能をきちんと発揮できるよう、情報共有の仕組みづくりを始められないか考えている。
改定年度ではないものの、診療報酬の改定に、より一層力を入れて進めていくことはもちろんだが、加えて次回の税制改正要望として、他の医療法人に室料差額平均5千円の制限がないことをふまえて、この制限の見直しを要望していく。昨今、個室志向が強い傾向にあり、個室を安価で提供することは厚生連の使命としてもちろんのことだが、個室のグレードに見合った相応の報酬が得られる形でニーズに沿った医療サービスを提供していきたい。
診療報酬の見直し等の病院にとって共通の課題は他団体と連携することによって効果が上がる。これまでも日本赤十字社、恩賜財団済生会、JA厚生連の公的病院3団体は、連携して補助金獲得運動を展開するとともに情報交換もできている。「農民の健康を創る会」を通じての要望について他団体から高い評価を得ており、良好な関係を保っている。
また昨年度は、日本病院会や全日本病院協会、日本医療法人協会等も含めて、緊急的な財政支援措置を求める「緊急要望」を国に提出したところでもある。
経営の健全化で自立経営めざす
■JAグループの一員としての位置付けは?
高齢化が進む社会で、なくてはならないのが医療。どの厚生連施設もJAと同じく地域になくてはならない存在だ。だからこそ、健全な経営を続けていくため、どのようにコストダウンしていくかが重要になってきている。
経営を健全に保つことでJAに迷惑や心配をかけないことが基本だ。地域の医療を守ることは我々の使命であって、そのために厳しい中でもきちんと自立した経営ができるようにしていかなければならない。
病気を未然に防ぐために地域の方々の健康管理を進めることはもちろん、病気になったときに近くに厚生連病院があってよかったと思ってもらえることが大切。そのために地域と強く結びついているJAを基盤としていることに大きな意味があると思う。
「健康」であることは「持続可能な農業の実現」を実践する第一歩となる。JAグループの一員として、豊かで暮らしやすい地域共生社会の実現に貢献するため、厚生連が地域に必要な保健・医療・高齢者福祉サービスを高い水準で提供できるよう事業を進める。