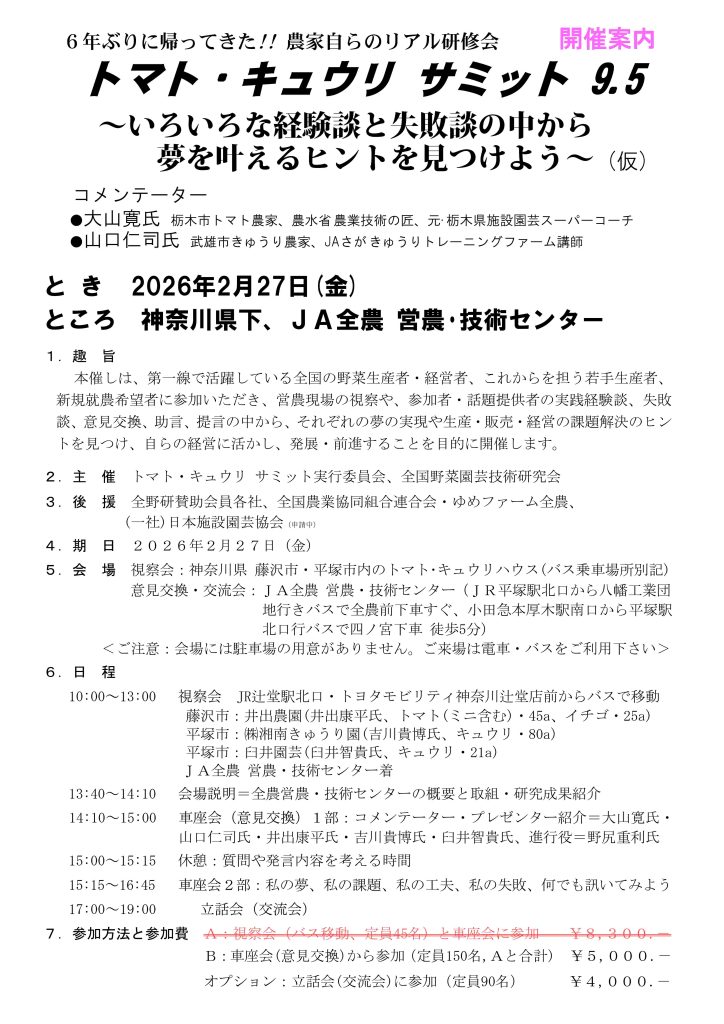昨年夏の令和のコメ騒動が発生して以降、米を巡る情勢はめまぐるしい。米価の高騰が続いているが、備蓄の放出がこの3月に行われ、今後の価格動向が注目される。令和のコメ騒動にともない、生産量と集荷量からして17万トンの米の在庫がどこかにあるはずだとして米流通ルートの変化や複線化がすすんでいるのではないかも話題になっている。そしてミニマムアクセス米とは別枠で関税を払って外国産米を輸入する動きが見られるとともに、一方では米の増産が必要であるとして2018年に廃止したはずの減反が実質継続されていることからこれを止めて、作付けを自由化して増産をはかり米の輸出増大を促進し、国内消費に不足が発生した時は輸出から国内消費にシフトさせればいいとの主張も飛び交うなど、米をめぐる動きはまさに混乱・錯綜した状態にある。
こうした動向・情勢も踏まえて食料・農業・農村基本計画の策定に絡めながら27年度からの水田政策の見直しがすすめられている。今回の米を巡る一連の議論は、そもそも食料・農業・農村基本法の改正にともない最優先で議論されてしかるべき一丁目一番地の大課題だった。基本法改正の最大の眼目は食料安全保障に置かれ、農地の減少、担い手の不足が加速度をつけて進行しつつある中、まさに日本の米、水田稲作をどうしていくのか、これにともない備蓄、輸入、輸出、さらには減反をどうしていくのか、これに踏み込んだ検討を行ったうえで20余年ぶりに基本法の改正をはかるところにこそ、その歴史的意義はあった。ところがこうした議論を回避して改正基本法を成立させ、その後の令和のコメ騒動で脆弱化した米生産基盤が明るみに晒されるに至って、後追いでの議論となった。
そもそも情勢認識が甘いと言わざるを得ないが、27年度からの水田政策の見直し検討がすすめられた結果として、3月25日、衆参両院の農林水産委員会は基本計画に関する決議を与野党の全会一致で採択した。そのポイントは〈水田政策の見直し(飼料用米など意欲を損なわない制度を設計、納税者の理解を図りつつ直接支払制度を設計、多面的機能を念頭に水田面積を維持等)〉〈中山間地域等直接支払い交付金の支援拡大〉〈米輸出2030年に35万tの目標達成へ、国際競争力の高い産地の育成〉〈食料の価格形成で実効性ある仕組みを構築〉〈食料自給率向上へ農地集積、多様な農業者の取り組み促進〉〈日本型直接支払制度の在り方を検討〉〈既存予算の他に別枠予算を措置〉等となっており、一部異論はありながらも高く評価したい。
与党・野党の立場を超えて今後の検討の方向性を打ち出したことは画期的であるといっていいが、それだけに今、米をはじめとする日本農業の危機が顕在化し始めたことからすれば、党派党略を超えての議論展開がもう数年早かったらと思わずにはいられない。米をめぐる情勢は錯綜しているが、2070年には日本の人口が9000万人を割り込む予測や、各国の食料主権の尊重も勘案した食料安全保障を土台にしての長期政策を明確化すると同時に、短中期では段階的かつ柔軟な米政策を展開していくことが求められている。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2025年4月5日号掲載