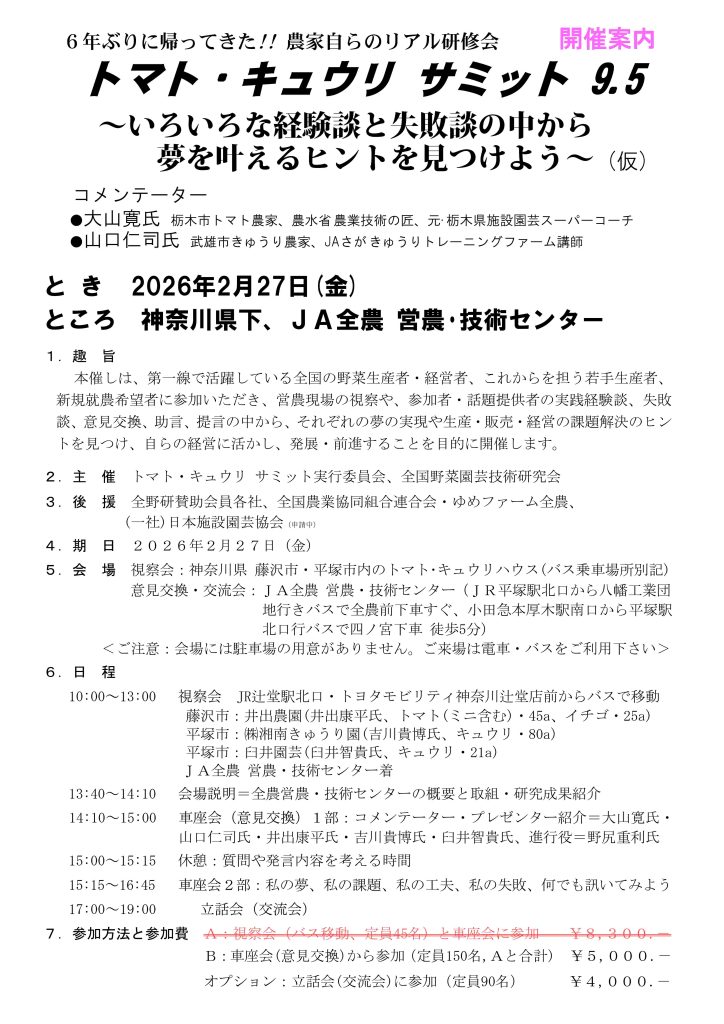3月30日に東京の青山公園に集合しての「令和の百姓一揆」開催が予定されているが、これに先立って2月18日に衆議院第二会館で院内集会が開かれた。ヨーロッパではトラクターを引っ張り出してのデモ行進は珍しくはないが、日本ではめったない〝歴史的挙行〟でもあり、そのキックオフとなる集会に足を運んでみた。会場参加の定員は確か50名か60名であったと思うが、開始15分前に会場に入ったところ、すでに満杯で、かろうじて一つだけ空席を見つけて座ることができたが、大変な混雑と熱気に驚かされた。実行委員会事務局の発表では会場参加が120名、オンライン参加は150名。さらに32名もの国会議員に代理での秘書の参加が7名と異例の大集会となった。
「安全でおいしい国産の農産物をつくるために日々土を耕し、家畜を養い、自然と向き合い、農業を営」んでいる日本の農家は、「農業生産を通じて地域の環境を守り、生態系を維持することにも努めて」きた。しかし 日本農業は「異常気象による災害、担い手不足、農業経営の赤字などにより農家人口は年々減少し、食料自給率も73%(昭和40年)から38%(令和5年)と低迷して」いるのが現状であり、「タネの海外依存度を考慮した実質食料自給率は2035年に11%になるといわれて」いる。そうした中、「かろうじて農家も『自給10円』程度で頑張ってきましたが、この窮状を多くの方に知っていただき、生産者と消費者の声を農政に届けて行」くことをねらいに行われるもので、「農家に欧米並みの所得補償を! 市民が安心して食を手にできる生活を!」をスローガンとする。20年ぶり以上で食料・農業・農村基本法の改正が行われたものの、大規模化、生産性向上に偏重し、小農・家族農業を軽視する農政のスタンスに変化は乏しく、もはやこのままでは日本農業は崩壊しかねない、今が日本農業の維持をはかるためのラストチャンスであるとして、「物言わぬ百姓たち」が立ち上がったものである。
この院内集会では、各地域より農業生産者からの状況報告が行われたが、水田稲作の生産者は「農家を切り捨てて日本は豊かになったのか?」「あと5年、10年で水田稲作は崩壊だ」「今、米価上昇で少しほっとしているが、経営が楽になったわけではまったくない」と切々と訴えた。そして酪農家からの「赤字で金を払って搾っている」「補助金はもらったが、次の月にはなくなる。首の皮一枚でつながっている」「この3年間で100万円ももうかっていない。まさに奴隷で、自尊心を傷つけられている」との悲痛な叫びには胸をえぐられるような思いであった。
昨年5月に改正基本法が成立した後「令和のコメ騒動」が発生。10月の衆議院選挙では与野党が逆転。新米が出回ればコメ不足は解消するとの観測も強かったものの、需給はひっ迫して米価はさらに上昇。ついに今年に入って政府は備蓄米の放出を決断。さらに米の輸入増加の一方で、減反廃止とあわせて輸出拡大を政府は目論む。農政転換は政権交代なくして困難であることは明らかだ。山場となる7月の参院選挙に向けて奮闘が期待される。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2025年3月5日号掲載