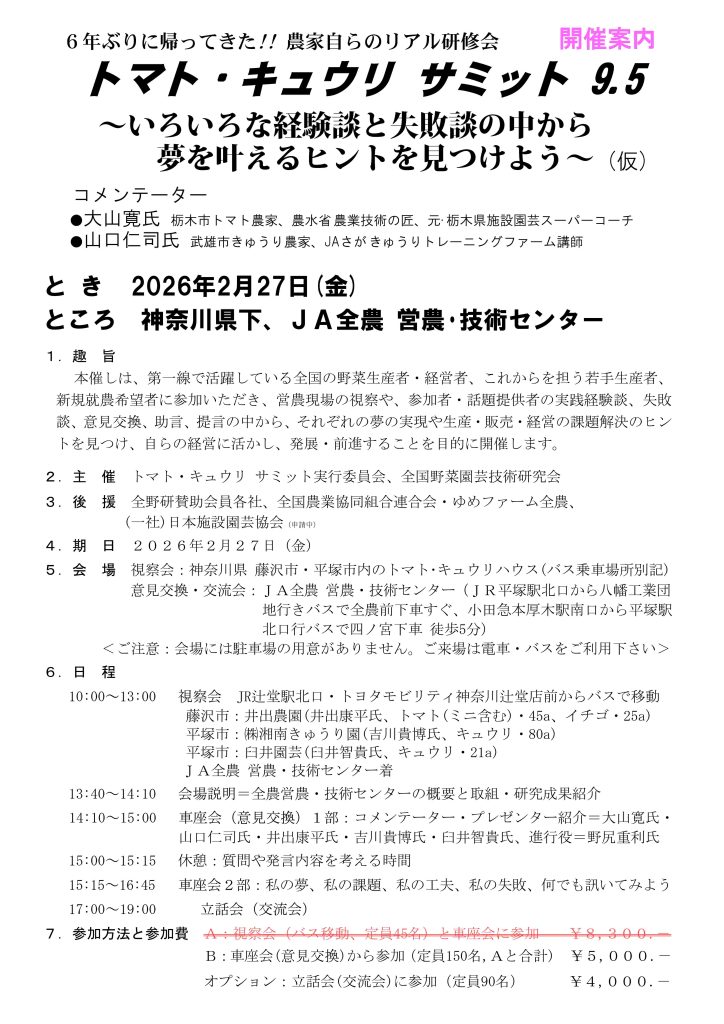1988年の初夏、福島県南部で肉用牛を育てる年配の男性を訪ねた。畜産現場の取材は初めてだった。きっかけは同年6月に妥結した日米農産物交渉だ。焦点の牛肉とオレンジについて日本は3年後の輸入割当(数量制限)撤廃と関税率の段階的引き下げなどを約束した。将来への不安を語る男性の沈んだ表情が脳裏に焼き付いている。
その後も貿易自由化は進んだ。ウルグアイラウンド合意(95年発効)、環太平洋パートナーシップ協定(TPP。2018年に発効したが米国は離脱)、他にもさまざまな国・地域との経済連携協定(EPA)などで日本農業は国際競争にさらされた。
その度に賛否両論が渦巻いたが、自由化推進論者は市場開放のメリットを強調した。安い輸入農産物は消費者と食品産業に恩恵をもたらす。生産者にとってはコスト削減や品質向上を進め「強い農業」を実現する好機–そういった主張だ。
「自由化は怖くない」という論拠にされたのが、牛肉とかんきつ類だった。いずれも業務用など低価格帯の市場は輸入に任せ、国産は品質向上に努め高級品にシフトすることで生き残った。要は「違う土俵で勝負すればいい」という理屈である。
数年前までは、それも一定の説得力があった。しかし、今は異常気象などによる海外の生産減少、新興国の消費拡大、円安などで輸入品の価格が高騰している。牛丼チェーンや焼き肉店が使う牛バラ肉は今年に入って国内産と米国産の卸値が逆転した。オレンジ果汁は主な輸入先のブラジルが自然災害や病害に見舞われ、原料の調達難に陥った飲料メーカーはジュースの値上げや販売休止を余儀なくされている。
愛媛県の定番商品「ポンジュース」のパッケージは4月に「オレンジみかんジュース」から「みかんオレンジジュース」に変わった。国産果汁の割合が増えたからだが、国内のミカン農家は高齢化などで減り続けており、供給力には限界がある。畜産経営も飼料代の高騰などで厳しく、一方ではコスト増から閉店に追い込まれる焼肉店が増えている。「国産回帰」を手放しで喜べない36年後の現実をどう見るか。あの時の畜産農家にもう一度、聞いてみたい気がする。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2024年7月25日号掲載