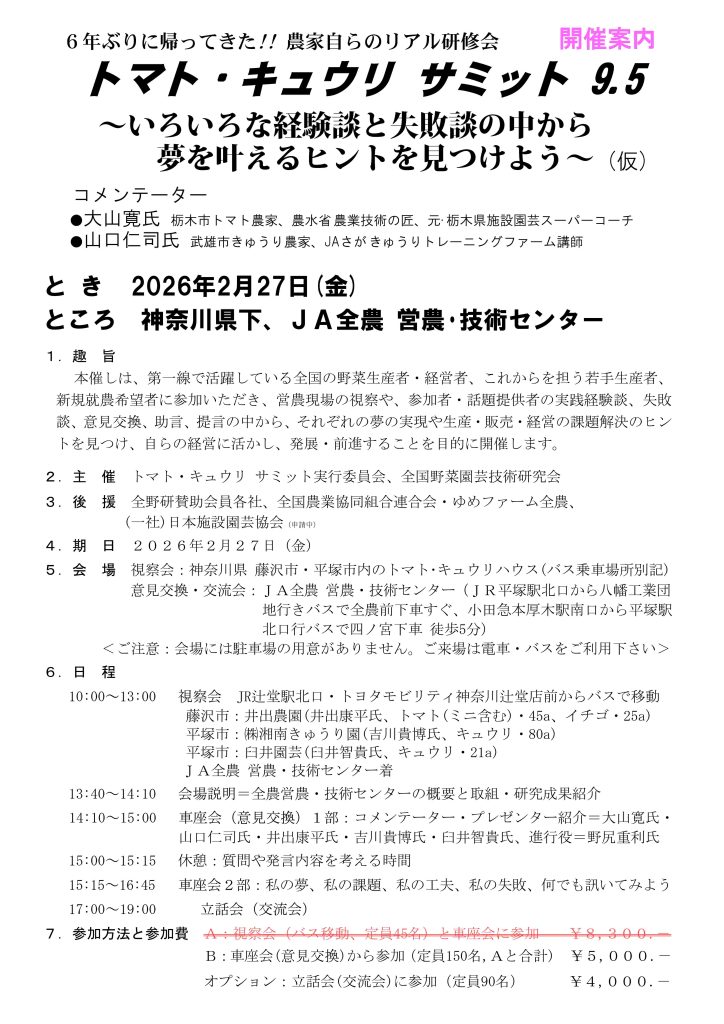世界農業遺産に登録される石川県輪島市の白米千枚田。日本海へ向かって広がる棚田の景色は息を飲む美しさだが、元日の能登半島地震で無残に壊れた。無数の亀裂が走り、水を張ることもできない。棚田の多くは高齢の農業者たちが支えている。地元の力だけで再生・維持するのは厳しそうだ。
2日付の日本農業新聞によると、能登半島全体で米の作付けが困難な水田は1000haに上る。東日本大震災でもそうだったように、災害をきっかけに離農する人が多いだろう。
東北の被災地では、農地復旧と併せて水田の大区画化や水利施設の改良が進められた。いわゆる「創造的復興」を目指す施策だが、少数の担い手で大きな面積をカバーするには必要だった。実際、一部の農業者が法人組織を結成し農地の受け皿になった。だが、平地が少なく高齢化もより進んでいる能登半島では、それすら難しく思えてしまう。
農業者の減少を見越して(あるいは奇貨として)農地を集約し、スマート農業などで省力化を進める手法は「諸刃の剣」にもなりうる。それによって産業としての農業は維持できても、結果的に人口減少やコミュニティーの衰退に拍車をかけてしまう面があるからだ。
福島第1原発事故で6年間の全村避難を強いられた福島県飯舘村は、帰還する高齢者が営む自給的な「生きがい農業」を支援する村独自の制度を設けた。国の農政には無視される小さな農業も、地域社会を維持する意義は小さくない。余った作物は直売所で売られたり地域内外の親族や知人に贈られたりして、人と人とをつなぐ。高齢者をサポートする家族や隣人、移住者がかかわって本格的な農業経営へステップアップする可能性もある。小規模自治体ならではの慧眼だと思う。
能登の農業再生も産業の視点だけでなく、複眼的に進めてほしい。棚田の1枚1枚に映える「田ごとの月」のように、一人一人に光を当てる「人間の復興」が重要だ。以前のような地域には戻せなくても、多様な人々が根を下ろし暮らしと生業を丁寧に営むことが結果的に未来への展望をひらくだろう。東北の被災地を見つめてきた経験から、そう確信する。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2024年2月25日号掲載