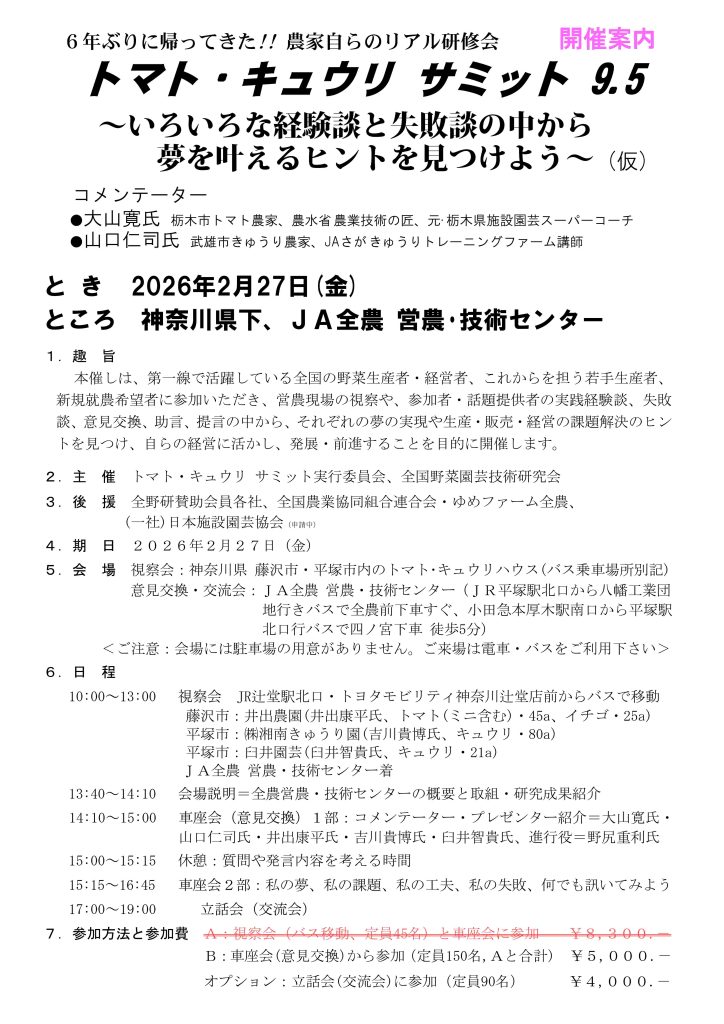一人暮らしをしていた母が入院したため、4月上旬から1カ月ほど里帰りした。故郷を離れて44年。こんなに長く実家で過ごしたのは初めてだが、地域の変容ぶりを実感した。かつて買い物をした近所の商店はすべて廃業しており、食料品や日用品は少し離れたスーパーやドラッグストアで買うしかない。比較的近くにコンビニがあるのが救いだった。
長い距離を歩けない母は、生協の宅配サービスを利用していた。実家の冷蔵庫をのぞくと、冷凍食品やレトルト食品がたくさんあった。揚げ物など高カロリーの食品が多い。それを90歳の母が一人で食べている姿を想像すると、胸が痛んだ。
街を走る宅配トラックを頻繁に見た。人口減少と高齢化、単身世帯の増加、商店街の衰退などで個別配送のニーズは増えている。冷凍などの調理済み食品も同じだ。「食文化の破壊」や「食の工業化」を嘆いてきたが、母のような高齢者がそれらに支えられている現実を否定できない。
最近、新聞などで「2024年問題」という言葉をよく見る。トラック運転手の過酷な就労実態を改善するため、時間外労働の上限を年間960時間とする規制が来年4月に発効するからだ。野村総研が今年1月に発表した試算によると、元々の人手不足にこの規制が加わることで、25年に28%、30年には35%の商品が全国で運べなくなるという。大都市圏より地方に影響が大きいとも指摘される。
ドライバー不足のもう一つの背景は、ネット通販などEコマース(電子商取引)の広がりだ。スマホやパソコンでクリックすれば買い物ができるのは便利だが、その便利さが商店街を「シャッター通り」に変え、地域の衰退に拍車をかけた。そして、買い物難民になった高齢者が頼るのも同じ宅配だ。その皮肉な構図の中でトラック運転手たちが疲弊していく。
人が老いるように、街も、社会も老いていく。老いは必ずしも喪失ではなく、成熟によって得られるものもあるはずだ。だが、この数十年に我々は何を得たのか。故郷を捨てた自分にも責任はあるのだろう。空き地と空き店舗が並ぶ、かつての繁華街を眺め自問した。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2023年5月25日号掲載