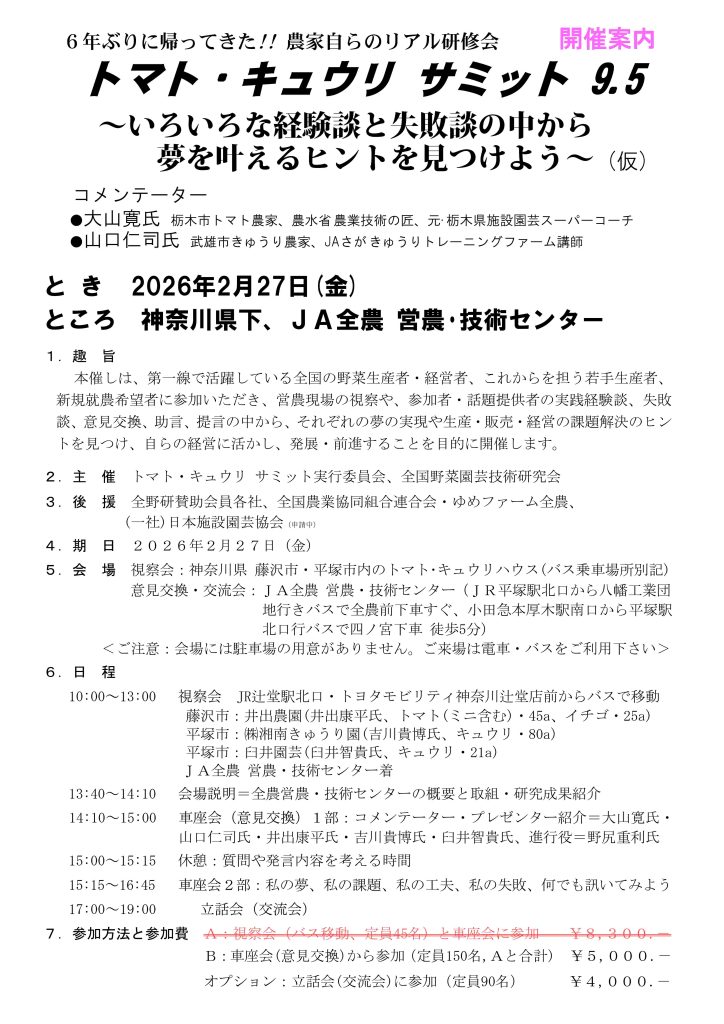トーストやサンドイッチにする四角いパンは英国発祥。固焼きで棒状のバゲットや三日月型のクロワッサンはフランス生まれ。前者が日本で「食パン」として定着したのは、明治政府と英国との親密な関係が背景だという説がある。
また、第2次世界大戦後は米国から援助物資として大量の小麦が供与され、学校給食はパン食が基本になった。給食の「コッペパン」は日本独自の名称だが、米国式のパンが原型らしい。
食の欧米化が小麦の消費を拡大させた。農林水産省の統計によると、1965年度の国民1人あたり年間供給量は米112kg、小麦29kg。昨年度は米52kg、小麦32kgだった。米は半減し小麦は横ばいだ。生活様式や家族形態の変化で外食や中食が増え、家でご飯を炊く機会が少なくなったことも要因だろう。
家庭の購入金額では既にパンが「主食」である。総務省の家計調査で2人以上世帯の月次データを2000年までさかのぼると、最初にパンが米を上回ったのは03年1月。2010年代にはそれが定着し、直近は19年11月~今年7月の33カ月連続でパンの方が多い。コロナ禍による「内食回帰」で20、21年は差が縮まったが、今年に入って再び1000円以上に開いた。行動制限の緩和で外食・中食が再び増えたことに加え、価格要因、つまり米価下落と小麦の値上がりも大きいとみられる。
この状況、考えようによっては米の消費を拡大する好機だ。国産小麦の生産振興の追い風にもなり、食料自給率向上につながる。「禍を転じて福となす」発想があっていい。
だが、政府は10月以降の輸入小麦の政府売り渡し価格を据え置く。輸入価格の実勢を反映させれば2割程度の値上がりになるところを、食料安定供給特別会計のやり繰りで吸収するそうだ。物価高に悩む消費者、特に低所得層に配慮した緊急避難的措置は必要だが、生活困窮者を支える政策手段は他にもあるはずだ。本当にこの選択肢しかないのか。
かつて、同特別会計の前身である食糧管理特別会計(食管会計)は国産米を高く買って安く売り、膨大な累積赤字を積み上げて批判を浴びた。似たようなことを輸入小麦で行うことに、割り切れない感想を抱くのは筆者だけだろうか。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2022年9月25日号掲載