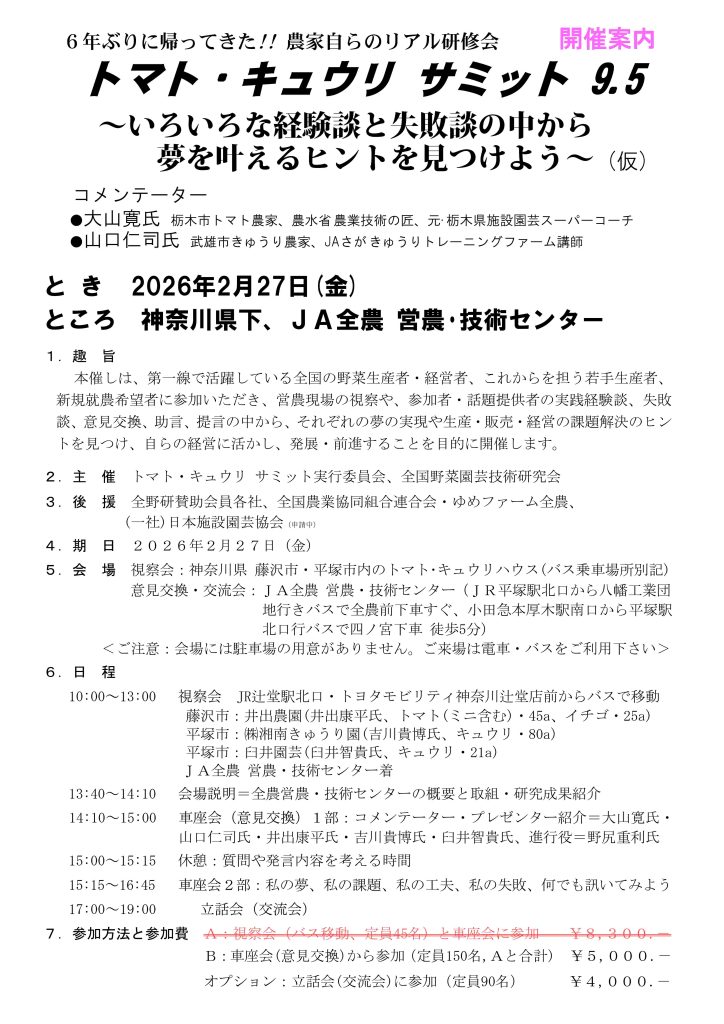「雨ニモマケズ」で始まる宮沢賢治の有名な詩は、彼が岩手の実家で闘病中だった1931年に書いたものとされる。「世間から評価されなくても、人のため自己犠牲を惜しまない人間でありたい」。そんな賢治の志が表現されている。
この詩には、1日に「玄米4合」を食べるという表現が出てくる。ずいぶん多いように思えるが、旧日本軍では「1日6合」が基本だったそうだ。実際の戦場では多くの兵士が餓死したが、基準として4合が多いとは言えない。
1合の重量が150gとして、4合は600g。農林水産省によると、昨年の国民1人あたりの米消費量は1日139gだから、4合が戦前の標準なら4分の1以下になった。戦後のピークは1962年の324gなので、そこからみても6割近い減少だ。
ちなみに、この詩が書かれた年に満州事変が起き、その2年後に米穀統制法が成立。政府が公定価格で無制限に米を買い入れる仕組みが導入された。37年に日中戦争が始まると、また2年後に米穀配給統制法ができ、米は配給制になった。そして、太平洋戦争開戦(41年)の翌年には食糧管理法が制定され、麦・イモ類を含む主要食糧が国の全面的な統制下に置かれた。戦時下の国策に米も組み込まれていったことがわかる。
その食管法制定から来年で80年。同法は戦後の食料難でも役割を果たし、60年代末からは逆に「米余り」に対応する機能を発揮した。ただ、その運用が需給ギャップを拡大させ、多大な財政負担を伴う過剰米処理や減反政策の矛盾も生んだ。ある元農林水産事務次官は「食管法は実に便利な法律だったが、そこに欠陥もあった。(困ったら国が何とかしてくれるという)『国が国が病』を生んだ」と振り返る。
食管法廃止(95年)から四半世紀を経て今も米余りは止まらず、転作の強化や市場隔離、備蓄米の買い増しなど、また同じような議論が繰り返されている。「市場原理に委ねよ」とは言わないが、国策に引き回され、国策に寄りかかる米作りが限界なのも明らかだ。一時しのぎの対策ではなく、米農業のあり方を根本から議論しなければならない。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2021年12月25日号掲載