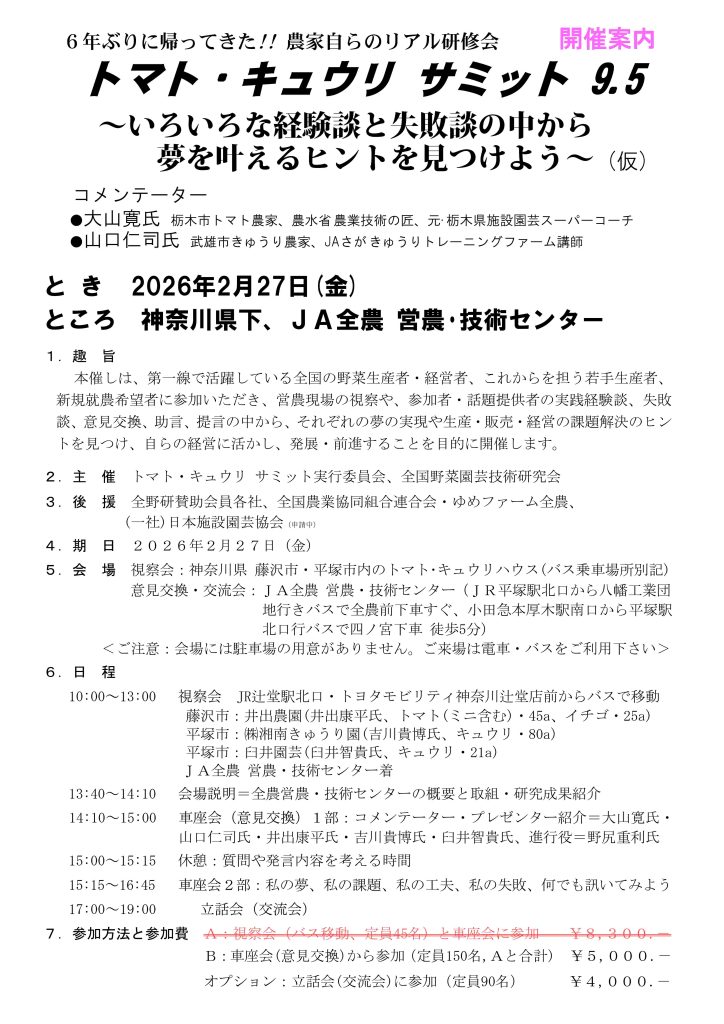平成が終わる。元号が替わって世界が一変するわけではないが、来し方行く末を考えるきっかけにはなる。この30年、食と農の世界を大きく変えた要素の一つとして「コンビニエンスストア」に着目したい。
コンビニは平成期に急拡大した。日本フランチャイズチェーン協会によると、店舗数は1988(昭和63)年に1万店を超え、89年(平成元年)には1万6466店になった。昨年末時点は5万5743店と30年間で5倍に増えた。売上高も08年に百貨店を抜き、スーパーに肉薄している。
スーパーも同じ時期、規制緩和やモータリゼーションを背景に郊外への大型店進出が進んだ。中心市街地の商店街は「シャッター通り」になり、その穴をコンビニが埋めた。当初は若者が利用するイメージが強かったが、最近は高齢者のライフラインになっている。
郊外の大型店立地では多くの農地が失われたが、コンビニも農業を大きく変えた。ある専門紙の試算では、小売価格100円強のおにぎりに使われる米の生産者手取りは十数円、生産費を差し引いた利益は2円程度という。
また、コンビニ弁当に使われる食材の多くは廉価な輸入品だ。神奈川県三浦市の小学校児童らが「総合的学習」の一環として調べたところ、弁当1個分の食材の輸送距離は計16万km、つまり地球4周分だった。三浦半島はダイコンの大産地だが、地元のダイコンは使われていなかった。
平成の終わりに、コンビニも曲がり角を迎えている。人手不足で24時間営業が厳しくなり、店主らの悲鳴を受けて「時短」実験が始まった。外国人留学生ら若い店員に交じり、中高年の店主が自ら深夜のレジに立つ姿も目立つ。特定エリアに集中出店する本部の「ドミナント戦略」で、過当競争を強いられていることも背景だろう。賞味期限が近い商品を見切り販売させず、過剰な仕入れを迫るシステムも食品ロス削減の見地から問題が指摘されている。
とはいえ、既にコンビニは国民生活に欠かせないインフラだ。日本社会が本格的な「縮退」の時期に入った今、目先のコンビニエンス(便利さ)より持続可能なビジネスモデルを、国民全体で考えるべき時期だろう。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2019年4月25日号掲載