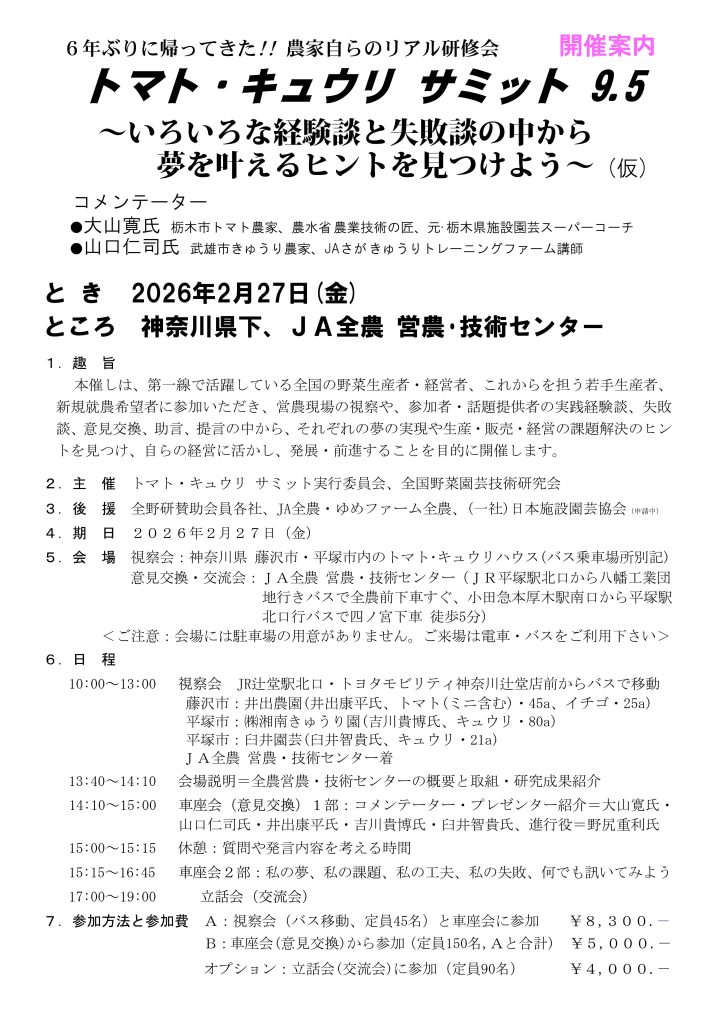気候変動対策に対応しての農政見直しに向け、「みどりの食料システム戦略」の策定作業がすすめられ、この3月末にはその中間とりまとめが公表され、パブリックコメントを踏まえての修正を経て、5月の中旬にも決定される見通しだ。
「2050年までに目指す姿」として、CO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減、耕地面積に占める有機農業の面積を25%(100万ha)に拡大、等のかなり思い切った目標が掲げられている。最終的には若干の微調整はあっても、大筋は既に固まったとみる。
4月21日には生産者を中心とする持続可能な農業を創る会で、農水省の事務次官以下との再度の意見交換を行った。話題の中心は、戦略決定後、これをどのようにして現場におろし、具体的な取組みにつなげ、かつ実効をあげていくか、となった。人類の生存まで危機にさらされかねない地球温暖化という脅威を抑制していくという、もはや逃れられない切実な大課題のために、今回の戦略を絵に描いた餅にすることが許されるような状況ではない。今後、戦略策定した農水省は勿論のこと、生産者、消費者、流通も含めて各々が自らの問題として受け止め、かつ自己責任をもって取組みを果たしていくことが欠かせない。
このための大きなカギを握っているのは農協だ、と言っても決して過言ではない。全中会長は「『みどりの食料システム戦略』は重要なテーマだ。先般の中間とりまとめでも、我々の認識では方向性は一致しており、共に取り組んでいかなければならないと感じている」と語っているが、むしろ全国連を含めた農協が率先して取組をリードしていくことなくしては本戦略の実効性自体が大きく損なわれかねないのが実情ではないか。
そこで思い起こされるのが韓国での農協の取組みだ。韓国での有機農業が占める農地面積割合(16年)は1・2%と日本の0・2%(認証ベース)を大きく上回る。しかも有機農業に無農薬栽培をも含めた親環境農業の割合は4・9%(17年)と、日本との格差は大きい。この親環境農業の推進に大きな役割を発揮してきたのが、全国農協中央会が展開するハナロマートでの親環境農業農産物の販売・流通であり、単協レベルではソウル市のカンドン農協が率先して手掛けた親環境農業支援センターの開設や、消費者を対象とした有機農業アカデミーの開設、有機たい肥購入への助成金支出等の一連の取組みである。
日本の場合には、例えば、まずは農協の中に有機農業に関心を持つ生産者を集めての有機農業部会を設け、ここで技術や農法等を習得・実践してもらいながら、各地区における有機農業推進のリーダーとなってもらい、地域営農計画の中に有機農業を位置づけ、その割合を引き上げていく。農協は販売事業で有機農産物の販路を獲得・開拓していくとともに、消費者との交流を促進していく。こうした取組みを県連、全国連がバックアップしていく仕組みも一手だ。JA自己改革の第二弾として、みどり戦略に対応した取組みの展開を期待したい。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2021年5月5日号掲載