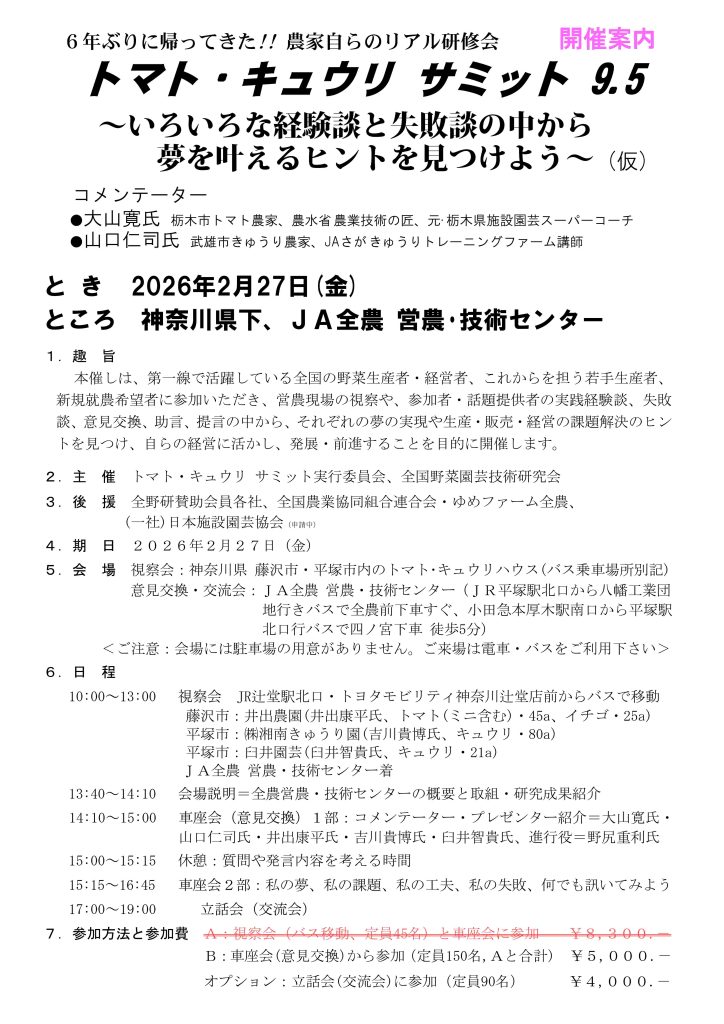「うらうらに照れる春日にひばり上がり 心悲しもひとりし思へば」
万葉集で大伴家持が歌ったヒバリは春を告げる鳥の代表格だが、大都市近郊では見なくなった。営巣に適した農地や草むらが減ったからだ。
昨秋、福島県飯舘村でトルコギキョウなどを生産する高橋日出夫さんに取材した時、その鳥の話が出た。「(原発事故の避難指示が解かれ)村に戻って一番うれしかったことは?」と聞いたら「ヒバリがいたこと」という答えが返ってきたのだ。
避難する前、高橋さんの畑には毎年ヒバリが巣を作った。高橋さんはそこだけ収穫を控え、ヒナたちが巣立つのを見守った。除染作業で重機が走り回ったので、もう来ないだろうと思ったが、帰還した17年もヒバリは姿を見せた。「うわぁ、と思った。ああ良かった、おれも頑張るぞ、という気持ちになれた。ちょっとしたことだけど、それがうれしかった」
確かに「ちょっとしたこと」かも知れない。しかし、それを喜べる日常を取り戻すということが、高橋さんにとっての「復興」だった。
福祉事業を営むNPO法人の理事長から花き生産者に転じた浪江町の川村博さんは、こう言った。「特別な10年だった。避難して困っている人への支援など復興のお手伝いもした。でも、そろそろ普通の生活に戻らないといけない」
「原発事故が風化していないか」と尋ねると「忘れてもらって構わない。人はそれぞれ置かれた状況の中で花を咲かせるのだから」と語った。
被災者一人一人にとっての10年がある。誰もが前を向けているわけではないし、いま前向きになれている人も、多くの悲しみや苦労を乗り越えて新たな日常を築いてきた。
「忘れてもらって構わない」は、自分自身に向けられた決意の言葉だろう。川村さんは「できれば、多くの人にここへ来てほしい。変わりつつある被災地の暗い面も明るい面も見てほしい。そして、エネルギー政策のあり方などを話し合う材料にしてもらえたら」とも話した。
今年もまた春が来た。天に駆け上るヒバリのさえずりは喜びの歌か、あるいは失われた日々を惜しむ悲しみの歌か。10年を過ぎても季節は巡る。その小さな声にこれからも耳をすませ続けたい。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2021年3月25日号掲載