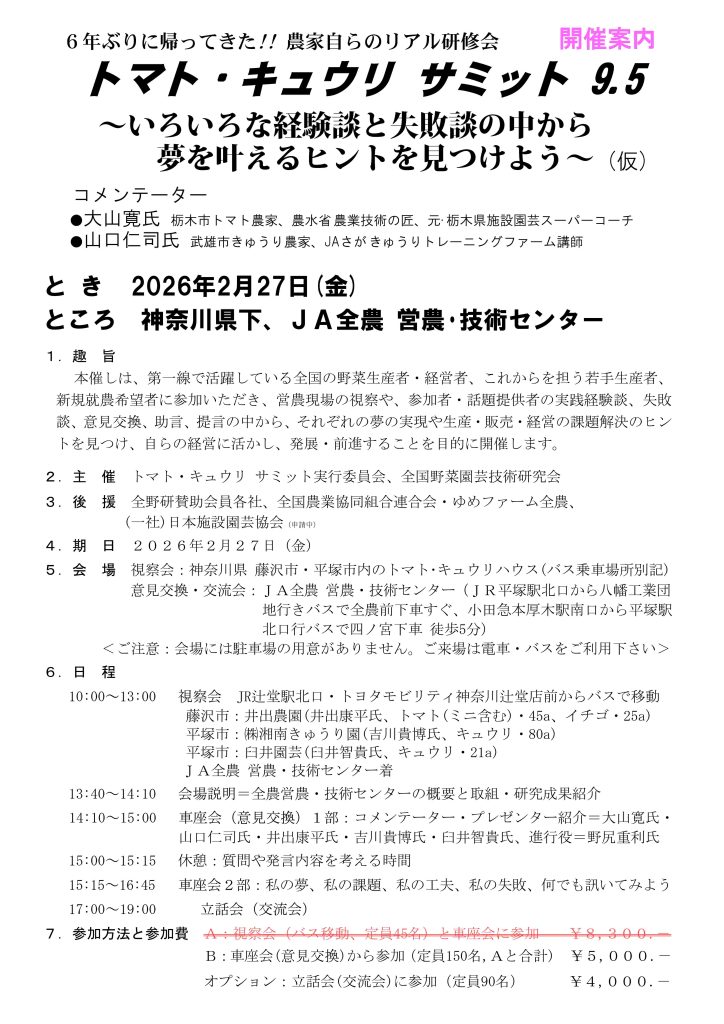深い峡谷にいるようだった。10年前、東日本大震災に続く原発事故で計画停電になった東京都心の夜だ。高層ビルに区切られた漆黒の空に無数の星が瞬く。人工の光がなかった時代には当たり前だった星空が唐突に戻ってきた。不思議な感慨に襲われながら「この光景を忘れないようにしよう」と思った。
だが、忘れていた。思い出させたのは「震災10年」の節目ではなく、コロナ禍で再びもたらされた街の静けさだ。ただ、今は星が見えない。
震災直後には「きずな」が叫ばれた。「日本はチームだ」という言い方もあった。「滅亡」を思わせる被災地の惨状と、闇に沈む東京。小さな集落で肩を寄せ合って暮らした太古の人々のように、人知を超えた力への「おそれ」が人々を結束させた。助け合い、譲り合う被災者が称賛され、大勢のボランティアと支援物資、支援金が被災地に集まった。
しかし、長続きはしなかった。放射能汚染や賠償金を理由とした、原発事故の避難者への差別といじめ。「福島の被災者には同情しなくていい。彼らはたくさんもらっているから」と言う人もいた。「きずな」はズタズタに切れた。そして今もコロナ禍で感染者や医療従事者が差別され「自粛警察」が横行する。
地震は天災だが、原発事故やコロナは人災だ。パンデミックも乱開発による自然破壊、大都市への人口集中、グローバルな人の移動が背景とされる。地球温暖化も含め、人類は自ら招いた災厄をコントロールできない。そして、何よりも連帯が求められている時に、いがみ合い、傷付け合っている。
イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、テクノロジーの暴走で人類が自滅に向かう可能性を論じた著書「ホモ・デウス」でこう指摘した。「私たちにはブレーキは踏めない」。なぜなら「ブレーキがどこにあるのか、誰も知らない」し「誰かがブレーキを踏むことにどうにか成功したら、経済が崩壊し、社会も運命を共にする」からだ。
21世紀最初の20年を経て、我々は出口の見えない深い谷底にいる。コロナ禍が去っても、震災から10年が過ぎても、忘れることは許されない。そして、暗夜に星を探し続けなければいけない。
(農中総研・特任研究員)
日本農民新聞 2021年1月25日号掲載