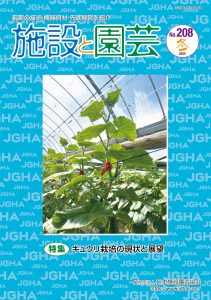「令和の米騒動」は江藤農水大臣の失言問題で一転。競争入札で備蓄米を放出していたものを、早々に随意契約に変更。備蓄米はおよそ半値での販売へと誘導をはかりつつあり、生産構造のあり方は横に置かれて、消費者対策への注力は著しい。
小泉農水大臣の行動力とスピード感は大したものであると感心させられるが、一方で農協批判、農協改革を煽っているかのような言動を見逃すわけにいかない。これらを受けてマスコミは、備蓄米の競争入札でその大半を全農が落札したものの、市場に出回ったのはその一部にすぎず、全農・農協が米価を釣り上げている、との批判を繰り返す。農協は米を買取せずに概算金払いで精算を遅らせてもうけている等の尾ひれまで付く。
ここで強調しておきたいのは、こうした農協批判に対して農協事業に対する理解獲得のための事業見直しや広報でのさらなる努力が必須だということだ。概算金払いは、集荷前に必要な肥料等資材の購入に要する資金を前払いし、これを運転資金として利用可能にするもので、それなりの必要性があって系統共販の仕組みの一部として定着させてきたものだ。現在では概算金払いを基本としながらも、買取販売を選択可能にしているところも増えているようだ。さらに委託販売、共同計算も含めて系統共販独自の仕組みがあり、歴史の中でそれなりの役割を果たしながら今日に至っており、こうした実情をもっと知らしめていくことが欠かせない。
こうした中、6月25日付の日本農業新聞では、JA全農とっとりが、これまでの相場や需給を踏まえて設定していた米の概算金を、県内農家の9割を占める2ha規模以下の農家の再生産に必要な費用を積み上げる「生産費払い」基準に見直したことが報じられている。こうした時代・環境の変化に合わせた事業の見直しも重要であり、JA全農とっとりの時宜を得た米概算金のあり方見直しは特筆される。
もう一つ注目しておきたいのが、6月5日の衆議院農林水産委員会での小山展弘衆議院議員(立憲民主党)による質問とこれに対する小泉農水大臣の答弁である。小山議員の質問は、4月8日に江藤前大臣が、国際協同組合年に当たり、政府・農水省は協同組合の果たす役割について一定の評価をする旨の答弁をしているが、小泉農水大臣はこれを引き継ぐのかも含めて、認識を問いただしたものである。これに対して小泉大臣は、まず5月27日の衆議院、5月28日の参議院で、国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る国会決議が可決されたことに触れ、自らこれに賛同することを述べた。そして江藤前大臣が答弁したとおり、事業を総合的に行うことで、農林漁業や地域社会の維持発展に重要な役割を担っていると承知している、との答弁を引き出したことはきわめて重要である。
今年が国際協同組合年であるだけでなく、昨年の第30回JA全国大会での決議も踏まえて、あらためて農協の存在意義を噛みしめ直すと同時に、誇りをもって新しい時代に対応した系統共販のあり方を見直し・再構築していくことが求められる。農協は日本の食料安全保障を支えるキーだ。農協なくして日本の農と食を守っていくことは不可能なのだから。
(農的社会デザイン研究所代表)
日本農民新聞 2025年7月5日号掲載