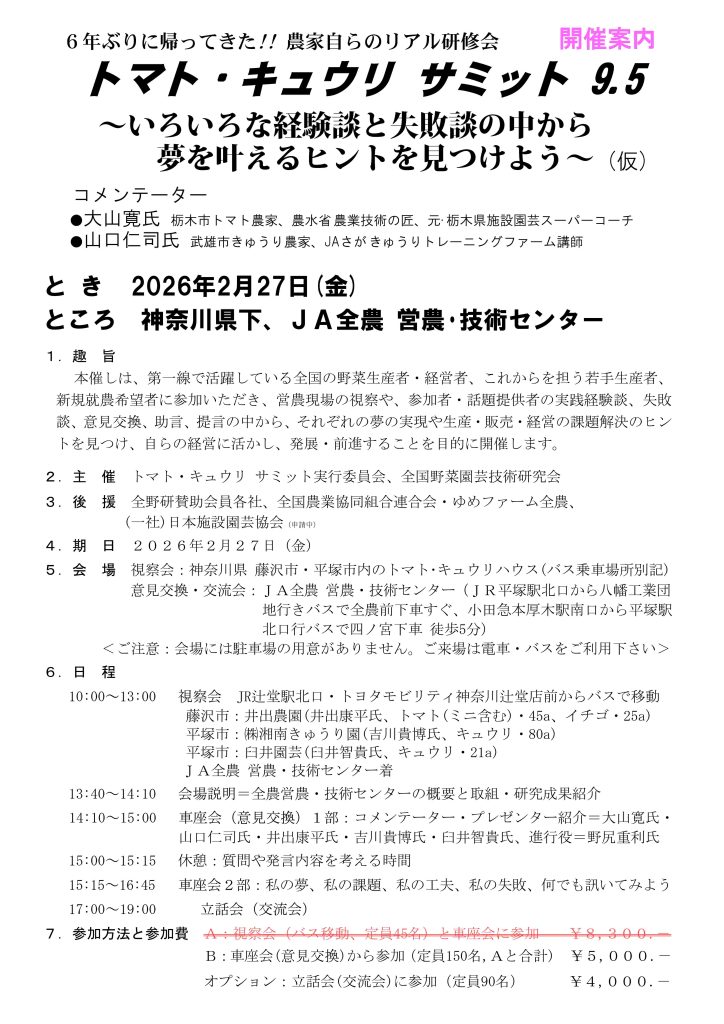正月気分を吹き飛ばした元日の能登半島地震。筆者も帰省先に津波注意報が発令され、老母の手を引いて右往左往した。しかし、被災者の苦難とは比べようもない。心からお見舞いを申し上げ、亡くなった方々の冥福を祈る。
新聞記者時代から災害には縁があった。新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(11年)、熊本地震(16年)では現地へ行った。福島県の被災地には今も時折、足を運んでいる。
被害の形は土地によって多様だが、これらの被災地に共通するのは(仙台圏を除けば)過疎化・高齢化が進む農山漁村という点だ。報道を通じ能登の状況を見ていると、既視感を覚える。
中越地震では崩れた土砂が川をせき止めて「土砂ダム」が形成され、多くの道路や集落が水没、新潟県山古志村(現・長岡市)などで一時60以上の山間集落が孤立した。能登でも土砂崩れや道路の損壊で最多時30以上の集落が孤立状態になったという。避難経路が限られる山村地域の課題が改めて浮かぶ。
能登半島地震(本震)の震源地のすぐ北に珠洲市高屋町という地域がある。北陸・関西・中部の3電力が計画した珠洲原子力発電所の建設予定地だ。住民の粘り強い反対運動で03年に凍結されたが、もしここで原発事故が起きていたら、同市に加え輪島市、能登町などの広範な部分が30キロ圏内に入っていた。福島第1原発事故では30キロ圏外にも放射性物質が流れ、多数の市町村で避難指示が発せられた。能登半島の場合、避難もできないまま放射能を浴び続ける集落住民が大勢出たのではないか。
単なる仮定の話ではない。今回の地震で、半島南西部に立地する北陸電力志賀原発(運転停止中)では変圧器の油が漏れ、外部からの電力供給が一時止まった。停止中も使用済み核燃料は冷やし続けなければならず、外部電源は不可欠だ。津波による外部電力喪失が引き金になった福島の事故を想起せずにはいられない。
1日も早い被災地の復興と被災者の生活再建を祈る。同時に、この災害から何を学ぶかも重要だ。原発の立地・再稼働を推進する地域に改めて問いたい。「それでも原発との共生は可能か」と。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2024年1月25日号掲載