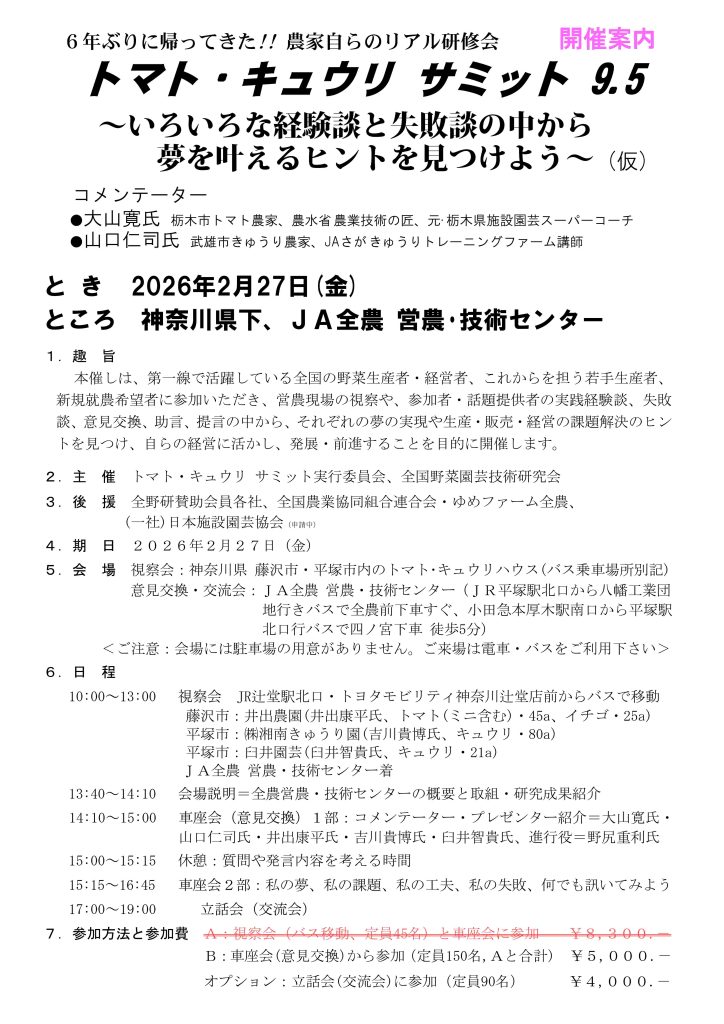福島第1原発事故で約6年間の全村避難を強いられた福島県飯舘村。その地で和牛の繁殖を営むある若手農家は、母牛の体に取り付けたセンサーで体温を測定し、出産などの兆候をスマートフォンに知らせるシステムを活用している。子育てなどの事情で隣町からの「通い農業」を続ける彼にとって、離れていても家畜の状態が把握できる仕組みは心強い味方だ。
人口減少と高齢化が一気に進み、農業の担い手が足りない被災地では、スマート農業の導入が進められてきた。南相馬市小高区では、自動運転のトラクターなどを使い、100ha規模で米やナタネなどを生産している株式会社もある。営農情報を統合的に管理する「農業クラウド」も導入し、その先進的経営に魅力を感じて入社する若者が相次いでいる。
しかし、技術だけで突破できない壁もある。たとえば離農者から託された水田は各地に分散し、移動に時間がかかる。1人で複数台を操作できる自動運転の農機も、公道を走る際は人が乗らなければならず、作業者の数はあまり減らせない。
イノシシやサルの被害も深刻だが、それを防ぐ電気柵の管理が大変だ。バッテリーの一部は交換が不要なソーラー式にしているが、雑草が電線に触れると漏電して効果が落ちるため、定期的な草刈りが欠かせない。
以前は集落住民が共同で草刈りや水路の掃除をしていたが、そうした活動が再開されない地区も多く、そこも耕作者の負担になる。基幹的な作業(耕起・作付け・防除・収穫)に劣らず除草や水路の管理、鳥獣害対策は重要だが、そこをカバーする技術の開発はあまり進んでいない。
被災地だけの問題ではない。全国的にも5年間に2割のペースで農家が減り続ける中、農村地域の多くが同じ困難に直面している。技術開発は「こんなことができる」という夢の実現だけでなく「現場で使える、現場が求めている」ものに重点を置くべきだろう。
加えて言えば「半農半X」のような形も含め、農業・農村の関係人口や定住人口を増やしていく取り組みが重要だ。農業のイノベーションが単なる「人減らし」ではなく、農業のサポーターを増やし、農村に活力と「にぎわい」をもたらす力となるよう望みたい。
(農中総研・客員研究員)
日本農民新聞 2023年1月25日号掲載